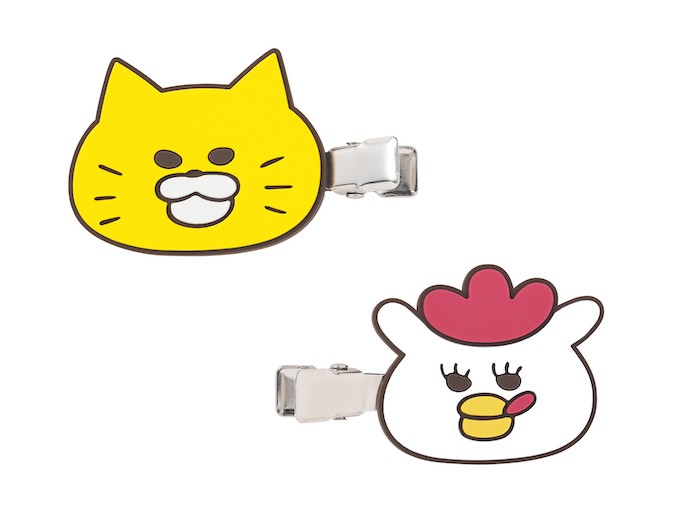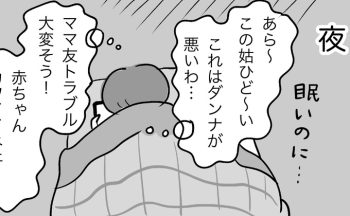『生きるとか死ぬとか父親とか』著者ジェーン・スーさんインタビューweb版
ここにいていい
アメリカで解放された
大学在学中にアメリカのミネアポリスに1年留学。ジェーン・スーというペンネームは、この時代のルームメイトから「ジェーン」を借用、「スー」はアジア人らしくとつけたものである。
――留学はご自身の選択ですか。
父は「これからは英語を喋れなきゃ話になんない」ということで、早くから私を留学させたがっていました。まず中学生のときに、父が「留学しろ留学しろ」と言うのを、母が「中学から留学させる親がいるか」って懸命に止めて。高校のときも、「20歳過ぎなきゃダメ」と止めてたんですね。今考えれば、両親はそういうことでもケンカをしていたんでしょう。で、20歳のとき大学の交換留学システムに登録して、アメリカに留学しました。
――その経験はいかに。
すごくよかったです。楽しかった! そこに関しては、母に対して「高校で行かせてくれればよかったのに」という気持ちもありますね。ただ高校で行っていたら、私、多分帰ってきてなかったと思う。だからまぁよかったのかな、とも思いますけど。
――アメリカで新しい人生が開けた、みたいなところがあった?
それこそアメリカには私より体の大きい人がたくさんいるので、服屋さんに行っても私の上にまだまだサイズがあるんですよ。「うわぁ~、ここにいてもいいんだ」と、居場所が見つかったという気持ちでした。言いたいことを言っても悪目立ちすることがなかったのも、私には快適だった。留学して初めて、日本ではいかに「女の人はこうあるべき」とか、「女の人とは」と型にはめられていたかに気がついたんです。
――ああ、なるほど。ご両親から、「女のくせに」とか、「女だから」という言葉を聞いたことはありましたか。
両親からは一切なかったので、外に出て社会が押しつける女らしさにびっくりしたんだと思います。
だからアメリカに行って、「やった~!」って気分ですよね。アメリカではアジア人なのでマイノリティなんですけど、個としてはかなり埋没できるっていうのが嬉しかったんです。小さな頃から「力を手加減しなさい」と言われ続けてきたから、自己表現に関しても手加減しなくていいということをすごく喜んだのを覚えてますね。
――それまでは大きいこと、力が強いことに遠慮があったんですね。
あったと思います。家族の外に出たときはありました。自分は力が強いとか体が大きいとか言いたいことは言うとか、そういうことは十分自覚していたと思うので、学校や社会ではどこかで加減していたんだと思います。
――ご両親は娘の変化を歓迎されたのでしょうか。
帰ってきた最初の頃は、アメリカナイズされた私を見て、両親はちょっとギョッとしてましたね(笑)。ただ私もその辺はレーダーが働いて「1年しか行ってないのにアメリカナイズされてるのは格好悪いな」と思い、そこは自分で早急に修正しました。
帰国して1年後の1996年に大学を卒業し、就職。少女の頃から音楽好きで、大学時代は早稲田大学のサークル「ソウルミュージック研究会GALAXY」に所属していたジェーンさんは、迷わず就職先にレコード会社を選ぶ。就いたのは宣伝の仕事だった。
――就職先はレコード会社しか考えられなかった?
それぐらいしかやりたいことがなかったんです。「音楽が好きだったらレコード会社でしょ」という短絡的な考えですね。いまだに5年後に何をやってるかとかあんまり考えてないところがあって、当時から成長戦略的なことを考えたことはありません。母は入社をすごく喜んでくれました。ところが、入社半年で両親がいっぺんに倒れてしまったので、そこから半年くらいかな、介護休職をしてるんです。なので、母には働いている姿はほとんど見せられなかった。

24歳のとき母が逝く
あんな悲しみはない
社会人になった年の夏、父は肝臓に病気が見つかり、インターフェロン治療のために入院中だった。そして、体調の悪さを押して毎日父の見舞いに通っていた母にガンが見つかる。「お母さん、お願いだからお父さんより先に死なないで」と口癖のように言い続けた娘が受けた衝撃は、大きかった。
――お母さんの発病は突然のことでした。
私が成人した頃ぐらいからかな、旅行好きの母が年に1回海外へ旅行に行くようになりました。自分の人生をようやく楽しみ始めた頃だったんです。体調が悪いのは私たちから見ても明らかだったし、母自身も分かっていたんだと思うんですけど、人間ドックでは異常は見つからなかったし、「それ以上はあんまり調べたくない」と言ってました。でも、入院中の父を看病する母の体調は日増しに悪くなっていき、父もお見舞いに来る母がとても疲れていると心配していた。それで父と私が「頼むから病院に行ってくれ」と母に懇願したんです。蓋を開けてみたら、父より母のほうがずっと悪くて、すい臓ガンでした。母の検査結果を、私も一緒に聞きました。
ショックでしたよね。当時は今と違って、ガンは「すぐ死んじゃう病気」というイメージが強かった。母が可哀想だったし、自分も可哀想だった。なんで私とお母さんがこんな目に遭わなきゃいけないんだという憤慨もすごくありました。悲しみというより不安と憤慨が大きかったです。
――「お父さんより先に死なないでね」と言っていたのに……。
父が家庭人ではないのはよくわかってましたから、父とふたりは嫌だという気持ちがずっとありました。だってわがままだし、本当に好き勝手に生きてる人なんで、「この人とふたりで残されたらきついな」と思い、「何にも残さなくていいから、お母さんの方が長生きしてくれ。お父さんとふたりきりにはしないでくれ」と母に言ってたんです。けれど、残念ながら願い叶わず。
――お母さんも心残りだったでしょう。ご自分の病状をご存じだったと思いますが、言い残されたことはありましたか。
「仕事は辞めるな」と言ってましたね。辞める気はさらさらなかったんで、「うん」と適当に返事をしていました。多分、自分のせいでキャリアが止まってしまってはいけないと考えて、言うべきことを私に言ってくれたんでしょう。でもまさか、そのまま仕事を最優先して、「ひとりでやっております」が今日まで続くとは、母は思ってもみなかったかもしれません(笑)。
――母の呪縛かも。
それはないですね。「お母さんが辞めるなって言ったから」と、自分の行動を規制したことは一度もありません。母は、私が復職してから半年後、1年半ぐらいの闘病生活を送り、64歳で亡くなりました。私はそのとき、24歳でした。
――働く娘はご覧になったけど、今の活躍は見られなかった。
生きていたら、喜ぶと思いますよ。すごい喜ぶとは思う。でも、生活習慣のあれこれについては、やっぱり、今も叱られていたと思いますけど(笑)。
――亡くなってから、「お母さんの人生をもっと聞いといた方がよかった」と思ったことが、お父さんについて本を書こうと思ったきっかけでした。
本当にそう思いましたから。母にも「女」の面も「妻」の面も、それこそ父親が外で好き勝手やってることについての修羅の部分も絶対にあったはず。でも、そういうものは全部編集してから私に見せてくれてたんで、私はつらい思いはしなくてすんだんですよね。それでもやっぱり、「実際女としてどうだったのよ?」とか、「じゃ、なんで離婚しなかったのよ?」という話は聞きたかったです。生きているときには、母はそんな質問をさせませんでした。やっぱり、「母として全うする」ことが彼女の大きいテーマだったんでしょう。
――外に女性がいる父と別れなかった母への怒りはありませんか。
全然ありません。母は父が好きだったんだろうと思うし、父も母が大好きだった。別れなかったのは、多分、ふたりには私も入り込めないような絆があったんだと思います。母も、父に関してはあんまり合理的に考えられなかったんだろうなあって思ってます。理性と感情は別なんでしょう。
――喪失感は大きかったと思いますが、お母さんがいなくなって何が一番変わりましたか。
父との関係ですね。それに、母の死が私の人生に意味することはなんなのかと考えました。この間、永六輔さんのお嬢さんの永麻理さんと対談したときに、お父さまを亡くした麻理さんがおっしゃったんです。「うちの父は死んでみせてくれたんです。死んでみせるのが、親の最後の仕事だと思う」と。「あっ」と思いました。母もそうだったな、って。あれほど悲しいこと、つらいことはありませんでした。お葬式や四十九日とか初七日も含めて、私にとっては全部初めてのことじゃないですか。こういう儀式があるんだよということも含めて、自分の命と引き替えに「死」というものを教えてくれたんだなと思います。