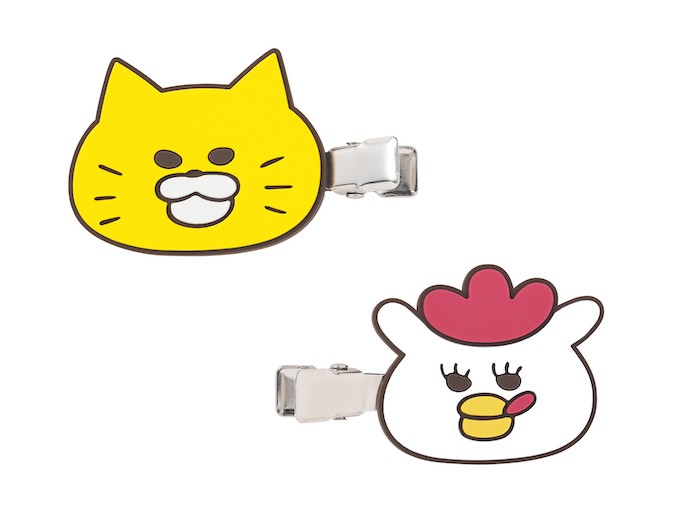『生きるとか死ぬとか父親とか』著者ジェーン・スーさんインタビューweb版
投資は集中
過剰な期待はなし
本郷のマンションから小石川の一戸建ての家に引っ越したのは、幼稚園のとき。貴金属業を営む父の会社と自宅がひとつになった立派なビルだった。ジェーンさんは、ひとり立ちするまで、そこで大きくなった。
――小石川のおうちは豪邸です。
父の職場と一緒になっていたこともあって、大きいビルでしたね。1、2階が父の会社で、3、4階が自宅です。大きな家に住んでいるという自覚はありましたが、今考えれば、自宅部分は2LDKくらいだから、特に大きな家でもなかったのかも。
――経済的に豊かに育っているという自覚はありましたか。
それがね、国立の学校だと周りがそこそこ金持ちなんです。「すっご~い」というレベルの友達もいましたから、うちはお金持ちだと認識していた記憶はないです。小学生時代はお小遣いもひと月500円だったし。派手な贅沢をしている自覚はありませんでしたが、服とか、必要なものは惜しむことなく買ってもらっていました。私、被服費には相当お金を遣わせたと思います。体がすごく大きかったんで、着られる子ども服がないんですよ。着られるサイズのものはおばさん向けの服しかなかったら、中学のときには、ぶかっとしたデザインのDCブランドを着てました。「DO!FAMILY」とか「I.S.」とか、「PERSONS」とかデザイン的にサイズ感に余裕がある服を着て遊んで、すぐに汚してしまっていた。母はたまったもんじゃなかったでしょうね。
――ユニクロもなかったあの頃は、子ども服のサイズも限られていました。小さな頃から体が大きかったことは、ジェーンさんの人生にどう影響していますか。
20代に入っても30代に入っても、人生全般にわたって影響しましたね。40代になってようやく解放されたけれど、小さな頃からひとりだけ周りより大きかったし、小学校卒業するときには身長が160cm近くありました。同級生はみんな私より細く、体が薄いので、違和感があるんですよね。子どもの頃も、高校生になっても、なんで私はみんなと同じ格好ができないんだろうと思ってた。子どもの頃は、男の子たちより体が大きいっていうだけでからかわれましたから。小さくて可愛いものに対するコンプレックスはずっとありました。
力も強かったんです。幼稚園で男の子を突き飛ばしたときもそうだけれど、あの頃は、自分だけ力が強いなんて自覚はなかった。でも、親には「ほかの子どもに比べたらあなたは力が強いんだから加減しなさい」と言われていました。だったら、力を使うような運動をさせてくれればよかったのに。親は一所懸命私のことを考えていろいろ習わせてくれて、中学からはテニスを習ったんですけど全部見当違いでした。そういうものではなくて、重量上げとかをさせればよかったのに(笑)。
――パワーの人なんですね。
有酸素運動じゃなく、無酸素運動の方が絶対得意だったはずなのに、親はさせる運動を間違ったなとは思います。
――初潮も早かったのではありませんか。それは、お母さんが教えてくれた?
小学校4年のときです。教えくれたのは、母より学校の方が早かった。ナプキンの使い方は母に教えてもらいました。母は祝いの赤飯を炊いてましたね(笑)。夕飯の席で、父が「おお、よかったな」みたいな感じで言うので、ばつが悪かったのを覚えています。でも、ばつが悪いなぁと思いながら、「多分こういうのが家族の通過儀礼なんだな」というのはちょっと感じていました。
――その頃から、コラムニストの素地があったみたいです。
どうなんですかね、わからない。作文とか下手だったし、中学ぐらいになって、流行小説を読んだりして、エンターテインメントとしての読書はしてたけど、それに影響されてなにかを書いたことはありません。ただ創作ノートみたいなのものを自分で作ってはいたんですよ。多分それって、「創作ノートを持っている」ことが喜びであっただけで、何かを書き終えたことなんか一度もない。あとで見たら、歌詞みたいなのが書いてあって、本当に3行ぐらいで終わってました(笑)。
――みんな、そんなものじゃないでしょうか。小さな頃の話に戻します。おうちが建ったとき、子どもには危ないかもしれないとお父さんが心配して、手すりを替えたとか。子煩悩な父親に見えますが。
「これじゃ怪我する」と言って、突然手すりを替えさせていました。あと、歯並びを気にしていて、小学生のときは歯列矯正をさせられていましたよ。いろいろ、気にはしていたんでしょう。ただ父は私を可愛くてしょうがないんですけど、面倒は見たくないんですよ。そこは「昭和のお父さん」。子どものことは目に入れても痛くないぐらい可愛いんだけれど、手を引いて動物園に連れて行き、ひとつひとつ動物のことを教えてくれるとか、そういう教育的なものを授けてくれることはほとんどなかったです。ただ「わ~、可愛い~、じゃあね!」みたいなそういう感じですね(笑)。
――小さい頃、お父さんのことは好きでした?
母の方が断然好きでしたね。一番好きなのはお母さん! まあ、あの頃はみんなそうだったんじゃないのかな。たまにものすごく子煩悩でちゃんと教育を授けるタイプのお父さんがいて、その娘は「お父さんが好き」と言ってましたけれど。
――ご両親には、ひとり娘への期待があったのでは。
あったのかもしれないけど、何も覚えてないですね。「オール5じゃなきゃダメよ」みたいなことで怒られたこともないし……。通信簿も、成績がいいとか悪いとかというよりも、きちんとやっているかとか、多分そういうところを見られていたと思います。苦手な科目に対して努力をして少しでも点数が上がっているか、極端にできないものがないか、そこですね。母は、私が何が得意で何が不得意かは全部把握していました。
中学に入ったばかりの頃は、数学がすごく苦手だった。で、私自身は、「苦手でいいや」という感じだったんですよ。「悔しいから頑張る」みたいな負けず嫌いではまったくなかったから。いまだにそうなんですけど。
――勝ち気じゃない。
まったく違う。「どうぞどうぞお先に」というタイプです(笑)。だから数学が全然できなくてもどうでもよくて、ぽわ~っとしてたら、2年生のときに、母が近所で数学を教えてくれる寺子屋のような塾を見つけてきたんです。最初におばあちゃん先生に面接されたとき、「本当はここの塾は中学1年からじゃないと入れない方針なんだけど、あなたのお母さんが何日も通ってお願いされたから、特別に入れます。ちゃんとそれをわかっておきなさい」みたいなことを言われたんです。母は念が強いんですよ(笑)。やるとなったら必ずやる人でした。ありがたいですよね。
―― 高校は、カトリック系の女子校です。
エスカレーターで幼稚園から小学校、中学校まで行けたのはラッキーでした。でも、小、中になると受験してすごく頭のいい子たちが入ってくるんで、私の成績じゃ内申点が足りなくて附属高校には行けなかったんです。特に悔しかった覚えもなくて、受験に際しては、自分の行きたいところを3校ほど選んで、受けたんです。母は、「この学校に行け」なんて言いませんでしたから。
ただ、そのときに面白かったことがありました。私は、授業は男女に分かれるけれどクラブや生徒会は男女一緒という「男女別学」の高校に行きたかったんですよ。ところが、先にその高校よりもちょっと偏差値が高い女子校に受かっちゃったんです。で、母はせっかく受かったのにと思ったんでしょうね。機転を効かせて別学の高校の受験日に、そのあとに記念受験することになっている青学のことを言い出し、「青学の記念受験が成功するようにブルーマウンテンというコーヒーを飲みに行こう」と私を連れ出し、別学の高校を受けさせないで終わっちゃったんです(笑)。母が自分の意志を強引に押し付けていたら私も反発したと思うけれど、そんなユーモアのあるやり方だったから。
――お母さんは娘にできる限りいい教育をつけてあげたかったんですよ。
きっと少しでもいいところに、と思ったんでしょうね。でも、うちの両親のいいところは、「(自分たちが)これだけやったんだから」というのはまったくなくて、「これだけやっても、私たちの子だからこの程度だな」という諦めをしてくれたこと。「親ができる限りのことはやるけど、結果がうまくいかなくても、私たちの間に生まれた子だからしゃあない」というところは、ちゃんとわかってくれていたと思います。
――そういう親なら、子どもは追いつめられなくてすみます。やっぱり、ひとりっ子に注がれる両親の愛情を一身に受けてこられた。
確かにひとりっ子のメリットみたいなものは全力で味わってますね。投資がひとりに集中していた(笑)。
――大学は横浜のフェリス女学院大学です。そこも自分で選んだのですか。
今考えたら受験料がもったいなかったのですが、あのときは、受けられる限りの東京の私立をとにかく全部受けて、ほとんど落ちてしまった。結局、フェリスだけ受かったんですよね。言ってみれば、ほかの大学は、受かるはずもないのに受けた「格好つけ受験」みたいな感じでした。親には本当に申し訳ないことをしました。だから投資した分に関しては、10分の1ぐらいのリターンしかできてないんじゃないかなと思います。
――投資することが喜びだったかもしれません。ご両親にとっては。
お金をかけられて育ったけど仕上がりこんな、っていう悪い見本です。

モテモテの父
淋しさを見せない母
――いわゆる母と娘の葛藤はなかったのでしょうか。
普通に反抗期はありました。母親の言っていることが気にくわないとかそういうのはいっぱいあったので。何が原因かはもう覚えていませんが、多分、生活態度なんかを母から注意されたんでしょうね。「早く寝ろ」とか「風呂が長い」とか「掃除をしなさい」とか「髪の毛が落ちてる」とか。
高校生の頃、素直に「お母さん」と呼べなくなって、「おばさん、おばさん」って呼んでいた時期があります。母は、「あまりに腹が立ったんで夜中に歩いて墓まで行った」と言ってました。高校生の私に「出て行け」とは言えないから、家から30分くらいかかる護国寺まで行ってお参りしたみたいです。
――普通の母と娘ですね。では、お父さんに対しての反抗は。思春期の娘は、父親を敬遠しがちです。
父が家で一緒にごはんを食べるのは週に1回あるかないかでした。夜中には必ず帰ってくるんですけど、私が起きている時間にはほとんど家にいないので、ケンカになりようがない。ただ、私が大学受験をする頃は父が不眠症にかかっていた時期で、睡眠薬の副作用のせいかメチャクチャ短気になっていて。もともと何かあるとすぐに大きな声を出したり、母親ともよく怒鳴り合いのケンカをしてましたけど、それが私に向いてくることはなかったから、そのときは怖かったですね。
『生きるとか死ぬとか父親とか』には、常に女性の影がちらつく父の姿が綴られている。ジェーンさんは、そのことを、子どもの頃から当り前のように母から聞いていた。母はいつも「わが家にお父さんはいないの。うんと年の離れたお兄さんと、あなたと、お母さん」と娘に話していた。
――お母さんとお父さんのケンカは、浮気を巡ってですか。
そのことでケンカをしてるのは見たことないですね。ケンカの原因は、多分商売のことだったと思います。事業の立ち上げの頃から何年間かは、母も一緒に仕事をやっていたんです。小石川に家を建てた頃にはもうやめていましたが、父が危なっかしい人なんで、何か大きいことをしようとすると、それに対しては「絶対ダメ」と止めたりしていました。ただ母が外の女性に対して「あの女が気に入らないわ」と言うのを、小学生の頃から私は普通に聞いてましたよ。「気に入らないなぁ」とか2人で言ったりして(笑)。
――小さくとも、その意味はおわかりだったでしょ。お父さんに腹が立ちませんでした?
もちろん、わかってました。でも、そんなに腹は立たなかった。なんだろう、やっぱり、すべては母なんですよ。母親が「気に入らないわ」と言いながらも平気な顔をしていたら、子どもはそのことが平気になる。私が高校生くらいのときに、「お父さんが家にいなくても淋しい思いなんか全然しなかったよね」と父と母のいる前で話したら、母は「あら、それは私があなたの前で一切淋しい顔をしなかったからよ」と言ってました。「確かに」と思いましたね。
――父の浮気話を母と娘でするなんて、なかなかないと思います。
中学になると「あの女とお父さんがあそこにいて、こういうことがあって、あれだけはお母さん許せないわ」みたいな話を聞いて、「それは許せないね!」って相槌打ってましたから。父の外の女性のことで私がバランスを崩したのは、母が死んでからです。