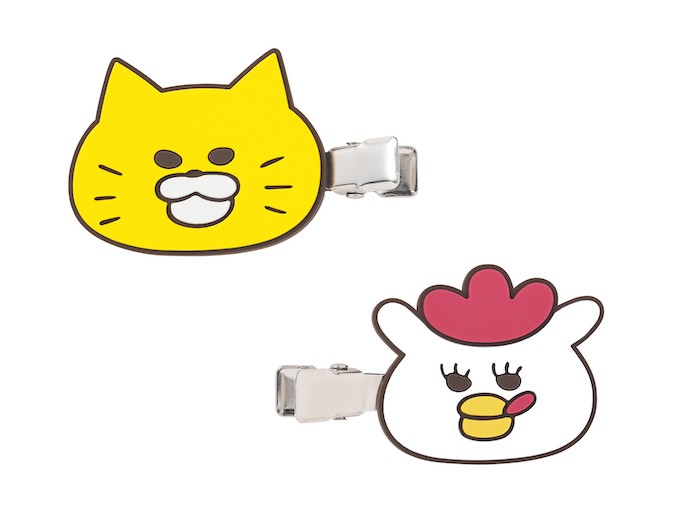絵本作家・植垣歩子「お年寄りを描きたくて、大好きだった絵本の道に」

絵本作家になると思っていた子ども時代
―― はじめて自分で絵本を描いたのはいつ頃でしたか?
母が福音館書店の「こどものとも」 が好きで、小さいころから家に絵本がたくさんありました。それで自然と絵本が好きになりました。絵が好きで、いつも絵を描いて遊んでましたねえ。ぶつぶつしゃべりながら、お話仕立てで絵を描くんです。『くまさんの魚つり』っていうのが最初に描いた4ページくらいのちっちゃな絵本のようなもので、くまさんが「赤い魚つれた」「青い魚つれた」ってひたすら釣りをするストーリー(笑)。幼稚園くらいでしょうか……親が褒めてくれるとうれしかったりして。喘息持ちだったので、外で遊べないときはずっと家で絵を描いていましたねえ。
―― どんな絵を描いていたのでしょう?
ねずみがみんなで生活してるとかキノコ採りに出かけるとか、牧場にいろいろな動物が暮らしている絵とか……うさぎさんの絵で、場面はレストランと厨房、なんていうのもありましたねえ。レストランでは紳士淑女のうさぎさんがごはんを食べてるけど、かたや厨房ではみんなが大忙しで働いて、とか設定を考えて、楽しかったですね。小学生になってもそうやって遊んでました。絵本みたいなものを、しゃべりながらお人形さんごったみたいな感覚で描くんですね。息子もよくしゃべりながらひとりで遊んでいるので、きっとそういう世界が子どもにはあるんでしょうねえ。
―― 本格的な絵本を描かれたのが、なんと小学生のときなんですね?
12歳のときに『いねむりおでこのこうえん』という絵本を描くことになったんです。父の知り合いに学校の先生で詩を書いている方がいて、その方が絵本の文章を書いたというので私が絵を頼まれて……。描いたものをコンペに出したら、子どもが描いたってことで珍しかったのかもしれないんですけど、賞をいただいて、小峰書店さんから出版されたんです。いまだったら描けないんじゃないかっていう、おおらかさがありますよね。自由なんですね……何も見ないで描いてる。忘れちゃいけない描く喜びを感じますねえ。この絵とくらべると、私も大人になっちまったなって反省したり。当時からちょこちょこ細かく描くのが好きだったですねえ。二度と描けない絵がこうして残っていて、ありがたいなと思いますね。


―― それはうれしい経験でしたね。そのときに絵本作家になろうと思いましたか?
その頃には、自然と絵本作家になるものだっていう子ども特有の思い込みがありましたね。ただ、大学生になって、他に違う表現があるんではないだろうかと日本画を専攻して、絵本から一度離れたんです。いろいろな絵や芸術ってものを本気で見たりしてましたねえ。それはすごくいい時間で、絵本だけじゃない、いろいろなものに広く触れたっていうことは、ほんとによかったと思いますね。
―― 絵本には、どんなきっかけで再会したのですか?
大学を卒業して22歳くらいから、介護の仕事につきました。仕事自体はすごく自分に合っていたんですけど、絵を描きながらやるっていうには、ちょっとハードな仕事でしたね。眠い目をこすりながらはできない仕事で……例えば、お風呂で介助しながら、私がつるっと滑ったら大変ですし、すごい緊張感がありました。それで絵を描く時間がなくなってしまって。私は何がやりたかったんだろうって、ちょっと立ち止まって考えてみたんです。そうしたら、やっぱり絵を描きたかったんだよねって思って。その頃から、ふだん接しているお年寄りを描きたくなったんですね。そのときに、表現として「絵本」があるんじゃないかなって思って。ここで絵本に戻りましたね。
―― この後お年寄りが主人公の作品を作っていかれますね。お年寄りの魅力って、どんなところにあるんでしょう。
認知症の方もいっぱいいらして、認知症であっても、いままで長い時間生きてきたもの、たとえばお人柄とかが垣間見える瞬間がある。人生を考えさせられることがいっぱいありました。元歯医者さんのおじいさんがいて、認知症だったんですけど、歯についてはすごく生き生きと話したりとか。そういうところからお年寄りに魅せられて。姿もすごくチャーミングでしたし……働いてるとそんなに呑気なことは言ってられないんですけれども、絵の題材としてもとても魅力的だったので、ひとつ描いてみようかって。
それで仕事をやめて、アルバイトをしながら絵本を描き始めました。最初に描いたのは『ろくにんのろうじんと男の子』っていう絵本で、ピンポイントギャラリーのコンペの賞を受賞したんです。この絵本は、思い入れが強すぎて、長い間なかなか形になりませんでした。今、ようやくお話がまとまって編集さんと作っているところなんです。ふたりとも子育て中なのでゆっくりペースですが。このコンペの審査員だった編集の方とのご縁で『ひげじいさん』というお話の挿絵を書くことになりました。