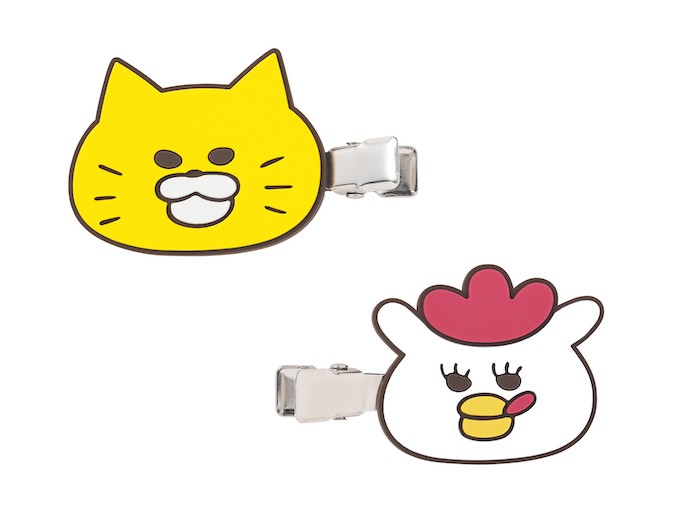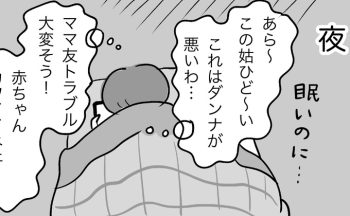『生きるとか死ぬとか父親とか』著者ジェーン・スーさんインタビューweb版
ラジオのパーソナリティやコラムニストなど、幅広く活躍するジェーン・スーさんは、東京生まれ、東京育ちのひとりっ子。今回は亡くなってもなお大きな存在のお母さんのこと、そして「父の本を書いたことで今が一番いい関係」というお父さんのことについて話してくれました。kodmoe2019年2月号のロングインタビューに載せきれなかった完全版でお届けします。
インタビュー/島﨑今日子 撮影/大森忠明 ヘアメイク/村中サチエ

じぇーん・すー/コラムニスト、ラジオパーソナリティ。『貴様いつまで女子でいるつもりだ問題』(幻冬舎)で第31回講談社エッセイ賞を受賞。また、毎週月~金の昼に、TBSラジオ「ジェーン・スー 生活は踊る」のパーソナリティを務める(2019年2月現在)。著書に『私たちがプロポーズされないのには、101の理由があってだな』(ポプラ社)など。
厳しくも娘に
全身全霊を捧げた母
――東京生まれの東京育ちです。ご両親に関する初めての記憶は?
本郷のマンションに住んでいたときです。私が小さな頃は、土日のどちらか、家族で外食するのが決まりだったんです。多分、そうしたときだったのか、父親の車でどこかに出かけて帰ってきた夜、私が先に寝るときに母が部屋の窓を開けるのを布団に入って待っていて、空気が変わったのを感じてから眠った記憶があります。母は、夏でも冬でも寝る前に「空気チェンジ」と言って、換気するために窓を開けるのが好きでした。
――それが、1日の終わりの儀式だったんですね。ひとりっ子でお育ちになりました。
両親は前回の東京オリンピックの年に結婚していて、私は結婚8年目か9年目に生まれた子どもだったんです。あとでわかったことですが、その前に何度か流産していたようです。母は父より6つ年上なんですが、初産で私を産んだときは41歳でした。当時としてはかなり遅かった。あの時代は高齢出産に詳しいお医者さんはそんなにいなかったらしく、本郷から小岩にある病院にわざわざ通ったと聞きました。
――とても大事にされていた?
うちの父は高度成長時代に仕事をしすぎて家庭をあまり顧みなかった、あの時代によくいたタイプの父親です。よく働きよく遊び、毎日帰るのは午前様で、休みの日は朝からゴルフで家にはいない。だから私に関しても、愛情はたっぷりあるのですが、その場その場で可愛がるような感じでした。
母にはしっかりと育てようという意識が強くあったのは、小さいながら私も感じていました。母は9人きょうだいで、父は3人きょうだい、両親にはひとりっ子の経験がなかったんです。当時は、ひとりっ子って、わがままと弱虫の代名詞だったので、そう思われたくないという気負いが母にはあったんでしょう。厳しく育てられました。幼い頃は、いつも「忍耐力がない」「継続力が弱い」「集中力がない」と言われていましたね。
1973年、東京文京区に生まれ、育った。最強のコラムニストにして、ラジオパーソナリティ、かつその他職業多数。「未婚のプロ」という別名まであるジェーン・スーさんの近著『生きるとか死ぬとか父親とか』(新潮社)は、父と娘の一筋縄ではいかない関係を綴ったエッセイだが、いつも父と娘の中心にいるのは、亡くなったジェーンさんの母である。元映画雑誌の編集者で美しく聡明な人だった。
――小さな頃は、どんな子どもだったんでしょう。
生まれたときは3000gちょっとなんですけど、そのあとの成長が著しくて、歩き始めてからは母の手に負えなくなったみたいです。雨の日になると「外に出せ、外に出せ」って、マンションの玄関のドアをガンガン蹴るんでもう堪ったもんじゃなかったそうです(笑)。
あまりにもエネルギーがあり余っているというので、母の友達がやっていた近所の幼稚園に2歳から入りました。プレ入園みたいな形で1年間そこの園に通った後、駒込の幼稚園に通うんですね。でも、いいとこのお嬢さんお坊ちゃんの行くようなところで、間違えて入れちゃったみたいなんです。お遊戯の時間が決まってたり、園庭がちっちゃかったりして、私はすごくイライラしていたらしく、同級生の男の子を突き飛ばして親が呼び出されたこともあったみたい。3年間行く予定だったのに、「ダメだ、これは合わないや」というので、次の年に近所の国立の幼稚園を受けて、ガラポンで入ったんです。
――幼稚園受験して抽選で選ばれた? 強運です。
記念受験のようなものですよ。文京区で、私の住んでいた地域だと近所には3つの国立校があるので、お受験に対するハードルはほかの地区よりは低いと思います。私はラッキーにもそのうちのひとつに入れたんですよね。
新しい幼稚園は本当に自由でした。子どもたちがラグビーしながら泥だらけになっていたり、今だったら絶対無理だと思うんですけど、工作では幼稚園児にのこぎりや釘を平気で持たせてくれたので、板で車を作って、みんなでその上に乗って走ったり。相当やりたい放題だったので、すごく楽しかった。あり余っていたエネルギーが全部そこで解消できる感じでした。
――お母さんは娘に合った幼稚園を懸命に探したんですね。
厳しい人ではありましたけれど、本当に全身全霊を私に捧げてくれた母親だったと思います。亡くなってから、幼なじみの友達のお母さんが「体操の選手かと思った」と言っていましたが、私と一緒に滑り台に登って滑って遊んでくれていたとか。ひとりっ子で寂しいだろうからと、小学校の2年生ぐらいからは年に1、2回、学校の友達を集って、観光バスを貸し切り、スキーやサイクリングに連れて行ってくれた。きっとイベントとか企画が好きな人だったんでしょうね。私のためを考えて、いろいろやってくれました。
これも、幼なじみのお母さんに久しぶりに会ったときに言われたことなんですが、「あなたが子どもの頃、お母さんは小さい子に怒るというレベルじゃない怒り方をしていたことがあった。大人に注意するみたいな感じで理詰めで怒って、たまにあなたがわけわかんなくなってぽわ~っとすることがあったから、大丈夫かなと思ってたの。でも、大丈夫だったわね」って。完璧だと思っていた母にも、そんな風に我を忘れる大人げない瞬間があったということです。そうやって育ててくれたのかって、嬉しかった。私にとっては宝物のエピソードです。
――お母さんのお弁当もさぞや美味しかったのでは。
小学校は給食でしたが、お弁当の日もあったかな。母は料理がすごく上手な人で、全部手づくりで作ってくれました。母は味重視なんで、今でいうキャラ弁的なものは全然なかったけれど、焼きおにぎりなんか、私の友達がみんな「美味しい、美味しい」と食べるもんだから、いつも10個ぐらい持って行ってました。あとから友達に、うちに来たとき人生で初めて食べるものが結構あったと言われましたね。芽キャベツとか、ブラックオリーブとか。子どもと大人の食事を分けるってことはほとんどしない人で、全部大人の食べるものを食べさせていたんだと思います。

教育者の母
何も考えていない父
――聞けば聞くほど、素敵なお母さんです。衣食住の衣は?
その頃は制服ですから、「汚して帰ってこないでくれ」という感じだったと思います。親って大変ですね(笑)。一度、みんなが履いている戦隊もののイラストがついたピンク色のズックが欲しくて、「あれが欲しい」って言ったら、「あなたにピンク似合わないから」と言われてガーンとなったことがあります。今、写真を見ると、母はすごくお洒落な服を着せてくれてるんですよね。紺とかグレーとかベージュとかそういう系統の服。母のセンスのよさが遺伝したら嬉しかったのに、しなかったです。
――本は? お母さんはたくさん本を与えてくれたのでは。
母は『シートン動物記』とか、『世界名作全集』などを買い与えてくれたんですけど、私が読書が苦手で、ほとんど読んでいません。それが「集中力がない」というところにつながるんだと思うんですけど。私があまりにも本を読まないのを心配した母が、元国語の先生をしていた家庭教師を探してきたことがあったんですね。その先生の薦めで『秘密の花園』は読みました。その当時は、読書の何が面白いのかピンとこなかったんです。娯楽としても勉強としても、なんでこんなものがあるんだろうという感じでした。
――今こんなに本を書いてらっしゃるのに、不思議です。
読んでなくとも書くことはできるんだと思いますが、表現や語彙の基礎体力みたいなものはやはり乏しいですね(笑)。
――ジェーンさんの「考える力」はどこで培ったのですか。ラジオも面白いし、小さな頃からおうちの中でもこんなふうに喋っていた?
私、おとなしくはないし、よく喋ってましたけど、うちは父と母がもっと喋るんですよ。両親は常に丁々発止。私はそのラリーを見てた感じです。それに、私は怒られたときにじめじめして、それを根に持ってじめじめをわざわざ親に見せに行っていたらしいんですね(笑)。傷つけられたという被害者の顔を見せに行くので、父はよく「お前は暗い」と言ってました。母にも「怒られたり失敗したりした後の落ち込みの暗さが嫌だ」と言われたのを覚えています。
――ご両親が話好きだったのは、ジェーンさんの成長に影響してると思います。
そうですね。ただ、私に対して話すとき、母は娘に対する教育者という意識があるので、あくまで「母」という仮面をかぶった上で、近代史として自分の子どもの頃の話をしたり、学生の頃の話をすることが多かったんです。一方で、父には「こういうことを話すことでこの子の知識になる、役に立つ」という意識はまったくなかった(笑)。その日の出来事をぺらぺら喋ったり、昔のことを適当にぺらぺら喋ったりするだけ。だから、私は本を書くまで、父のことをなんにも知りませんでした。
――いや、子どもは親のことをそんなに知りませんよ。ところで、その頃一番快感だったのは。
音楽はずっと好きでした。テレビの歌謡曲番組が全盛の頃で、東京FMでやっていた「コーセー歌謡ベスト10」も、よく聴いていました。流行の歌を歌ったり踊ったりするのが好きな子どもでしたね。
――習い事は。
ピアノを習わせてもらったり習字を習わせてもらったりはしましたけど、何もどれも身に付かず。ピアノは小学校に入ってから高校1年生ぐらいまでやってたんですけど、全然弾けなかった。どの曲が弾けてからやめたのかさえ覚えていません。だから、フツーにものにならない子どもだったんですよね。習字も、私が教室で「あまりにもふざけすぎる」と、先生の奥様からクレームの電話かかってきたくらいですから(笑)。近所に大きい水泳教室があったので水泳も習っていました。泳ぐのは好きだったけれど、だからといって選手になるわけでもないってレベルで。
――学校では、どんなにキャラクターだったんですか。
よく母に叱られていたように、学校でも「落ち着きがない」と言われてました。いまだにそうなんですけど、大してできないことなのにわかったフリしたりできたフリをしたりして、人に教えたがったり。まっとうとされる道から逸脱するのが嫌で、小さな嘘をついてしまう癖がありました。大人にはバレてるのにね。それに、なんだかんだと自分でやるんじゃなくて、人にやらせるのが好きだった。振り付けを考えてみんなに踊ってもらったりとか。まったく、本当に馬鹿丸出しの子。すぐ調子に乗るし。
――自虐的すぎます(笑)。それにしても、文化的には豊かに育ってますよね。
そこは、本当に母に感謝してます。父は母に比べると文化度の低い人なので、私の文化的吸収は、母がいなくなった24歳で止まってしまっているなと思うこともあります。







KV修正-350x350.jpg)