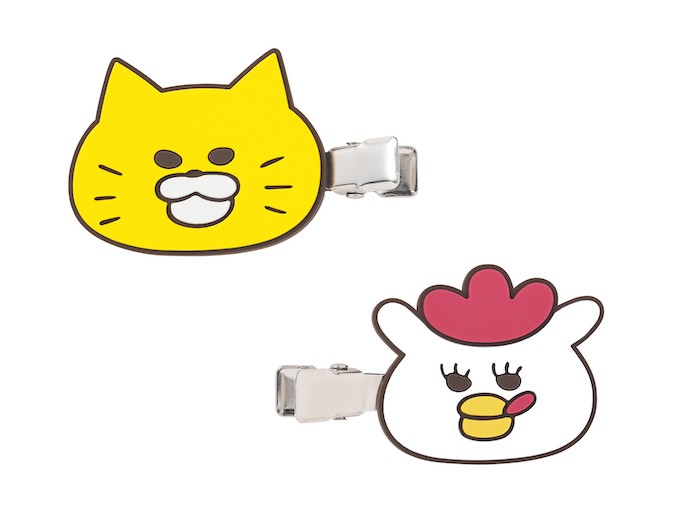内田也哉子さんロングインタビュー。夫は常に俯瞰して物を捉えるまっとうな価値観の人【後編】
俳優の樹木希林さんと、ミュージシャンの内田裕也さんの一人娘である、内田也哉子さん。母親は仕事に忙しく、父親は不在。幼少時代は孤独を感じていたそうです。kodomoe2月号でうかがった貴重なインタビューをkodomoe webで全編公開。後編では、自身の幼少期、19歳で結婚し21歳で母になったこと、そしてご家族についてなどをおうかがいします。
ロングインタビュー 前編はこちら
うちだややこ/1976年東京都生まれ。 エッセイ執筆を中心に、翻訳、作詞、音楽ユニットsighboat、ナレーションなど、言葉と音の世界に携わる。三児の母。季刊誌「週刊文春WOMAN」にてエッセイ「BLANK PAGE」、月刊誌「家庭画報」にて季節連載「衣だより」を連載中。Eテレ「no art, no life」(毎週日 8:55〜)では語りを担当。

親の支配なし
責任はすべて自分に
日本のロックを牽引した父もだが、共に暮らす母はとにかく規格外れの人だった。娘は小学校6年のとき、自ら希望して転校した日本の学校で、自分の異質ぶりを実感することになる。
――転校先ではいじめられた。
インターナショナルスクールはいろんな国の子がいるから、そんなに異質感はなかった。だけど日本の学校、今よりもはるかに男の子の格好は、女の子の格好がはっきりしていた。ランドセルも赤か黒かで、私は誰かからもらった黒いランドセルで通ったので、「なんで黒なんだよ」と石を投げられました。身なりもだけど、女の子らしさもなかっただろうし。それに何を習ってるのかしばらくわからなかったですから。読み書きが全然できてなくて、何から何までカルチャーショックでした。
――さすがに希林さんも「やめてもいいよ」と、おっしゃったとか。
「そんなに辛いんだったらやめたら?」ぐらいの言い方。決定権は私にあるんですよ。「日本の学校行ってみたい」と言ったのも私だし、あと半年で卒業だったので、ここをやめても責任を取るのは自分だから、我慢しようと思って行きましたね。
――母の支配はない代わりに責任は自分で取らなければならない。
門限もないし、小さいときからすべて責任は私に与えられてたから、本当に自由でした。でも、自由という言葉から連想されるのは、窮屈でしかなかった。他の子どもたちがお母さんから「何時に帰ってきなさい」、「こういうとこは行っちゃだめです」と制約を受けるのが、羨ましくて仕方なかった。それが愛に見えたんですよね。私には誰も言ってくれる人がいなくて、自分で決めるしかなかった。
私が育った80年代終わりから90年代は、親たちが競争するように分刻みで習いごとを入れる時代でした。中学に上がってみんなが受験勉強を始めたとき、ひどく焦ってしまって、「私も行った方がいいかな」と母に聞いたら、「学校行ってんだから行く必要ない」(笑)。高校選びも「こういう私立もあるらしいよ」と自分なりに調べてプレゼンするんだけど、「税金払ってるんだから近所の公立に行きなさい」。頼み込んで受験前の一か月だけ塾に行かせてもらって、近くの都立高校に入りました。
――しかし、すぐにスイスに留学することになります。
当時、チーマーやパーティーが流行ってましたが、いわゆるティーンエイジャーが楽しむような、ちょっと危険なことに私自身はあまりときめかなかった。私には元々規制がなかったから、それを壊したいというより、もっと自分の中に眠る何かを解き放ちたい。でも学校や友達を含め、この環境では見つけづらいと思ってしまったんです。そんな壁にぶち当ったとき、フランス映画が好きだったので、自分でいくつか大使館を巡ってフランス語を学べる海外の学校の資料を集めて、ここに行きたいと母にプレゼンしたんです。とても高い学費だから絶対無理だと思ったけど、「わかった。振込先だけ教えといて」とあっさり(笑)。学校を見に行くこともなかった。
也哉子さんのはじめての海外留学は、9歳のとき。海の向こうで暮らすことは、父と母からの、周囲の視線からの逃走でもあった。
――最初のホームステイ先は、ニューヨークでしたっけ。
インターナショナルスクールのアメリカ人の校長先生の勧めで、東洋人が一人もいないニューヨークの地方都市に1年間行きました。行きは母に送ってもらったんですが、家の子どもたちと1時間ぐらい遊びに出かけて帰ってきたら、母はもういなかった。自分の意志で行くとは言ったんだけれども、この置いていかれ方はもしかして捨てられたのかもしれないと(笑)。母らしいですけど、自分が子どもを持ってみて、こんな酷いことはできないと思いました。
――さよならを言うのが、辛かったんでしょう。
のちに母の友人に「あの時は、すごく心配してたよ」という話は聞いた。ただ電話は1本もなかったし手紙も1回もなくて、コミュニケーション手段が全部断たれました。1度、私が大熱を出したときに、向こうの家族が心配して「お母さんの声聞きたいでしょ」と国際電話をかけてくれたんですよ。私が完全に日本語を忘れていて、「ああ、ああ、ああ……」と言ってるうちに、「なに? どうしたの? もう切るわよ、国際電話高いんだから」とガチャッて切られた(笑)。そのあとも毎年、夏休みの2か月半ぐらいは、必ずどこかの国にホームステイさせられていました。みんな普通の家だったので、お誕生日やクリスマスに、いっぱいプレゼントもらって。はじめての経験をいっぱいしました。
結果的に、あのまま私が東京で両親の影響下で育ってるだけだったら、私ならではの人生はなかったと思うんです。「両親があんなめちゃくちゃでよくグレなかったね」と、言われます。だけど、グレるって、その子が息苦しいから自分でもがいて、転んだりすりむいたりしながら大人になっていくことだと思うんですね。私は外国の暮らしや、学校でのコミュニティなど、環境の変化が当たり前だったし、いろんな場があったからこそ、それなりに葛藤がありつつも反抗する必要はなかった。それは親が意図してなかったとしても、とてもありがたかった。
――幼い頃は、両親が芸能人だとは言えなかったんですものね。
ずっと「サラリーマンと主婦」と嘘をついてました。「私はあの2人とは別に生きてます」と、思ってましたから。それもあって、16歳のときに、完全にスイスに行ってしまいたいと思ったのかもしれない。潜在意識の中では、もっとまっさらな場所に行って自分を探してみたかったんでしょうね。
19歳で結婚
21歳で母になる
父と映画で共演した10歳年上のスター、本木雅弘さんと出会ったのは15歳だった。95年、19歳で結婚。97年に長男を、99年に長女を、2010年に次男を出産。2012年からはイギリスで暮らし、子育てをしながらエッセイを書き、絵本などの翻訳を手がけてきた。

――結婚後は、お母さんと二世帯住宅で暮らした時期もあります。
当初は別のところで夫婦で暮らしてたんですが、子どもができたときに、母が二世帯住宅はどうかと言ってきたんです。最初は私も夫もキョトンとしたんですが、完全に所帯を分けるというか、階段でも繋げず、別個の家が二つ上下にのっかっている感じだったので、いいかなって。ごはんも基本は別々でした。
―――21歳のお母さんですから、大変だったのでは。
私が一生懸命子育てをしている姿を見て、母は「私は母性が足りなかったわ。こうやって育てるのね」と言うだけで、何も教えてくれない。夫のご両親も遠かったし、夫も忙しかったから、最初は孤独な子育てで、ちょっとこじらせました。長男は乳製品アレルギーで、赤ちゃんの頃に全身じんましんになって救急病院に走るという経験をしてからは常に怖くて怖くて。
でも、夫は父親というよりは、世話好きなお母さん気質なんですよね。だからいつからか、お母さんが2人いると子どもたちが息苦しいからと役割をバトンタッチしたというか。お母さんは夫で、お父さんは私(笑)。12歳の長男がスイスに留学するときは母がついていってくれたんですけど、長女の留学のときは夫が寮に行ってクローゼットのサイズ測って、仕切りを入れてとかいうのを全部やったり。そういうのが得意でしたね
――それはいいですね。お子さんは3人とも留学していますが、ご自身の体験を踏まえてですか。
私は過剰なんです。自分がしてもらえなかったことを、自分の淋しさを埋めるためにやってしまっているという俯瞰の目もある。自己嫌悪しながらも言い過ぎちゃったり、やり過ぎちゃったりします。長男が小学校高学年の頃に、母が通りすがりに「そろそろ親の手を離した方がいいよ」とアドバイスをしてくれたんです。
――イギリス暮らしの目的は。
娘がイギリスの学校に入るとき、学校が始まる夏に家族で向こうへ行って、1か月ぐらいホテルアパートメントに泊まってたんです。そのうち「まだ仕事は延ばせる」と。それが2か月、3か月になって、ある時、長期貸しのアパートを見つけた。夫が日本で仕事をして戻ってきてというのをやってるうちに、長男がいるスイスからも近いし、なんだか住むことになって5年いました。次男は2歳から7歳までいて向こうの生活が基盤だったので、日本の文化や言葉を学ばせたくて今は日本で暮らしています。
――お子さんの洋服とかどうしてますか。買う? 買わない?
買いますね。でもね、私は食品の買い物はしますけど、いまだに物を買うことへの罪悪感が拭えません。夫は買い物好き、特に洋服が好きですから、最初っから子どもたちの洋服とか必要な物は夫の役割でした。
――希林さんは、娘家族が楽しく買い物をしている姿に対しては、どんな反応でしたか。
「いやぁ過剰だわ」と呟いてました(笑)。「やめなさい」という言葉は絶対言わないし、忠告もないんだけど、「私にはできないわ」と言って去って行く感じ。だから今でも葛藤してますよ(笑)。母はいないけれども、その母の目が私の中にあるものだから、ブレーキを踏みすぎて夫と揉めたりします。夫にしてみれば、自分で稼いで、欲しい物を手に入れることを咎められるのは辛いだろうし、私としても夫と母の中間くらいの感覚でいられたらと思うのですが。
――希林さんと本木さんは、揉めませんでした?
揉めました! 同じ役者っていうこともあるし、互いにすっごく気を遣っていたんです。でも、母には本木さんが養子に来てくれたことに対する感謝があったけれど、気を遣い過ぎて言いたいことも言わない母ではないので、思ったことはズバズバ本木さんに言い、本木さんもそれをサンドバックのように受け止めながら、抱えきれなくなったら、「でも、希林さん!」って爆発する(笑)。だから、なかなか印象に残る大きなケンカをしてましたね。
私は最初、両方ともに味方したいからウロウロしていたら、「今は黙ってて」と言われて、しゅん。夫は自分の感情だけを押し付ける人ではなく、常に俯瞰して物を捉えるまっとうな価値観を持っているので、家族で議論したときも最初に彼が提案したことが結果ベストなんです。最後に母が「やっぱり本木さんの考えはまともだわ。本木さんの言うことを素直に聞いてれば間違いないわ」と笑って、言い争いが終わることが多かったですね。
母からのギフト
授けられた生き方
――也哉子さんは、初恋の人と結婚したわけですが、それまで男のロールモデルだった裕也さんとは対極にあるような方です。
とんでもないロールモデルしか知りませんでした(笑)。でも、今いろんな人から話を聞いたり、数少ない父との記憶を集めると、実はすごく柔らかい人なんですよね。本木さんも、柔らかい感性の持ち主で、「俺についてこい」という人なら私はダメだったかもしれない。むしろ内面の女性性の強いところは、2人に共通しているんです。多分、表現者という共通点があるからかもしれないですね。
――ご家族三代の素敵な写真が公表されてます。
滅多に会わないから、会ったときは母が全員を写真館に連れて行くんですよ、会ったことの証拠を残すって(笑)。父も真ん中にドーンッと、ずうっと父親でしたみたいな感じで座っている。孫もみんながいるとき、父がボソッと、「俺たち別れなくてよかったよなあ」と、言ったんです。自分のブラックホールを埋めるためであったとしても、母が軸となっていてくれたことで家族が増えて、夢にも思わなかった団らんのひとときを持てた。そのときの言葉は、私にとってはとても救いでした。
――希林さんが余命宣告されて、イギリスから帰国。最期の時間を一緒に過ごされたんですね。
乳ガンを発病したときも、再発したときも母は一人ですべてを決めて、手術して、治療して、本当に長く病気とつきあってきたんです。私たちは、自分たちがイギリスにいたから見落としたんじゃないかとか罪悪感もあったけれども、母はいたって淡々と、「それにしても長生きしたわよ。お釣りがくる人生よ」という感じでした。
父は母が亡くなったとき、あんなにしょんぼりするのかというぐらいしょんぼりしていた。母の亡骸と対面したとき、母の本名を呼んで「なあ、啓子、キレイだよなあ」と、私たちに言うんです。母がよく言ってた「お父さんにはほんの0.001パーセント純なものがある」という言葉を思い出した。父のあんな姿を見ることができたのは、私にとってはギフトでした。
――不登校の子どもたちに何ができるかを考える『9月1日母からのバトン』を出版されたのも、希林さんからのギフトに思えます。
亡くなる2週間ほど前の9月1日に、母が病室で「死なないで」と言って、涙ぐんでいたんです。夏休み明けに、学校に行けず心が病んでしまう日本の子どもたちが自殺してしまうことを、憂いたんですね。その少し前から「40歳を過ぎたら子育てはほどほどにして、この世に生まれてきたんだから1人でも2人でも誰かの杖になりなさい」と言われていました。母は、虚無感を抱えながらこの世の中をなんとか生き延びてきたんですよね。追い詰められた子どもたちが「死ぬしかない」となった際に、「あと1ミリ絶対に何か面白いものや生きていて良いことがあるはず」という母の経験を伝えたくて、本を出しました。
みんな状況が違うから同じようにはならないけれども、両親が遺していってくれた生きる術みたいなものをわずかでもシェアできればと思っています。世界の貧富の差をどうやって解決していくかをわかりやすく示した、イタリアの『ドッツ』という絵本を翻訳したばかりです。こうした仕事が集まってくるのも、きっと母が遺してくれたギフトでしょうね。
――有名人の両親と夫に囲まれて、埋没することがない。也哉子さんが、ご両親から受け継いだものはとても大きいです。
何かにぶち当たったときに人生を投げ出さない術を、言葉ではなく体感として授けてもらったと思っています。
INFORMATION

『点 きみとぼくはここにいる』
ジャンカルロ・マクリ カロリーナ・ザノッティ/作
内田也哉子/訳 講談社 1980円
点というグラフィカルなモチーフを用いて、移民問題を子どもが直感的に理解し考えることを促す絵本。貧困、差別、人種などの問題を「自分ごと」として考えられる一冊。

『9月1日 母からのバトン』
樹木希林・内田也哉子/著 ポプラ社 1650円
2018年9月1日、樹木希林さんがつぶやいた「死なないで、死なないで……。今日は、大勢の子どもが自殺してしまう日なの」という言葉。それを受けて内田さんが考え、まとめた一冊。
インタビュー/島﨑今日子 撮影/馬場わかな ヘアメイク/木内真奈美(kodomoe2023年2月号掲載)