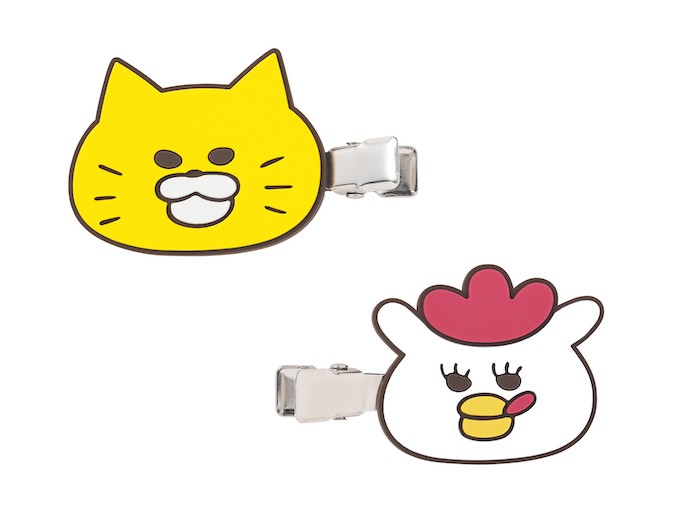作家くどうれいんさんロングインタビュー。「見て見て!」が今もずっと続いているだけ【前編】
小説にエッセイ、短歌、俳句、絵本、童話と、幅広いジャンルで執筆活動を行う新進気鋭の作家、くどうれいんさん。ウェブでは、kodomoe4月号の貴重なロングインタビューを全編公開!
前編では、文芸への道を歩み出すきっかけとなった、子ども時代の原体験や、文芸部の活動に打ち込んだ高校時代についてをおうかがいします。
1994年岩手県生まれ。小説『氷柱の声』(講談社)が第165回芥川賞候補作に。著書にエッセイ集『虎のたましい人魚の涙』(講談社)、第一歌集『水中で口笛』(工藤玲音名義/左右社)、絵本『あんまりすてきだったから』(みやざきひろかず/絵 ほるぷ出版)、創作童話『プンスカジャム』(くりはらたかし/絵 福音館書店)など。「群像」(講談社)にてエッセイ「日日是目分量」連載中。
好きだと思った人には
お手紙を出しましょう

大学生の頃に発表した食をめぐるエッセイ集『わたしを空腹にしないほうがいい』(BOOKNERD)は、リトルプレスとしては異例の大ヒット。自身初となる中編小説『氷柱の声』(講談社)が芥川賞候補作となるなど、文芸界で注目を集める作家、くどうれいんさん。生まれ育った岩手県盛岡市に今も暮らし、精力的に執筆活動を展開しています。
このインタビューの撮影中、「ほらほら、見てください、これ!」と披露してくれたのは、手影絵。「南部鉄器です、岩手の名産!」と、くどうさんは笑います。親しみやすくて、チャーミング。くどうさんは、どのような子ども時代を過ごしてきたのでしょう。
――「れいん」というお名前はご本名ですね。漢字で「玲音」。ご両親が付けたのですか?
父がこの名前にしようってひらめいたそうです。最初は「寧々」にするつもりだったとか。この前、絵本の韓国語版が出たときに名前を韓国語で「雨」を意味する「비」にすることになって、この名前は世界に通用するんだ! と気が付きました。もしいろんな国で翻訳されることがあれば各国の「雨」を作家名にするつもりです。
――そんな素敵なお名前を考えたお父さま。どんな方ですか?
父はこだわりが強いというか、ちょっと変わり者かもしれません。生け花とか料理とか山登りとか釣りとか。趣味がたくさんあるけど全部ひとりでやっていて、友達は少なそうです。わたしのサインは本ごとに違う印を押しているのですが、それもすべて父が彫ってくれています。
――お母さまはどんな方ですか?
変わり者なのは、母も同じかも。似たもの夫婦なんです。両親とも東北の田舎生まれで、カルチャーにあこがれながら大きくなった二人が育てた結果が、私っていう感じです。母もあまり友達は多くなさそうですね。両親が行きたいだけだったと思いますが、幼いころはよく陶器市や美術館に行きました。
――くどうさんは、どんなお子さんだったのでしょう。子ども時代に印象に残っていることは?
父が転勤族だったこともあって、小さい頃は引っ越しが多かったんです。幼稚園のときは岩手県の大船渡市という港町に住んでいて、こぢんまりとした園に通っていました。楽しく過ごしていたんですが、年長さんになるときだったかな、盛岡市に引っ越して、マンモス幼稚園に移ったんです。
それまでの園と違って規模は大きいし、ほかのみんなは友達関係がすっかり完成していたところにひとりでぽーんと入ってしまったものだから、気後れしちゃって、コミュニケーションがうまくとれなくて。当時のアルバムを見ると、大船渡に住んでいたときは明るかった表情が盛岡に来てから一気に渋くなっちゃって、「なんかあったね?」っていうのがすぐにわかるくらい、新しい環境についていけなかったんです。
それで、ほかのみんなは鬼ごっことかかくれんぼとかで盛り上がっているときに、私は園長室に行って、園長先生とふたりで切り絵をしたり、工作をしたりしていました。今思い返してみると、周りになじめない子のための場や時間を作ってくれていたんだなと思うんですけれど。
この時間には、園長先生に絵本もたくさん読んでもらっていました。その頃はストーリーを楽しんでいたというよりも、絵が素敵だな、きれいだなって思いながら見ていたかな。ストーリーの本筋と関係ないところで何か面白いことが起きている場面の絵とか、『からすのパンやさん』(かこさとし/作・絵 偕成社)みたいに、見開きに見るものがたくさんあるような絵本が好きでした。
――本好きなのは、当時から?
どうなんでしょう? でも、当時は母が書店で働いていて、児童書売り場を担当していたそうなんです。それもあってか、母はよく読み聞かせしてくれました。
毎週のように地元の図書館に通っていた時期もありました。図書館カードを持って行けばひとり5冊まで借りられたんですが、両親、私と弟も各々のカードを持っていたから、みんなの分を合わせれば一度に20冊まで借りられるんです。大量の絵本を図書館から運んでいたという記憶はありますね。
あ、そうだ。私、母にいまだに言われることがあるんです。「読み聞かせするとき、私は必ず作者の人の名前とか、出版社の名前まで読んでいたのよ。今のあなたはそのおかげね」って。
――例えば、「かこさとし/作・絵」「偕成社」まで読んでくれていたということ?
そうです、そうです。表紙にある題名や作者の名前、出版社の名前なんかを読んで、それからお話を。「おしまい」のあとには奥付も読んでいたって、母は言うんですけれど……。
――くどうさんは覚えていない。
正直、こまかいことは覚えていないんです。ただ、わりと「作・絵」は覚えているかな。「どこかに作っている人がいるんだなあ」ってなんとなく感じながら絵本を眺めていたような気がします。
――2022年には、くどうさん初の絵本『あんまりすてきだったから』(ほるぷ出版)を発表しました。この絵本の絵を手掛けたみやざきひろかずさんに、子どもの頃、お手紙を出したそうですね。
「好きだと思った人にはお手紙を出しましょう」っていうのが母の口ぐせだったんです。好きなテレビ番組や好きなお菓子を作っているメーカーに「おもしろいです」「おいしいです」って、しょっちゅう手紙を書いていました。
その頃に読み聞かせしてもらっていた絵本に、みやざきさんの「ワニくん」シリーズ(BL出版)があったんです。私、ワニくんのことが大好きになって、みやざきさんにお手紙を出したら、ご本人がお返事をくださったんです。
みやざきさんと私のつながりはそのお手紙だけだったのですが、自分が作家になって、読者の方から感想をいただく側になってからそのときのことを思い出して。それで、思い切ってみやざきさんに当時のやりとりのことや「いつかご一緒できたら」というメールをお送りしたら、「ぜひ!」とおっしゃっていただけたんです。『あんまりすてきだったから』は、そうしたご縁からできた絵本でした。
「見て見て!」が
今もずっと続いているだけ

――文章を書くことに興味を持ち始めたのは、いつ頃から?
興味を持ったというか、あれが原点だったなと思うのは、小学校1年生とか、2年生のときです。地元で読書感想文や詩のコンクールがあって、それに出すために先生が声をかけた何人かで放課後に居残りして、書いたものを添削してもらうことがあったんです。そこではじめて自由詩を書きました。
――どのような詩を書いたのでしょう。
いくつか書いたのですが、いちばん最初は、確か学校の机のこと。机の天板の下のところが、教科書やノートを入れる物入れになっていますよね、それをモチーフにして「机が教科書をたくさん食べてお腹いっぱい。みんなが家に帰るとお腹が空いちゃう」みたいな内容だったと思います。
そうしてコンクールに出したら、自分が書いたものが入賞したんです。両親も祖父母もすごく喜んで、たくさんほめてくれて。私は運動ができないし、絵を描くことも、楽器を演奏することも得意じゃない。だからと言って、勉強がめちゃくちゃできるわけでもない。それまで自分が何かに秀でていると思ったことがなかったんですけれど、「あ、もしかしたら、自分はこれなのかも」って、そのときにはじめて思えたんです。
――それから書き続けてきたわけですね。
そうですね。やっぱり、低学年で賞を取ったときに家族が喜んでくれて、「自分はこれだ!」って思えたことはすごく大きかったです。両親には礼儀は厳しく教えられましたが、それ以外はわりと放任主義でのびのびとやらせてくれたし、私がやっていることを揶揄するようなことも一度もありませんでした。
「今度はこんなのを書いたんだよ。見て見て!」って見せにいくと、なんとなくあしらうなんてことはせずに、いつでも「すごいね、見せて見せて!」って言ってくれて。「見て見て!」の相手が、家族から今は担当編集さんになったという感じです。
――子どものときから変わっていないのですね。
周りで詩歌をやってきた人に聞くと「隠れるように書いてきた」「書いていることを誰にもバレないようにペンネームで投稿していた」っていう話を聞くんですけれど、私はそうした経験がないんです。「書いたよ」「賞とったよ」と言ったら、家族もクラスメイトも「すごいね」って言ってくれる環境で。「ダサいよ、それ」「文芸って、なんかオタクっぽいよ」なんてからかわれずに来れたから、照れるヒマもなかったんです。
「自己肯定感を持つ」っていうほどちゃんとした感じじゃなくても、なんていうか、自分にうっとりすることを許してもらうって、大切なのかもしれません。そのおかげで自分は書き続けられてきたのかなと思いますし。
――周りを気にするあまり、やりたいことの芽を自分でつぶしてしまうこともあります。
そうですね。「こんなことをしたら周りから浮いちゃうんじゃないか」「ちょっとナルシストすぎやしないか」って、自分で自分を殺してしまうというか。私はずば抜けた感性だとか、特別な何かを持っているわけではなくて、単に「うっとり」のリミッターがなかっただけなのかもしれません。
文芸部の活動に
打ち込んだ高校時代
――学校の先生に見てもらう以外に、文章の書き方を教えてもらったことは?
ほんの一時期ですが、中学生の頃に地元の文章教室に通いました。3回くらい行って「なるほど、こういう感じね。わかった!」って、すぐに辞めちゃったんですけれど。ただ、そのときに「気に入った作品は読むだけじゃなく、そっくりそのまま書き写してみるといい」と教えてもらって、山崎ナオコーラさんのエッセイを書き写したことがありました。「ここで読点を入れるんだ」「この一文、長い! 次は短い!」みたいに、自分の手を通して息づかいやテンポが感じられて、それは楽しかったですね。
俳句の会にも入っていました。身内でもなく、学校の先生でもない年配の方たちと季語についておしゃべりしたり、「このお花の色は白だけじゃなく、赤もあるのよ」って教えてもらったり。俳句って、年が離れていても対等に話ができるんです。ですから13歳のときに、70代とか、80代の友達がいました。
――高校は岩手県立盛岡第三高校。文芸部の強豪校です。文芸部を目指して、この高校へ?
正直、どこでもよかったんです。でも、盛岡三高の文芸部がコンクールに入賞するたびに母がそのニュースの新聞記事を見せてきて「ほらほら、今度は文部科学大臣賞を取ったみたいよ?」って。なので、母の思惑通りというか。
入学していざ文芸部の扉を開けてみたら、アニメや漫画の二次創作をやっている人も多くて「私のやりたいことと少し違うかも……」って思ってしまって。そんなときに剣道場の前を通りかかったら、剣道がとてもかっこよく見えて、そのまま剣道部に入部したんです。
――剣道の経験は?
皆無だったし、運動も苦手。剣道部は上下関係が厳しくて、入部して3か月で「もうダメだ」と。剣道部の顧問の先生がゴリゴリの体育会系で「根性がないから辞めたくなるんだ。続けないと意味がないんだぞ!?」みたいな、めちゃくちゃなことを言うタイプだったんです。そこに助け舟を出してくれたのが、偶然にも文芸部の顧問の先生でした。
――その先生は、くどうさんに文芸部に入ってほしかったのでは。
いえいえ、私を見初めてという感じではなくて、単に癖の強い剣道部の顧問から逃がしてやりたいという気持ちが強かったんだと思いますよ。「『剣道以外に成し遂げたいことがあるんです』って言えば大丈夫。情には弱いはずだから」というアドバイスをくれて。それで「私は文芸部に入りたすぎて、剣道部を辞めるしかないのです。文芸のコンクールで一番を取ることを誓います!」と部員みんなの前で宣言させられて、なんとか辞めることができました。
回り道はしましたが、ようやく文芸部へ。インタビューは後編へと続きます。
INFORMATION

『あんまりすてきだったから』
くどうれいん/作 みやざきひろかず/絵 ほるぷ出版 1540円
歌手の歌声があんまり素敵だったから、こんちゃんはお手紙を書きました。お手紙を運ぶ郵便屋さんは、なんだかうれしくなって口笛を。それを聞いたヤマメは、なんだかうれしくなってしぶきをあげて跳ねました。こんちゃんの気持ちが不思議とみんなに伝わります。

『虎のたましい人形の涙』
くどうれいん/著 講談社 1540円
「いまのわたしが、いまのわたしで、いまを書く。いまはこれから」。文芸誌「群像」で連載中の「日日是目分量」に書きおろし1篇を加えて書籍化。時が過ぎ、変わっていくもの、変わらないもの。さりげない日常の場面や心情を切り取った23篇のエッセイを収録。
インタビュー/菅原 淳子 撮影/大森忠明(kodomoe2023年4月号掲載)







KV修正-350x350.jpg)