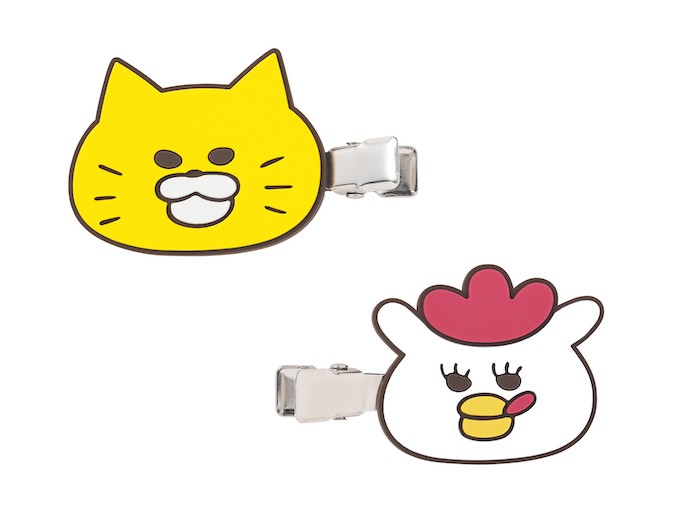作家くどうれいんさんロングインタビュー。「本当にそれでいい?」子ども時代の私が問いかける【後編】
小説にエッセイ、短歌、俳句、絵本、童話と、幅広いジャンルで執筆活動を行う新進気鋭の作家、くどうれいんさん。10代の頃から実直に、まっすぐに、書くことを続けてきたくどうさんが文芸への道を歩み出したきっかけは、子ども時代の原体験でした。
kodomoe4月号でうかがった貴重なロングインタビューを、ウェブでは全編公開。今回は、高校で入った文芸部の時代から、就職、専業作家となるまで。さらに、絵本についても語っていただいた後編をご紹介します。
くどうれいんさんロングインタビュー前編はこちら
1994年岩手県生まれ。小説『氷柱の声』(講談社)が第165回芥川賞候補作に。著書にエッセイ集『虎のたましい人魚の涙』(講談社)、第一歌集『水中で口笛』(工藤玲音名義/左右社)、絵本『あんまりすてきだったから』(みやざきひろかず/絵 ほるぷ出版)、創作童話『プンスカジャム』(くりはらたかし/絵 福音館書店)など。「群像」(講談社)にてエッセイ「日日是目分量」連載中。

――回り道はしましたが、ようやく文芸部へ。
「一番になる」と言って剣道部を辞めた手前、上位を目指さないと文芸部の立場がないと思って、応募できるものには全部出していました。高校文芸には、詩、短歌、俳句、小説、随筆、戯曲、児童文学の7つのジャンルがあるんです。全ジャンルに出していたけれど、入賞はできても、どれも1位は取れなかったんです。
――どうしてだったのでしょう。
ある大会で合評会のあと、思い切って先生に「私の作品が一番おもしろかったと思うんですけれど」と言ったら、「確かにおもしろかった。なんなら一番よかった。だけどね、君の作品を1位にしちゃうと、次から風変わりな作品しかこなくなっちゃうんだ」と。奇をてらわずに、高校生らしいメッセージ性のあるものが良しとされて、おもしろくても一番になれないなんて、ちっとも公平じゃないなって。高校生の頃はコンクールの制度みたいなものにすごく腹を立てていた時期でもありました。
――今も母校の文芸部を訪れることがあるそうですね。
「自分の書いたものを読んでください!」と言われて随筆なんかを読ませてもらうと、「努力作文」になってしまっているものが多いんです。随筆なのだから身の回りのできごとを好きに書いていいのに、「自分のことを書く」イコール「失敗や欠点を晒し、それを克服する努力をした結果、いかに良くなったかを書くもの」みたいな、コンクールで選ばれやすいフォーマットに縛られているというか。
――くどうさんご自身は、どうやって自分が書きたいことを守ってきたのでしょう。幅広いジャンルで書かれていますが。
ジャンルについては、すっきりと言い切りたいものは俳句や短歌のほうが向いているけれど、17音や31音で伝えきれないこともある。そういうものは随筆にしたり、フィクションを織り交ぜて小説にしたりしています。
自分の書くものすべてに共通して言えるのは、私自身の実体験がベースになっているということ。今と同じスタンスで小学生のときからいろんなものを書いてきましたけれど、それってつまりは、子どもの頃からずっと自分のことしか気にしていなかったということなのかもしれません。我ながら「イタいヤツだなあ」って思いますけれど。
――宮城県の大学に進学して、卒業後は地元の盛岡に戻って就職しました。仕事と並行して執筆活動を続けていたそうですね。
作家になりたいと思っていたわけではなく、これからもずっと書き続けていけたらなと思っていて。仕事は営業職でした。入社試験で書いた作文を社長が気に入ってくれたようで、その後の面接で「君は何になりたいんだ?」と訊ねられて。「仕事をしながら書き続けたい。なおかつそれを馬鹿にされない環境で働くことができたら幸せです」と伝えたら、「作文を読んだ。君のような才能を盛岡から逃がすわけにはいかない」と言ってもらえて。就職活動では仙台や東京の会社も受けていたんですよ。だけど、「文章を書いています」と言うと、「へえ、なんかクリエイティブな感じですねえ」みたいに、いじられてはメソメソしていたので、社長の言葉は本当にありがたかったです。
――4年間働いて、2022年の春に退職。専業作家となりました。
はい。いまだに「夢が叶って作家になりました!」というよりは、「小学生時代の延長でここまで来ちゃったけど、大丈夫!?」という感覚のほうが強いんですけれど。
「本当にそれでいい?」
子ども時代の私が問いかける

――小説やエッセイ、短歌をはじめ、幅広く活躍されていますが、絵本については、どのように捉えていますか?
高校の文芸部のときに、児童文学を2作書いたことがありました。ひとつは『プンスカジャム』(くりはらたかし/絵 福音館書店)の「煮詰めてジャムにする」というアイディアの元になっている作品です。もうひとつは「岩が転がって丸くなる」というのをお話にしたもの。「嫌われ者の岩が川に暮らすみんなのすみかを嵐から守るために、こっそりと働いた。嵐が過ぎると、みんなが見たことのない人が死んでいる。それは変わり果てた姿の岩だった」というストーリーでした。
当時は、正義感があって、みんなのお手本になるような人が主人公で、なおかつ教訓のあるものが絵本や児童文学だと思っていたんです。作家になってからも、心のどこかでそういうものだと決めてかかっていたのでしょうね。書いているとき、小さい頃の自分がじーっと見張っているような、なんだか落ち着かない感じがして。子どもの私が言うんですよ、「はいはい、いいお話ですね」「ちゃんと教訓もあるしさ」って。
――くどうさんがやりたいことは、そういうことではない。
発売を控えている絵本のほかに、今まさに執筆を進めている絵本がいくつかあるのですが、「ヒーローも教訓もいらない。もっと好きに書いてみよう」と思ってやってみたものの、全く筆が進まないことがあって。自分は小さい頃から好きに書いてきた自信はあるし、楽しいことや愉快なことを考えるのも得意なほうなのに「どう書けばいいの?」と、わからなくなったんです。
それで、名作として昔から読み継がれてきた絵本を片っ端から読み直したんです。そうしたら「名作って、意外と読者が突っ込みやすいものなのかも?」と思って。
――突っ込みやすいというのは?
例えば、私の中では五味太郎さんの『がいこつさん』(文化出版局)がそうで。登場人物は全員人間なのに、主人公だけががいこつの姿かたちをしているんです。「忘れていることがある」と言いながらあちこちを巡るのですが、「あ、これは自分が死んでいることを忘れてしまっているんだ、奥の深い作品だなあ」と思って読み進めていくと、忘れていたのは、なんと歯みがきだったという。「そっちかーい!」と思いつつも「死」みたいに、味付けが濃くてインパクトの強いほうへと簡単に向かおうとした自分の浅はかさに情けない気持ちになりました。
――ものの見方が試されるような。
大人が子どもに見てほしい絵本って、立派なことや正しいことだけをする人が出てくるようなものなのかもしれません。だけど、私が子どもの頃におもしろいと思っていたものは「ダメだよ~、そんなことしちゃ!」「ええっ、何やってるの!?」って言いながら読めるような絵本だったんです。
「主人公はかくあるべき」と思い込んでいたけれど、むしろ主人公がダメダメだからこそなんだか放っておけなくて、読んでいる人が関わっていきたくなるみたいな、読み手がお話に参加できることって、すごく大切だったんだなと改めて気づけました。
――確かに。意外な一面や抜けているところがあるキャラクターほど気になってしまいます。
今はみんなが「ちょっと、ちょっと~」って言いたくなるような、だけど、憎めないキャラクターを考えることがすごく楽しいんです。「さあ、どうだ! こんな子はいなかったでしょう?」って意気揚々と書いてみるんですけれど、子ども視点の私が背後から「……ちょっとハメ外してみました、みたいな?」と、冷静に言ってくる。「そうだよね、これじゃないよね」って、堂々巡りしてばかりです。
名作と呼ばれるための「これ」という正解は、絶対にあるはずなんです。なんとなく“いいにおい”は感じているんですけれど、においの正体とか、どうすればかたちになるのかがわからなくて、まだまだ手探りしている状態です。地道にやっていくしかない。でも、すごく楽しい。
いつかは「くどうれいん」という名前は知られていなくても、作品のタイトルや登場人物は誰もが知っているようなお話を作りたいんです。もちろん、小説もエッセイも短歌も何もかも、今よりもっともっと上手に書けるようになりたいけれど、今は絵本でそれを目指してみたいと思っています。
――絵本は主に子どもが読むもの。絵本ならではのやりがいがあるということ?
というよりは、子ども時代に書いたものを家族に「見て!」と言って見せていた頃みたいに、楽しい気持ちひとつで真っ向から取り組めるジャンルが今の私にとって絵本なのだと思います。
それと、私の中で絵本や児童文学は、いわゆる「子ども向け」ではないんです。3歳の「人」、7歳の「人」、12歳の「人」に向けて書いているのであって、「子ども」ではないというか。逆に私自身が「28歳の幼い人」という感覚もあったりしていて。
小さくてまだ字が読めなかったり、読んですぐには意味がわからなかったりしても、成長してから、ふと「あのときに読んだ絵本、すごくおもしろかったなあ」と思い返すこともきっとあると思うんです。まるで読んだ当時の自分と待ち合わせしていたみたいに。
――子ども時代に心からおもしろいと感じたものは、大人になっても変わらず好きだったりします。
子どもだけが特別な感受性を持っているとか、大人はそれがすり切れてなくなってしまったということでもないと思うんです。年齢ではなくて、人間がひとりひとり持っている感覚が違うだけだと思っていて。ですから、絵本だからといって「小さい子に向けて書こう」という気持ちはあまりないんですよね。何を書こうとも、「3歳のあなた」にも「30歳のあなた」にも等しく伝わるものにしたいって思っていて、それを探るのが今とっても楽しいんです。

くどうれいんさんロングインタビュー前編はこちら
INFORMATION

『あんまりすてきだったから』
くどうれいん/作 みやざきひろかず/絵 ほるぷ出版 1540円
歌手の歌声があんまり素敵だったから、こんちゃんはお手紙を書きました。お手紙を運ぶ郵便屋さんは、なんだかうれしくなって口笛を。それを聞いたヤマメは、なんだかうれしくなってしぶきをあげて跳ねました。こんちゃんの気持ちが不思議とみんなに伝わります。

『虎のたましい人形の涙』
くどうれいん/著 講談社 1540円
「いまのわたしが、いまのわたしで、いまを書く。いまはこれから」。文芸誌「群像」で連載中の「日日是目分量」に書きおろし1篇を加えて書籍化。時が過ぎ、変わっていくもの、変わらないもの。さりげない日常の場面や心情を切り取った23篇のエッセイを収録。
インタビュー/菅原 淳子 撮影/大森忠明(kodomoe2023年4月号掲載)







KV修正-350x350.jpg)