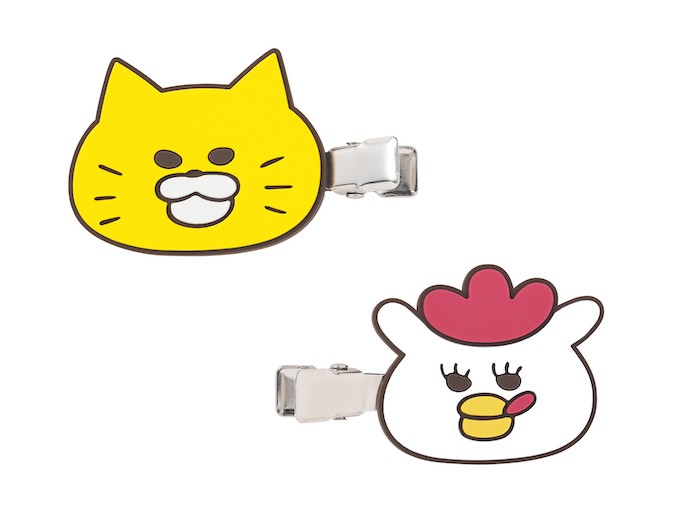内田也哉子さんロングインタビュー。両親の人生は壮大なエンターテインメントだったとさえ思います【前編】

不思議なしかけのおやすみ絵本 マジック・トーチのえほん
俳優の樹木希林さんと、ミュージシャンの内田裕也さんの一人娘である、内田也哉子さん。母親は仕事に忙しく、父親は不在。幼少時代は孤独を感じていたそうです。kodomoe webでは、本誌のロングインタビューを全編公開。前編では、若くに結婚し、家族という形を模索しながら3人の子どもを育てている内田さんに、ご両親のこと、そして子育てのことを伺いました。
ロングインタビュー 後編はこちら
うちだややこ/1976年東京都生まれ。 エッセイ執筆を中心に、翻訳、作詞、音楽ユニットsighboat、ナレーションなど、言葉と音の世界に携わる。三児の母。季刊誌「週刊文春WOMAN」にてエッセイ「BLANK PAGE」、月刊誌「家庭画報」にて季節連載「衣だより」を連載中。Eテレ「no art, no life」(毎週日 8:55〜)では語りを担当。
そっくりな母娘
母を見て育つ
2018年9月、母である樹木希林さんを看取り、その半年後に父、内田裕也さんを見送った。母の面差しを受け継ぐ内田也哉子さんは、イノセントなイメージはそのままに、健やかな身体と精神の持ち主だった。1976年生まれ、3児の母でもある。
――2017年封切りの映画『東京タワー〜オカンとボクと、時々、オトン〜』を観てきました。お母さんの若い頃を演じておられて、お2人はそっくりです。
出演したのは20代の終わりです。今は46歳なので15年以上たっていますが、あれを観た人には「似てない」と言われますよ。私はお芝居ができないから、母の自然な感じと、私の身のこなしとかがあまりにも違いすぎて。
――でも、小さいときから「似てる」と言われていたのでは。
母を見て育ってきたんですから。きょうだいもいませんし、父という存在はいたけれど不在だったので、家には母しかいなかった。自分の子どもを見ていても思うんですが、子どもって本当に見たものをそのまま吸収する。大竹まことさんのラジオに出演したときに、「姿形が似てると思ってたけど、それだけではなくて、精神が似てるんだね」と言われました。
――生まれたときからお母さんと2人家族。平均から外れていることが、当然だったんですよね。
子どもって最初っから親が一人しかいないと、これが自分の家庭のスタンダードだって思うから、何も淋しくはなかったんです。むしろ友達の親とかに、「可哀想ねえ、淋しいでしょう?」と声をかけられて、「え、なんでだろう?」。そういう自覚の仕方でした。
しかも育った家は、西麻布にあるコンクリートの打ち放しで、床が玄昌石の真っ黒な家。よくこんな環境で幼い子どもが育ったなというような危険をはらんだ家でした。角だらけで、手すりが片方しかなくてすぐ落ちてしまう階段。友達が遊びに来ると、「ここんち怖〜い」と言ってそそくさと帰っていきました(笑)。
のちに母は自宅一階の裏側に事務所を構えたので、マネージャーさんがいて、所属タレントの岸部一徳さんや大楠道代さん、風吹ジュンさんらが出入りしていました。母が仕事でいなくても大人の気配があって、困ったときは飛び込めましたけど、面倒はみてくれません。ごはんも一人で食べていました。私が生まれたことをきっかけに、母は葉巻をふかす一方で、マクロビオティック的な食生活を始めたんですが、木の蓋の鉄の羽釜で玄米を炊いておいてくれて、一品ぐらいおかずが置いてあって、ぬか漬けは切って冷蔵庫に入れてあり、「お味噌汁は自分で作りなさい」。小学校の1、2年生で味噌汁を作ってましたね。
――希林さんは「愛情を公にしないで生きてきた」という旨を話していますが、妊娠してから玄米食にするとは十分な愛情です。
母がよく言ってたのは、「子育てに確固たるポリシーもなかったけど、軸に置いたのは食べ物。なるべく低農薬で、手づくりだけどあまり手を加え過ぎてない、昔ながらの製法で作ったものを食べさせること」。そこは徹底してましたね。自分が子育てしてみて、毎日ごはんを作ることが本当に大変なことだってわかりました。しかも母はフルタイムで仕事をしながら、会社も運営して、そばにいない夫を食べさせながら(笑)。

海外ロケに同伴
服は全部貰い物
也哉子さんが生まれたのは、悠木千帆と名乗っている母が樹木希林になった頃だ。高視聴率ドラマ「時間ですよ」や「寺内貫太郎一家」でお茶の間の人気者だった俳優が、ロックンローラー内田裕也と結婚して3年目。妻は妊娠中に夫を追い出していた。
――お母さんが泊まりでロケに出かけることもあったでしょう。
そういうときは、親戚の誰かが泊まりに来てくれたりはしていました。海外ロケのときは、学校を休ませて私を連れて行くんです。当時はバブル期だったこともあっていっぱい海外ロケがあったんですよ。面倒みる人がいないこともあるけれども、「学校行くよりも海外の文化や人々に出合えた方がいいだろう」との大胆な考えで(笑)。なかなか行けないようなところに連れてってもらいました。しょっちゅう休んでたから、成績もすごい悪かったです。
――撮影中、也哉子さんはどうしてたんですか。
なんとなく現場をちょろちょろしていたり、知り合いがいる都市ではその人たちと街を歩いたり。確かチェコスロバキアの現場で、私が寝ちゃったんです。母は着ていた毛皮に私をくるんで、公園のベンチに置いたまま撮影に入って、終わって戻ってきたら長い時間なのにまだ寝ていたとか。母のショルダーバッグの中に、赤ん坊だった私が入ってる写真が残っています。
――母親が職場に子どもを連れて行く是非を問うアグネス論争が起こったのは、87年です。その10年も前に、希林さんは職場に子どもを連れて行ったことになる。
顰蹙(ひんしゅく)を買っていたかもしれないけれど、人に迷惑かけるのが嫌いな母だったので、スタッフさんに頼んだりしないで「ここで遊んでいられるわね?」と言われてた。だから私、孤独でしたよね。中学に上がるまで、洋服を買ってもらったこともなかったし。
――ベビー服は?
それも全部、知り合いのお古をもらっていたそう。おしめももらうか、さらしを縫った、と言ってました。徹底してたんです、そこは。人がプレゼントとしてくださっても、「いらない」と返すんです。子ども服もおもちゃも全部。お年玉でさえ、100円玉とか500円玉の硬貨でなければ「返してきなさい」と言われて、どれだけ辛かったか。学校の制服が途中で切り替わったとき、「新しいモデルを買ってほしい」と頼んだら、「着れるのに必要なの?」って。「みんなと同じじゃないから」と言うと、「へえ〜、あなたはみんなと同じになりたいんだ?」と、すごく軽蔑されて(笑)、「お年玉を貯めて買いなさい」と言われました。
――洋服はどうしてたんですか。
全部、人からもらった物でした。藤谷美和子さんとか、浅田美代子さんとか、岸本加世子さんとか。みんな小柄で、きっとシーズン毎に買い換えるから、何年か前の型落ちの物をもらっていました。子どもにしてはいい物だったかもしれないけど、大人のだから、肩上げしたり、縫い縮めて着て、大きくなったらほどいて着てた。
お友達がなかなかできなかったんですが、雰囲気からして異様だからでしょうね。ずっとうちは貧しい家なのか、ものすごいケチなのか、わからなかったんです。のちに母は父をはじめいろんな友人知人に、ものすごい単位でお金を援助していたことを知りました。母が亡くなったあとに、感謝の手紙が来てびっくりしたんです。
――樹木さんは、「買えるのに買わないのも辛いんです」と書いておられます(笑)。
戦後の物がないときに生まれた母は、後に実家が物だらけになるのを見て、物が溢れたところに幸せはないと思ったようです。自分の子どもが生まれたら、物の冥利が果てるまで使い尽くしてほしいと考えた。いろんな道具を揃えるのではなく、一つの道具をアレンジして使うことを学んでほしいということでした。テレビは母の部屋にしかなかったし、鍋も最小限の物だけ、包丁も万能包丁一つに小さい包丁が一つ。靴下や肌着もボロボロになったら雑巾にするのは、当たり前のことでした。
――也哉子さんが多感な頃はちょうどバブル期で、日本中に物が溢れていた時代です。
友達のおうちに行けばおもちゃが溢れていて、家に帰ってくると何もない。ある物は数冊の絵本と、母の書物だけ。人形もないから、鍋を使っておままごとしたり、傘を広げてテントを作ったり。お人形が欲しかったあのときの気持ちは、忘れられません。
――泣き落としは効かなかった?
昔のお父さんみたいな人だからまったく効かない。小さいときにりんごのむき方を教わったときも、一回だけ見せてくれて、「はいやってご覧」と言って、行っちゃうんですよね。私が指を切ってもうろたえない。小学校高学年のときに自分の部屋を作ってもらったんですが、朝起きたら布団を正して、パジャマを畳むと一通り教わってからは、一切何も言われませんでした。要するに、「あとは自分で覚えなさい」。だから小言もなし。押しつけるような発言は一度もないし、「こうしなさい」も、「こうしてほしい」も、まったくない。
――肝が据わっていますね。保育園から小学校6年の途中まで、インターナショナルスクールに通ったのは、お母さんの方針ですか。
母は近所の日本の保育園に入れようとしたのですが、離婚調停中だったので、ものすごい数の報道陣が集まって、私たちが動くたびについてきたので、入園を断られたんです。たまたま知り合いがオープンしたばかりのインターナショナルスクールがあって、そこなら外国人が多いから、過保護にもならず好奇の目で見られることもなく、普通に素で育つだろうと考えたんですね。だから、英才教育とかではまったくありません。

破天荒で不在でも
母には父が必要
――内田裕也さんをお父さんと認識したのは、いつ頃ですか。
父と会うのは年に1回か2回で、父のやってる「ニューイヤーロックフェスティバル」に、父が母に買ってきたビンテージ物のワンピースを肩上げして着せられて、「会いに行ってきなさい」と言われて、親戚のお姉さんに手を引かれて行くんです。下からステージを見上げて、終わったら楽屋に連れて行かれるんですが、その道すがら怖いメイクをしたロックンローラーがいっぱいいて。その中を通って行くと、「今忙しいんだ」とか言われてずうっと待たされて。「おお、入れ」「ああ、大きくなったなあ。どうだ?」とか言われても、なんにも会話ははずまず。「じゃあ、俺もまだ次があるから帰れ」と言われて、帰るという感じですね(笑)。だから父という認識は、最後までなかったです。
――はあ〜(笑)。也哉子って、お父さんの名前をとってるのに。
裕也の「也」が先なんですね。よく二番目だと間違えられるんですが、母に「裕也の『也』が最初ですって言いなさい」と言われました。母はものすごい父を立てるんですよね。
――裕也さんのせいでメディアに追いかけられても。
私が小さな頃は、母も私が撮られないように守ろうとしたようですが、早くに晒されることに腹を括ったんです。マスコミは逃げれば逃げるほど追いかけてくることがわかったので、母は面と向かって来た人には「こうなんですよ」「私はこう思うんです」と言うようになったんです。父は離婚届を勝手に提出していなくなったとか、不倫だけではなく、逮捕されたり、いろんなことしてきましたから。
――裕也さんとある女優の不倫は派手なスキャンダルになりました。ハワイで鉢合わせしたとか。
あの光景は今でも忘れない。税関で並んでるときに、向こうの列に2人が並んでいて。母はそこに行って、「いつも主人がお世話になってます。よろしくお願いします」とお辞儀して戻ってきたんです。私は内心引きつってましたが、母は「すごい偶然ね〜」と感心していました。日本からの便だから周囲はみんな日本人。すぐに記事になりました。子どもとは一度も旅行したことがないのに、なんで女の人とは楽しくハワイに行くの? と思いましたよね。これでも家族という形をキープしないといけないのかという葛藤は、ありました。ただ、私は母が、父のやらかしたことに頭を抱えてるとか深くため息をついているという姿を見たことがない。いつも状況を俯瞰して笑ってました。
――裕也さんも、拘置所に入ったときなど、部屋番号が「69」、ロックだとはしゃいでいて。
それを喜んじゃってね(笑)。普通なら人生はこれで終わりだと思えることも、父と母にとっては人生の面白いことの一つでしかなかったんだろうなと、今なら思えます。母は、自我が芽生えるまではあまり構ってくれなかったんですけど、私が人生について考えたり、世の中に疑問を持ち始めて「お母さん、これどう思う?」と少し大人の会話ができるようになってからは、いろんなことを話してくれるようになったんです。小学校の高学年時、父に振り回されている母を見て、「なんで夫婦を続けるの? 別れてほしい」と訴えたら、「ちゃんと話そう」と別れない理由を教えてくれました。
母は小さな頃から、虚無感というブラックホールを抱えていたんです。一度結婚したことがあったんですが、その穏やかで平和な結婚生活にも飽きてしまった。だから離婚後しばらくして、撮影現場に来た父の他の誰とも似ていない危ない雰囲気に、「この危なさがあれば、自分のブラックホールが埋められる」と思ったようです。愛とか好きよりも先に、自分がこの先一生抱えるであろう虚無感をどう埋めるかということで父を求めた。小学生の私には意味がわかりませんでしたが、「これは母の問題なんだ」ということだけは腑に落ちた。母がちゃんと生きていくためにあの人が必要なんだって、はっきり言ってくれたから、そこからは何も聞きませんでした。
――父を受け入れた?
うーん。父ともっと暖かい時間を持ちたかったけれども、それはなかなか持つことはできなかった。母が父に求める役割と私が父に求める役割は全然違うから、そこの葛藤は今でもそのまんまです。
INFORMATION

『点 きみとぼくはここにいる』
ジャンカルロ・マクリ カロリーナ・ザノッティ/作
内田也哉子/訳 講談社 1980円
点というグラフィカルなモチーフを用いて、移民問題を子どもが直感的に理解し考えることを促す絵本。貧困、差別、人種などの問題を「自分ごと」として考えられる一冊。

『9月1日 母からのバトン』
樹木希林・内田也哉子/著 ポプラ社 1650円
2018年9月1日、樹木希林さんがつぶやいた「死なないで、死なないで……。今日は、大勢の子どもが自殺してしまう日なの」という言葉。それを受けて内田さんが考え、まとめた一冊。
インタビュー/島﨑今日子 撮影/馬場わかな ヘアメイク/木内真奈美(kodomoe2023年2月号掲載)