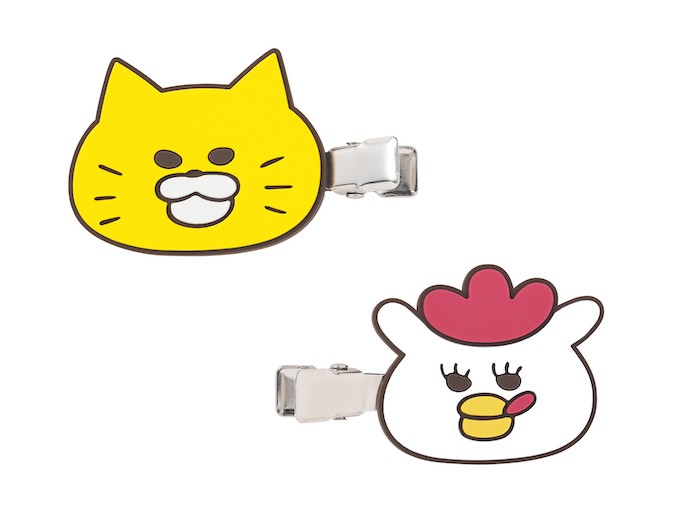マンガ家・ヤマザキマリ「息子に望むことは、自由であってくれ、それだけです」

生活のために漫画を 11年ぶりに日本へ
シングルマザーとなったヤマザキさんは、「油絵では食べられない。食べていくためには」と漫画を描こうと思いつく。
――食べるための手段として選んだようですが、漫画で食べられる人は少ないです(笑)。
社会的な仕事をしなきゃいけないと思ったんです。ボヘミアンだけが自分にできる生き方というのは心もとなかった。社会に帰属しても生きていける可能性を確認したかったんです。普通だったらどこかに勤めるんでしょうけど、私にとっては、自由を失うかもしれない社会的な仕事が漫画だったんです(笑)。
――つまり、商業主義に与するという覚悟?
出版社のシステムに従わなければならない漫画は私にはちょっと覚悟がいるものでした。でも、自分の描きたいものだけ描いていたのでは生きていけないという事が判ったので、これしかないと思ったんです。でも漫画も絵を描く仕事なわけだから、きっと長続きできるんじゃないかって。まだデビューもしていないのに凄い皮算用ですよ(笑)
――それが、今につながるというのも、またすごいというか(笑)。当時講談社から出ていた漫画月刊誌「mimi」に応募されたのがスタートでした。
母に「漫画の描き方がわかんないから、漫画雑誌送ってよ」と頼んで送られてきたのが、今はもうなき「mimi」でした。漫画は読まない人だったけど、大和和紀さんが「あさきゆめみし」を連載してたので、多分、漫画のことなどさっぱりわからない母はあの表紙で選んだのかなと(笑)
――ああ、歴史ものだから。
それで送られてきた「mimi」に、「新人賞募集!」という文字を見つけて、人生で初めて漫画を描いてみたわけです。まったく少女漫画風ではない、ブラジル人しか出てこないブラジル漫画。それを新聞紙にくるんで送りました。新人賞の中の一番下のランクにあたる努力賞に選ばれ、賞金10万、税引きで9万円をいただき、それで日本へのチケットを買って子どもを連れて日本に戻ったんです。
――息子さんを連れて帰られたときに、お母さんの反応は?
心配するだろうと思って子ども産んだことも知らせてなかったから、「ええ~っ!?」と驚いたけど、すぐに、「まあしょうがない、孫の代まで親の責任だ」と言いました。とても喜んでました。孫がかわいかったんですね。「さすが我が母の言葉だ」と思いましたよ。余計な事は考えない。ただ単純に何か素敵な、楽しい、いいことが起きたっていうあの反応が、世間体に捕われて生きない母らしかった。
――北海道では、イタリア語を教えたり、テレビのレポーターなど、7、8本の仕事をかけもちで働かれていたんですよね、タフです。
日本に戻ったとたんに堰を切ったように仕事の依頼が傾れ込んで来ました。自分がそんなに必要とされたことは今まで経験したことがなかったので、来るものは拒まずできそうな仕事は何でもやりました。イタリア語の講師、美術展のキュレーター、ラジオ番組、テレビでイタリア料理を作ったり温泉レポーターもやりましたよ。なんでもやれば絶対将来役に立つと思ってやっていました。
――全てがポジティブですね。
それでもさすがにネガティブになりそうな圧力が来たときもありますよ。妊娠中に会社が倒産しかけてて、毎日お金をどうやって返済していこうってそればかり考えて生きていましたから、「子どもがこんな世の中に生まれてきて楽しくやっていけるんだろうか、苦しみと直面するだけなんじゃないか」と猛烈に不安になりました。でも、こんな苦しいことがずっと続くはずがない、どこかできちんと幸せも感じられるときが来るはず、という確信があったのだと思います。どんなときも、私の中にはいつもそういう楽天さが機能してました。うちの母がそういう人だから。
――人生はつじつまが合う、と。そういう方に、子育ての方針を聞くのは愚の骨頂という気がしてきました。
方針、ないですよ。「生まれてくれてありがとう」と言い続けているだけ。息子にはすべてを包み隠さず話してきました。詩人のことも全部、決して悪くは言わず伝えてきましたし、「この先なにがあろうがどんなことをしてでもあんたを守るから安心しな!」という宣言もしてきた。それ以外は、「あとは知らない、適当にどうぞ」っていう感じで育ててきましたね。だから母と同じですよね。この子にこんな教育をしなきゃとか考えるゆとりもなく、とにかくまず私が「生きてることは結構幸せですよ」と提示することがお手本だと思ってました。だから私自身我慢を強いられるような嫌なことはもう堂々と避けて、「いろいろ楽しいんだよ」ということを子どもと一緒にやりました。子どもが男の子で嬉しかったなと思ったのは、私が大人になって躊躇してできなくなった遊びを、息子を口実にできるようになったから。虫捕りとか木に登るとか、もう夢中になって遊びましたよ。
――「母だから」の縛りもなく、欲望も隠さず、全て見せるっていう、一番大事なところをやってこられたわけです。
ただ母としてやったことは、カラスと同じ。自分の子どものいる巣に近づいてくる危険を察知すれば、それに対して体当たりで攻撃する。それは、本能でね。
35歳で子連れ結婚 再びイタリアへ
35歳のとき、14歳のヨーロッパ旅行で出会ったマルコじいさんの孫で、研究者である14歳年下のぺッピーノさんと結婚。そのとき、デルス君は7歳。母子は新しい家族と暮らすため再びイタリアへ。
――デルス君は、新しい伴侶との出会いも見てたんですね。
そうですね。イタリアのマルコじいさんの家にデルスも一緒に遊びに行ったときに私は旦那と出会ってますから。最初ぺッピーノはデルスと仲良くなって、とても可愛がってくれたんです。兄弟みたいに一緒に遊んでいた。で、子どもが寝静まったら、今度は古代ローマやイタリアの歴史の話とかを私として、彼としては楽しくてしょうがないわけです。だから彼の中には「この女と結婚したい」というより、「この二人と暮らしたい」というのがあったんでしょうね。彼はまだ大学生だったし、確かに恋愛感情はあったけど、それ以上に「コミュニティとして一緒にいたい」ということだったと思う。私もそう受け止めて、電話でプロポーズされたとき、「いいですよ、他には?」と答えたんです(笑)。
――デルス君の反応は? イタリアに行くことについては?
「ああ、そうなったんだ。へえ~」みたいな感じでそれ以上はなにも。まったく当たり前の事として受け入れていました。日本にいたとき、仕事に疲れると、息子を連れてしょっちゅう海外に行ってたんですよ。ニューカレドニアから知らない島に行ったり。空港の待合室にいる人たちがみんな裸足で、「これから私はいったいどこ行くんだろう」みたいなところでしたけど(笑)、デルスはあっという間に島の子どもと遊んでました。言葉も通じないのにちゃんとコミュニケーションとれてるんですよ。そういう旅を繰り返していくたびに、あの子は国籍が違うとか、言葉がわからないということに全然平気になってましたね。
――デルス君、その島では、自然にフランス語もどきの言葉も喋っていたとか。
泊まってるところがフランス人がやってる宿だったんで、みんな村の子がテレビを見に来るんですね。みんなで並んで『バットマン』見ている一番端っこに、5歳だったうちの子が座っていて、そのうちにみんなと一緒に、うちの子もフランス語もどきの言葉を喋りだして。隣の子が、一生懸命説明してくれてるのを首肯きながら繰り返している。こうやって言語って覚えるんだ、すごいもの見たなあみたいな感じでした。
――デルス君とヤマザキさんの関係は、ヤマザキさんとお母さんの関係の相似形です。
私が母に対して思ったように、デルスも私のことを、「この人は母親という役割を務めようとはしてるけど、あんまり似合ってないな」と子ども心に感じてたりもしたのでしょうね。だけども、本能レベルでの母親は絶対やらなきゃと思っていたし、人間は知性の生き物だから、道徳観とか倫理観など人として身につけておかなければならない必要最低限のことだけは教えるようにしていました。
――倫理観とか、本当に大きなくくりのことだけを、ですね。
ええ、私も、小さなころから一つの倫理意識というのは持ってました。クリスチャンの母は自分が長期の留守をするとき、自分の子どもたちをドイツ人たちの修道院に預けたりしていましたが、私も息子を仲良しの人が住職のお寺に行かせてみたりしました。「この世の中には宗教というものがあり、そこからとりあえず人として知っておくべき事を教えてもらうんだよ」ということでね。そういう場は作ってきましたよ。倫理については大人になってからあとは自分でいろいろ考えて判断すればいいのですから。
子どもには子どもの人生 健全な愛を注ぐだけ
――ヤマザキさんと息子さん、それぞれの子離れ、親離れは、さぞ早かったと思いますが。
早いですよね。最初に保育園に連れてったときだって、私の方が辛かったのを覚えています。うちの子はすぐみんなと仲良くなって、楽しそうに遊んでるんですよ。そんな彼の姿を見たときは、これまで私が「あなたがいなきゃダメ」という態度を見せなかった結果だからよかった、とは思いましたよね。本当は私だって彼と毎日ずっと一緒にいたいけど、それを我慢して仕事に出て、夜遅く帰ってきても「やあっ、どうよそっちは!?」って明るくやってきた。それはうちの母も同じでした。だから、うちの子は早くから自立できた。
――頭の中では、親はみんな、子どもはいずれ離れていくものだとわかっているんですが、なかなか手放せない。「愛」という名の拘束とでもいいましょうか。
邪念の混じらない本当の「愛」なら拘束は必要ないと思うんです。離れてようが死んでいようが「愛」っていうのはどこでも芽生えるものであるはず。人間とは、せっかく知性の生き物なんだから、そのへんの「愛」という考え方はもうちょっと熟成させてもいいじゃないかと思う。うちの母は全然家にいなかったし、言葉では一切愛情を表現しない人でしたが、なのに十分愛されてるのはわかってたし、私と妹の顔が見たくて一生懸命帰ってくるのもわかる。甘ったれた演出無しでお互いの存在のありがたさを認識し合う。それが健全な大好きさなのではないかと思います。
――確かに健全です。
自分の欲求不満や淋しさや、足りないものを補うために、ばんそうこう的に子どもを使っては絶対ダメだと思っています。子どもは親のために生まれてきたのではない。その子はその子としての人生を歩むために、生まれてきているんですよ。だから親は、細かいことを気にしてぐじぐじしている顔を子どもに見せちゃいけません。歩幅1メートルぐらいの感覚で歩けるような、おおらかな状況を作っていかないといけない。足下の石にいちいち目を止めていたらいつまでたっても目的地に到達できませんよ、って話だから。何と言っても細かいことを意識しない母親って逞しいし、子どもはそういう親を見ていたいんですよ。
――そんな母親に育てられたデルス君。反抗期ってなかったんでしょうか。
無かったです。母が心配して、「本当のこと言ってごらん、本当に腹立たしいことはないの」と聞いても、ないんです。それは、うちの家族が共同体だからなんだと思う。夫の仕事でイタリアから中東、ポルトガル、シカゴ、イタリアと引っ越していますが、環境の変化で、いつもみんながそれぞれの生け垣の中でもがいていたんですよ。シカゴにいたときは特に大変な低迷期だったので、デルスが最も反発してもいい時期でした。旦那もシカゴ大学という新しい環境で必死でしたし、私は私で『テルマエ・ロマエ』がヒットして映画化され、著作権問題や炎上問題とかが起きてて、おまけに健康も損ない、絶不調の状態だった。デルスも学校のことで大変だったろうけど、誰も誰かに対して落ち着いて何かをアドバイスできる状況じゃなかった。全員それぞれ自分たちの置かれた立場で悲惨な目に遭っていた。ああいう状況は、子どもの自立に大事かもしれませんね。
――家族3人とも爆発状態でグレる暇もなかった(笑)?
もうそれどころじゃなかった。息子は思春期だったから実はこっそりエロ本とか見てたりしてたかもしれないけど、気づかないまま終わってました(笑)。
学歴より大事なこと 自由であれ
――要は、さっきおっしゃったように細かいことはいちいち気にしてられなかったということ。そこは、大きいですよね。
子どもの態度や言動を親がいちいち見て、あれこれ言うから反抗期が起きるっていうのもあるんじゃないでしょうか。反抗って、社会に対する前にまず身内の、親の体制に対する反発だと思うから。でもうちの場合は親の体制自体が整っていませんからね(笑)。息子は私のことも旦那のことも、頼ってませんでしたから、二人の喧嘩を見ていてもまるで気に留めていなかった。泣いている私に「あいつもああ見えて一生懸命なんだから、大目に見てあげなってば」と助言してきたりして……。
二人の子どもの面倒を見ている親、みたいな立場が逆転したような行動をとることもありました(笑)。
――ということですね(笑)。でも、自立してるとはいえ、息子さんの針路については気になりませんか。
デルスは理数系が得意だったので、エンジニアを目指しました。成績の水準にあっていればアメリカの場合は大学は何校だって願書を出せる。10校ぐらい受かった中から、イリノイ工科大学に入ることにして、入学金も納め、寮まで決めてきた。でも最後に、ハワイ大学からの合格通知が来ていて、几帳面な旦那と直感力のデルスが同時に、「見に行った方がいい」と思ったんだそうです。日本にいた私に「ハワイに行ってきていいでしょうか」と連絡してきたと思ったら、ハワイに到着してものの4、5時間で「ハワイ大学に決定!」という電話がきました。レベル的に考えたらイリノイ工科大学の方が上だけど、ハワイは空も海も素晴らしく、みんなのほほんとしてて、シカゴやイリノイ工科大学で感じた切迫感が全く感じられない。私も息子に会いに行くのならハワイの方がいい(笑)。それでハワイ大学への進学を決めました。
私は、勉強ができるイコール頭の良さではないというのを知っています。ヨーロッパで学歴はなくとも死ぬほど頭のいい人を山のように見てきたから、進学校に行ってほしいとか出世してほしいとか思ったことも考えたこともありません。デルスが小さかったとき、私と取材で行ったラーメン屋のラーメンが美味しかったら、「僕、ラーメン屋になることに決めました」と言うから「どうぞなってください」。そのあと、「タコ釣り漁船のタコ釣りになる」と言うから「どうぞなってください」。何になろうと、その仕事の喜びや生き甲斐を感じてもらえれば、親である私はもうそれだけで嬉しいです。
――今の話が、このインタビューの総論になります。世間の価値基準に惑わされない生き方をしてこたられたヤマザキさんが、子どもに望むことは、「やりたいように、どうぞ」ということだけ。
そう。彼がもし将来もっと違う何かについてを勉強したくなったら、そのときはまた他の大学に行けばいいんです。何歳で何をしなければいけないとか、そんなことは決めなくていい。30で何しようが、40で何しようと、知識欲や興味が沸き続ける限り、好きなだけいつまでもその欲を満たし続けたらいいじゃないと思いますよ。私もそうやって生きているけど、総括して自分の人生には全く不満はありませんから。
――今のお話を一言に翻訳すれば「自由であれ」となります。
自由です。自由を謳歌してくれ。それだけです。







KV修正-350x350.jpg)