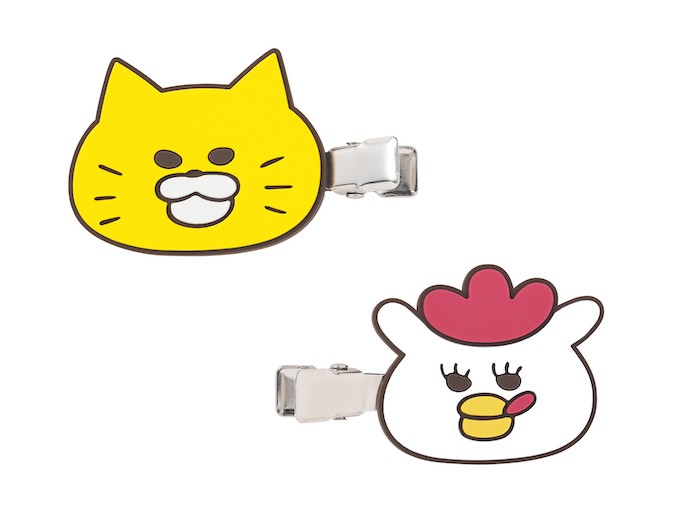マンガ家・ヤマザキマリ「息子に望むことは、自由であってくれ、それだけです」
17歳で単身イタリア留学。27歳でシングルマザーとして現地で出産。その後、国際結婚を経て、世界を股にかけて育児を行ってきたヤマザキマリさん。子育てに奮闘中のママさんに、新しい考え方、価値観を与えてくれる素晴らしい話が聞けました。読めば、心のどこかが軽くなるインタビューです。愛情さえあれば、何とかなる!! (kodomoe 2015年8月号掲載記事の完全版)
インタビュー/島﨑今日子 撮影/黒澤義教

1967年4月20日東京都出身 1984年に渡伊、フィレンツェの国立アカデミア美術学院入学 美術史・油絵を専攻。2010年古代ローマを舞台にした漫画『テルマエ・ロマエ』で第2回漫画大賞受賞、第14回手塚治虫文化賞短編賞受賞。著書に『モーレツイタリア家族』『ルミとマヤとその周辺』『男性論』等多数。現在は、講談社:ハツキスで『スティーブ・ジョブズ』新潮45で『プリニウス』を(とり・みきと共著)連載中
シングルマザーにして規格外れの母
――今、日本とイタリアを往復していらっしゃいます。
行ったり来たりですね。場合によりますけど、日本に来るとだいたい3週間〜1ヶ月ぐらい滞在します。こっちにずっといたほうが仕事的にはいろいろと効率はいいんですけど、自分の本拠地は家族のいるイタリアなわけだし、日本だけだとアウトプットはできても、私みたいに西洋美術や歴史をずっとやってきた人間には、触発の要素をなかなかインプットできない。考えてみたらイタリアに渡ってからもう30年経っていますし、うるさいとは思っても人間が声を出してコミュニケーションし合う世界にも慣れてしまっているので、やはりイタリアでの生活を完全に絶ってしまうのは難しいです。
旦那は調べ物の為にアメリカやヨーロッパの他の国に行ったり来たりしていますし、息子の大学はハワイだから家族が全員一緒っていうのはイタリアに戻ってもほとんどないのが現状ですが。
――日本ではおさまりきれないマリさんがどういうふうに育ったか。さまざまな作品に投影されていますが、お母さんが実に魅力的です。
うちの母はまったく世間体にとらわれない人で、子育てに関しても、「こうしなさい」「ああしなさい」ということもなく、お母さんとしての立場の意識を必要以上に見せなかった人です。
指揮者だった父と、ヴィオラ奏者の母の間に生まれたヤマザキさんだが、父は早世。2歳下の妹と共に、北海道の大自然のもと、シングルマザーとして奮闘する母に育てられた。
――お母さんは、「母とはこうあるべきだ」といった固定観念を持たない方でした。
うちは祖父が大正時代から昭和にかけて11年程仕事でアメリカに暮らしていた人なのと、彼女が通っていたのがフランス系のミッションスクールだったこともあり、戦前であっても海外的な考え方を自分の中に吸収していくことに規制がない環境で育ったようです。それでも彼女の父親は明治時代の親なんで、バイオリンを習っていた母が「音楽で生きていきたい」と言ったときに「花嫁道具としてやらせたことなのにそれで生きていくなんて無茶だ」と反対されたそうです。ムカついた母は、北海道でオーケストラができるのでメンバーを募集しているのを知るや、全てをリセットするつもりでまったく知らない土地に行くことを決めたそうです。勘当される寸前だったと言っていました。
――そういうお母さんの生い立ちは、追々知ったんでしょうか。
子どものときから、母になんとなく聞かされてました。暮らしていたのが千歳市だったんですが、その土地を選んだのも「空港があって東京を往復するのが便利だからだ」なんだそうです。新天地に来たのだって「ヨーロッパみたいで素敵だったし、できたばかりのオーケストラに参加するってわくわくするじゃない」とか言ってました。
――お母さん、やっぱり規格外れです。
私にとっては子どもに、「人として生きるというのはどういうことなのか」ということだけを見せていた人ですね。彼女には母親らしくしようという気持ちはあったのかもしれないし、母としてしなきゃいけないことは、当然一生懸命やろうとしてたけど、逆に私が「お弁当は私がつくるからなにもしなくていいです」と言うぐらいでした。ある日、お弁当の蓋をあけたら、片面にバターと砂糖の混ぜたの塗っただけの食パンが、まるまるぎゅうって詰めてあったことがあって、ああもう、彼女に任せるのはやめようと(笑)。
――わかります(笑)。まったく同じお弁当持ってきた友達は、隠れて食べてました。
昭和の一桁生まれで戦争を乗り越えた人ですから、食べ物に贅沢を求める感覚が彼女には無かった。子どもなんだし、これだけあれば滋養十分って考え方でしょうけどね。周りはみんな素敵なお弁当を食べてるので、私は開けた弁当箱の蓋をそのまますみやかに閉めて、後でみんながみていないところでこっそり食べました。彼女が忙しいのも判っていたし、一生懸命に母らしい事しようとしても上手くいってないのは子どもにもしっかり見えていたので、早いうちから私は「もういいよ、やれることは自分でやりますので」みたいな感じでした。
――シングルマザーの貧困が問題になっていますが、ヤマザキ家は経済的な苦労はなかったのでは。
小学生の頃、北海道の団地にいたときですが、母がオーケストラで遅くなるときの夕食代は妹と2人分で千円。折半すれば500円ずつなんだけど、物欲に負けて自ら貧しい子どもになっていた状況です(笑)。妹はしっかりご飯を食べてましたから。
母だけには頼れない 早かった自立
――小さなころから自然と動物が大好きで、自分も地球上の動物の一員だという意識が強かったとか。
北海道の野原で遊んでたときから今に至るまでそう思い続けていますが、母が動物好きだった事が強く影響していると思います。団地って動物禁止なのに、右手にバイオリン持って、左手に捨て犬抱えて帰ってきて「この子、ついてくるから飼わないと」って(笑)。あの狭い団地の我が家には猫も犬もいましたし、私は小動物大好きだったから家の中にトンボみたいな虫は飛んでたし、小鳥もザリガニもカメもいて、ちょっとした小動物園状態になっていました。母が演奏会や練習でいないとき、生命反応を示してる生き物が山のようにいると淋しさが紛れるんですね。母は帰ってくるたびに、「生きてる?」「ごはん食べてる?」といちいち聞くから、私もその中の一員になってるんじゃないか、そんな感覚でした。
――お母さんの躾は? 出かけるときには必ず手紙を置いていかれたそうですが、何が書いてあったんでしょう。
母からは必要最低限度のマナーは勿論教えられましたが、どちらかというと躾的なことは祖父から「こういうときはこうしないと恥ずかしいよ」と言われる事の方が多かったです。母は置き手紙に「遊びに行く前に宿題をやってからの方が大いに遊べます」みたいなことは書いてありましたけど、「勉強しろ」とうるさく言われたこともない。でも勉強は嫌じゃなかった。学校で教えてくれることが面白かったからですね。母が私たちにやらせたがったのは音楽だけ。バイオリンとピアノは凄く早いうちから教えられましたが、10歳ぐらいでバイオリンを叩き割って「もうやらない」と母に宣言したんです。母は私にバイオリニストになってほしくて、バイオリンだけは別の教師につけながらも、彼女からも厳しく教えられてました。だから年のわりには結構弾けてました。
――母仕込みですからね(笑)。
すっごい難しい曲を発表会でやらされるんだけど、私はバイオリンをやってる時間があったら外で遊びたいんですよ。なんでやっているのか意味がわからなかった。バイオリンへの嫌気が露顕しはじめると、母は「とにかく音楽だけはやっておいたほうがいい」って、力説するわけです。「音楽をやることがあなたを、いずれ救うかもしれない、道端で弾けば小銭を投げてくれるかもしれない」とか、理由がどんどんどんどん低次元になっていった(笑)。でも、あまりに執拗にバイオリン、バイオリンと言われるから、もう我慢できなくなって怒って楽器を床に叩き付けました。そしたら、「わかった。じゃあ辞めていい。」と。ピアノは結構長くやってましたけど。
――それでも、ヤマザキさんにとって音楽はインスピレーションの源。
そうです。お留守番ばかりはかわいそうだという彼女の計らいで、夜のコンサートに連れて行かれることがあるのです。そういう時、私と妹を客席の最前列に座らせるわけですね、その位置だと舞台からもよく見えますから。でも、楽しい曲ならいいんですが、シベリウスとかショスタコーヴィチみたいな人の曲は子どもにはとても退屈で、そのうち、「もう勘弁してよ」ともじもじしてくる。そんな私たちを演奏中の母がじっと見てるから、「ヤバイヤバイ! お母さん、指揮見てない!間違える」とドキドキしちゃって。つまらない音楽を聴きながらもできる限りお利口さんにしていました。
そしてそのときに身につけたのが、つまらない曲を聴きながら物語を考えるというスキルでした。だから今も、創作をするときは音楽をかけます。私の妄想力は音楽からきていて、それはそんな経験の影響が強いですね。
――作品には、小さな子を置いて働きに出る母親を批難する人もいるけれど決して動じないお母さんが描かれています。ヤマザキさんは、自分の環境が他の子どもたちと違うことは不自由でした?
母がそういうことを気にしている風でも全くなかったので、私も全然意識してませんでした。母はとにかく音楽家として音楽をやることにまっしぐらだったから、周りの奥さんたちの噂話なんて眼中に入っていないわけです。私も、近所の人に「マリちゃん、いつもお留守番大変ね」と言われてましたけど、「えっ、何が?」って。大変さはなかったけれど、淋しくは勿論ありました。公園で遊んでいると日が暮れてきて、5時の鐘が鳴ったら他の子どもはみんなお母さんたちが迎えに来る。団地のあちらこちらから、夕飯のおいしい匂いが漂ってくる。みんなは帰って行く家もあれば、わいわいお話をする家族がある。やはりあの感じは未だに思い出すとしょんぼりした気持ちになりますね。
――切なさはありますよね。
団地ですから、うちだけ電気が家に灯ってなかったりするとなんとも言えない気持ちになる。母がいないときに妹が迷子になっちゃったときがあって。私一人で探しても探してもいなくて、あのときはやっぱりへこたれそうになりました。最終的には遠く離れた公園でひとりでブランコに乗ってるのを見つけたんだけど、ああいうときに、「もう母ばかり頼れない」という意識が芽生えてましたね。妹はとにかく母よりも私を頼って生きていましたから。保育園も他の子のお迎えは全部お母さんなのに、妹だけ私。迎えに行くと妹が「なんだまたねえさんか…」ってつまらなさそうな顔をされる(笑)。彼女には子どものときから、「ねえさん」と呼ばれていました。
初水泳はパンツで グッズは自主制作
――物心ついたころから絵を描いていらっしゃったそうで。
絵とお話を作るのが大好きだったので、自分で楽しむ様に紙芝居を山のように作ってたんです。習っていたわけでも、誰かに言われたわけでもないから、ラスコーの洞窟状態ですよね。とにかくヘタでも何でも何かを描いていないと落ち着けない、という感じで、それが今につながっています。言語であったり、音楽であったり、自分を満たす表現化のツールはいろいろあるけど、私の場合は絵を描くことがなによりも一番楽しかったのです。
――当然、そのときは、将来何になりたいとかは。
なんにも考えていません。ただ母に「絵描きさんになりたい」と言ったときに、「これ読んでごらん。大変みたいだよ、絵描きさんになるのは」と買って持ってきたのが『フランダースの犬』の絵本。まだアニメ化される前の話です。絵描きになりたいと思ったが為に散々な目にあう少年と犬の非情きわまりないあの話を知ってもらうことが、「一応私は警告しておきますが、それでもなりたいならどうぞ」ということを意味していたのです。同時に『シンドバッドの冒険』や『ニルスのふしぎな旅』など、「世界はここだけじゃないよ」という物語を読まされていました。「絵をやってて、最終的につぶしが効かなくなったらネロみたいに行き倒れになる前に、どこかへ行けばいい」という教えもあったのかもしれません。
――子どもにちゃんと選択を任せているところが素敵です。
母は、音楽以外「なになにしなさい」が一切なかった。女の子らしい洋服を着せられたことも1回もないですよ。いつもジャージかジーンズ。そういえばいまだに忘れられない恥ずかしい思い出があります。小学校1年のときにプール学習が始まったんですが、担任がおばあちゃん先生で、「水着を買えない子もいるだろう、そういう子はパンツ一丁でいいですよ」と言ったんですよ。そのことを母に言うと、「じゃあ、パンツでいっといでよ」って。で、翌日、本当にパンツ一丁でプールに入ったら、周りは全員水着で、「どうしたのマリちゃん?」。しかも授業が終わったあとに、「今日は一人表彰したい人がいます」って。もうやめてくれと思いました(笑)。あの40年前の出来事を思い出すと、いまだに羞恥心がこみ上げてきます。「今日はパンツ一丁だったことで表彰されました…」って母に言ったら、次の日にすぐに水着を買ってくれましたけど。
――さすがに(笑)。
さすがに(笑)。子どもの服装には無頓着だったけど発表会でバイオリンを弾くときは、自ら気合いの入った服を作ってくれました。彼女はフリフリのピンクとかは嫌いなので、演奏旅行でヨーロッパに行ったときに買ってきたチロリアンテープを紺色のベルベットのワンピースにあしらったり。『暮しの手帖』の愛読者だったので、あとは持っている服からリサイクルですよね。若いときに彼女が着ていたオーダーメードの服からボタンとかいろいろとってきて、リフォームしたりしていました。
――お母さんは、『暮しの手帖』の創刊時からの熱烈な愛読者だったんですよね。
彼女が、十代ぐらいのときから買い始めたと聞いてます。家にはそれしか読むものがないから、私たちも『暮しの手帖』の熱心な読者になりました。いきなりオーブントースターのテストのために4万枚焼いたパンの写真が出てきたりするのをみて、ああ、大人になっても子どもみたいなことしていいんだなって(笑)、妹とふたりで笑ったり驚いたりしながらページを捲ってました。毎号ありとあらゆる実験や検査がされているから、それが楽しみでしょうがなかった。母が尊敬していた花森安治という人は反物欲主義者でしたが、母はまんまと影響されていましたね。
――子どもですから、キティちゃんとかも欲しかったでしょ?
勿論欲しかったです。でも、母は協力してくれないから、なけなしの食事代から50円ずつ貯金して自分で買ったりしてました。もう余程欲しいときは、最悪、作りましたね。私の作品である『ルミとマヤとその周辺』で妹のマヤが自分でスヌーピーのサンバイザーを作るエピソードを描いてますけど、ああいうことを私も本当にしていたのです。いまだに残ってますよ、私の作ったサンリオ商品。ちゃんと「サンリオ」とか200円といった値段も描いてあって不憫さ丸出し(笑)。スヌーピーとか、自慢じゃないけど、原作者シュルツの偽サイン入りで未だに上手に描けます。
運命を決めた 14歳ヨーロッパ一人旅
転機は14歳の冬休みにやってきた。一緒に行くはずだった母が行けなくなり、一人で送り出された一か月間のヨーロッパ旅行。旅の途中で出会ったマルコじいさんが、後にイタリアへヤマザキさんを誘い、やがてその孫ペッピーノがヤマザキさんの伴侶となる。
―――中学の娘を一人でヨーロッパへ出すとは、豪胆なお母さんです。
母には私への信頼があったんでしょうね。言われなくてもやることはやってきてるし、留守番も国内移動も誰かに頼らなくてもできるから、大丈夫だろうと。私のほうは「なんとなく楽しそうだな」ぐらいにしか思ってませんでした。本読みで、海外の文学を山のように読んでたから、本当のヨーロッパを自分の目で見てみたいというのはありましたが。あと兼高かおるさんが大好きだったから、”兼高かおるやってみようか”、ぐらいの浅はかなノリでしたね。
――一人旅はいかに。
パリの空港は迎えに来てくれた人がいたからよかったんですけど、そのあとですね。一人で移動しなきゃいけなかったときに、パリ市内で駅の乗り換え方がわからなくなって、呆然自失状態になってしまった。あのとき、「私は今ものすごくヤバイことになっているのではないだろうか。どうしよう」と硬直しましたよ。泣きそうになりました。でも、次の瞬間、「いや、大丈夫。自分がいるから自分を頼れば大丈夫」という自分の分離が起きたんです。「こんな縁もゆかりもない地なのにしっかり足着けて立っていられるんだから大丈夫!」って自分を励ました。なんでしょうね、あの精神状態。
――自分をはっきり客観視できるようになって、殻が破れるように内側から新しい自我が出てきたのでしょう。そのとき、英語はどれぐらい喋れたのでしょう。
英語はまあ比較的得意ではあったんですけど、学校のテストでいい点とる英語と喋る英語はまったく別次元ですから、さっぱりダメ。でも喋れないダメさに捕われてる場合ではないわけです。「今は生き延びることしか考えてはいけない。このあとどう私は進んでいくのか」と、それだけしか思ってなかった。言葉ができなくてひるんでる場合じゃないですよ。日本の人って、外国語に弱いと言われているけど、「きちんと喋んなきゃ」という意識から入るからダメだと言われていますね。私はもうそのとき、正直言葉なんてどうでもよかったんです。何語でもとにかくコミュニケーションが成立すればよかった。なんとしても私を待ってくれているドイツの家に行かなければと、タクシーを止めてドイツ行きの列車が出る駅に連れていってもらいました。列車のチケットを見せれば、その列車の出る駅を判断して連れてってくれるだろうという漠然とした思いで。それを乗り越えたら、俄然自分が頼もしくなりました。
――そのときの身長は?
今と同じ163センチぐらい。小さなときからずっと身長は高くて、小学校のときはバスケとバレーボールやってたんです。でも止まりましたよ、その旅で。もう背伸ばしてる場合じゃない(笑)。
――そこで身長が止まったのは、非常に暗示的です。
そのとき、聖子ちゃんカットでハマトラスタイルの14歳のどうしようもない娘っ子でした。家出少女にしか見えなかったので、列車の中でマルコじいさんにつかまって「家出か!」って言われて。「10歳くらいのくせに!」ってもの凄い剣幕だったけど心配してくれてたんですよ、他所の子どものことを。それがきっかけでマルコじいさんとの交流はずっと続きました。







KV修正-350x350.jpg)