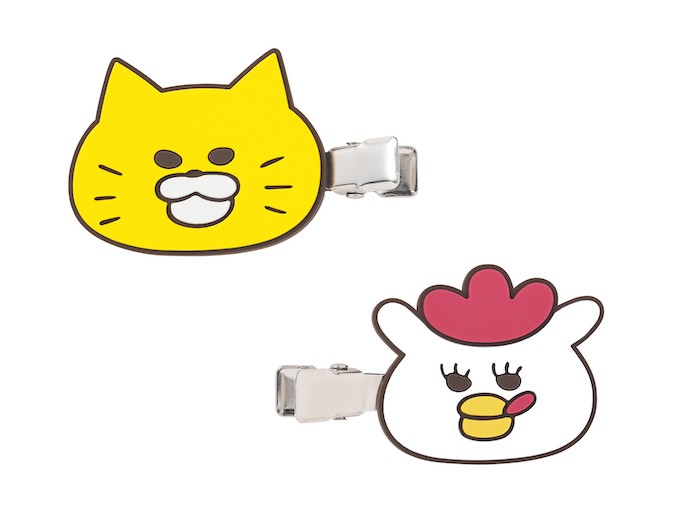マンガ家・ヤマザキマリ「息子に望むことは、自由であってくれ、それだけです」

お嬢様学校の異端児 「ここにはいられない」
――その旅を通過したあとは、厳しい校則に縛られたり、学校や日本も窮屈に感じるようになります。
日本に帰ってきた途端に、「こんなことどうでもよくない?」みたいなことがそれまで以上に目につくようになったんです。何通りもの生き方が許されて、世間体というものが存在しないヨーロッパを見たあとに、「世間体は」とか「規則が」と言われても、もうなんか堪らなくて、制服だの学則だの、こんなことにエネルギーを使っている場合かという気持ちになりました。
――日本の場合、規則より目に見えない規範に縛られますから。
世間体という目に見えない戒律的なものが、リアルに感じられるようになってきてしまって、ここに長くいては息ができないと思うようになってしまったんです。高校に進学したときに、「絵描きになりたい」と言うと、先生に「絵では食べていけませんから、それは薦められない。それでも絵をやりたいのなら美大を目指す予備校へ行ったほうがいいでしょう。」と言われました。ヨーロッパには見るからに貧しそうだけど、開放感があった。なんで日本では絵描きみたいな自由を謳歌できる仕事がしたいといっただけであんなに反感を買ったり懸念されたりするのか。とにかく失敗してもいいから自由になりたい、貧乏でも自分のための自分にふさわしい人生設計をしたい、って思ってました。
――高校でスキンヘッドにしちゃったんでしたっけ。
パンクに嵌っていたので。今思えば、短絡的にもほどがありますね(笑)。18歳未満でしたが、一時期、ツバキハウス(80年代に新宿にあったディスコ)やパンク系のクラブに行くのが楽しくて夜遊びに忙しい時期もありました。
――コム・デ・ギャルソンを着てバイトしたり。
ギャルソンは高いから自分で同じようなのを作って着てました(笑)。なんせ私のバイト一発目は、ちり紙交換ですからね。『PIL』という漫画に描いてますけど、バイト誌の情報だと、1日働けば2万円とか、すごい高額だったんですよ。条件も悪くなくて、「これはやるしかない」と思って、弁護士の令嬢だった友達と一緒に面接に行きました。そしたら「うちは出来高次第なんですよ。積めば積むほどお金は入る。頑張ってください」と言われて……。1日、朝から晩までトラックの荷台に乗せられ、頑張ったのに、なんと500円にしかならなかったんです。えぇぇ~って。挙げ句の果てに「新聞紙だけじゃ足りないから」と言われて、酒屋の段ボールとかまで回収させられた。死ぬほど辛かったです。2日間頑張りましたけど、さすがに体力的に保たずやめました。
――じゃ、稼ぎは千円で終わったんですね。
千円で終わりました。でも、こうやって苦労してお金稼がなきゃいけないんだな、というのは身に沁みました。それが高1で、そのお金はパンク音楽に費やされるわけでですが…
――完全なる反抗ですよね。
社会に対する反抗ですね。でも、「不良」とか「暴走族」とか反抗をするという部類の集団の一人になるのは嫌だった。何よりも、帰属というのが子どもの頃から合わない性質だったわけですから。たとえば制服にしても形が気に食わないと、制服の生地だけ買って、仕立て屋さんに1960年の制服の写真を持っていって作ってもらうんですよ。そしたら呼び出されて、「なぜみんなと同じにできないのですか」。「みんなと同じになりたくないからです」と答えると、「とにかく真似する人がいるからやめてくれ。」あのとき「ああもうだめだ、どこか別の場所に行こう」と本気で思いました。それまで耐えていたあの学校組織への帰属や社会の中の集団生活でやりくりしていく我慢の限界が訪れたのです。
「私は、やっちゃいけないことは何一つやってないです」と思ってました。髪は三つ編みをして白いリボンで結ばないといけないんですが、私は、ちっちゃい三つ編みをいっぱい編んでドレッドヘアにして、それを束ねてたんですよ。そしたら、シスターに呼び出されて、「その髪型は、どういうおつもりなんですか」って。「三つ編みですよ」と答えると、「いい加減にしてください…」とため息つかれちゃったので、丸刈りにしたんです。そのときは「そんなにうちの学校がそんなにダメなら、他のところに移られていいんですよ」と言われましたね。それでも校長先生と母が仲良しで、校長先生は私を面白がってくれていたので学校には行ってたんです。だけどやっぱり周りのPTAだのなんだのを意識するとどうにもいられない。だから母の中では「ああ、この娘はどうにかしないと」という思いがあったんでしょうね。
17歳でイタリアへ 息苦しい日本から脱出
――お母さんも、日本ではこの子は息苦しいだろうなとわかっておられたのでしょう。
機会があれば外に出した方がいいかなと思っていたんだと思います。パンク嗜好に走っていた私はロンドンに行きたくて、ロンドンの語学学校のパンフレットを取り寄せてると、母は「行きなよ」と言う状態だったから。でも、その間に、母は私がヨーロッパで知り合ったマルコじいさんと文通友達になっていて、「うちの娘はイギリスに行くことにしたらしい」「イギリスなんか行ったって、行く末もわかんなくなる留学生になるだけだからやめろ。『絵が描きたい』と言ってたんだから、イタリアに寄越せ」というやりとりが交わされていました。水面化で着々と事を進めてた(笑)。それで「一回行ってみなさい。ダメだったら、イギリスへ行き直せばいいんじゃないの」と言われて急にイタリアに行くことが決まったわけです。高校を辞めたら大学検定試験をとるのが条件だったので、それはクリアしていよいよ行きたくもないイタリアへ発つことになりました。私の意志は一抹も入らずして。
――それが17の夏。第二の転機になります。イタリアに降り立ったときの気持ちは?
14歳のときの「ヤバイ」がまた戻ってきました。「呼ばれもしないのに、縁もゆかりもないところに来てしまった」という。これからは全部を、私の意志で動かしていかなきゃいけない、開拓しなきゃいけないという緊張感で冷や汗が沸き出しました。
――そうか、頼りになるたこ糸みたいなものがゼロなんですものね。
この先にはたくさんの困難があることはもう絶対に決まっているので、諦観するしかありません。でも、ローマの空港に着くとマルコじいさんが迎えに来てくれて、そのままバスに乗って、コロシアムとかを回りました。見たことも、想像したこともないあの二千年前の遺跡を見たとき、自分の中の時空の価値観が変わりましたね。見えてるものだけが時代じゃのだ、ここは思っていた以上に奥が相当に深い場所なんだと。「とんでもない国に来たわ」という気がしました。
――そんなふうに瞬間瞬間に何かを感受できるのは、小さいときから見たもの触ったものに対する感受性が育まれてきたからだと思います。
そうでしょうね。なんせ想像力だけは豊でしたから、細かいこともキャッチする感受性が育ってたんでしょうね。そしてそれを規制されるどころか、花森安治の商品テストのおかげで「どんどんやっていい」と思う大胆さが身に付いていた。
――ある意味、もちろんお母さんが「母」なんですけれど、花森安治がヤマザキさんの「父」ですね。
ええ。かなり重要なポジションにいたバーチャル「父」ですね。スカートはいたりしてノージェンダーな格好はしていましたが。
――だからヤマザキさんにはジェンダー(性差)の壁もなし。
なし。母から「女らしくしなさい」と言われたことは生まれてから一度もないし、女らしさを意識しなきゃと思った事も一度もありません。
詩人と恋に落ち 知識人と交流
84年の夏、17歳のヤマザキさんは、陶芸家だったマルコじいさんのはからいで、フィレンツェの美術学校に入り、11年間油絵を学ぶ。同時に、それは一人の男性と過ごした時間でもあった。
――フィレンツェの美術学校は、画家志望には憧れの学びの場です。
日本から来てた人たちは、みんな芸大とか多摩美とか武蔵美を出てきた結構年配の人ばかりでした。
――いわゆる芸術、アートのエリートたちですよね。
だから、「あんた何?」って言われて、「いや、何って私も自分がどうしてここにいるのかわかりません」みたいな感じでやってましたけどね。
――本場で、17歳の子が一人暮らしをして芸術を学ぶ。羨ましい環境ですが、同時に過酷です。
間もなく学生同士でシェアしていたアパートの隣の部屋にいた4つ年上の大学生だった詩人が好きになりました。あのときは、イタリアに居続けなければならない理由付け的意味もあって、積極的にその人のことを好きになったのだと思います。どんなに辛くても、フィレンツェにどうしてもいなくちゃいけないんだという強固な理由を欲して。
――自分で、引力になる対象を探してたというわけですか。
小学生のころ『はみだしっ子』(三原順の漫画)が大好きでした。その登場人物の一人である、アンジーのような世の中に対してシニカルな性質を持った詩人に出会った瞬間、漫画で培った妄想力がワーッとスイッチオンになって一緒に暮らし始めました。でも、ダメですね、詩人というのは要するに経済的生産性から離れていなければ成り立たない職業です。要するにお金に縛られる詩人なんて存在しない。だから私が彼を養いました。日本語でできるありとあらゆるバイトをして、彼を養い、作品を集めた本まで出して(笑)。
――詩の本まで出してあげたんですか!
出してあげましたよ、千冊も。3冊しか売れませんでしたけど。
――11年一緒に暮らし養うだけの魅力が、彼にはあった?
もちろん。私より4つ年上でしたけど、ものすごい頭がいい人だったんです。直感力に優れ、経験値も豊富でした。知識や教養の深さも半端なかった。彼は文学青年ですからいろんなことを知っていて、「君は、谷崎(潤一郎)だったら何が一番好きだ」とか聞かれたりもしました。ヨーロッパ文学は子供のころから読んでいても、川端(康成)も、三島(由紀夫)も読んでいなかった私は、「同国の作家なのに知らないなんて信じられない」とすごく責められた。しょうがないから、彼のを借りてイタリア語で読んだんですが、安部公房の『砂の女』を読んだときに、もの凄い衝撃を受けました。「こんな作品があったのか」ってなって(笑)。
28歳で息子誕生 シングルマザーに
――そんな娘の様子を、日本にいたお母さんはご存じだったんですか。仕送りはあったんですよね。
仕送りは5万くらいでしたが、5万でやりくりできるわけがないじゃないですか、詩人を養わなきゃいけないし。母は私のアパートに来たとき、ガス、水道、電気とインフラが全部止まっているのを知って、「本当に『フランダースの犬』じゃないの。わたしは別な場所へ行きます」とか言って、すぐマルコじいさんの暮らす街に行っちゃいました。
――詩人のことは、どうおっしゃいました?
「あの人全然働かないけど大丈夫なの?」って嫌がってました。でも、「別れろ」とは一言も言わない。「しょうがない」って。「お母さんはあの人は問題あると思うけど、あんたが好きになった人だからそれは関係ない」と言ってました。
――それは立派です。
10年間、ずうっと言い続けてました。だけど、彼女は、そんな詩人にもいいところもあるというのはわかってたようです、もともと母という人間は、非常に騙されやすい人なんですよ。彼女にとっては世の中全員いい人なんです。人の悪い所が見えてもそこに執着できず、「でもいいところもある」ってなる。詐欺で騙されたときも、「でも、いい人だったのよ」とか言うから(笑)、この人はなんていうか、どうかしているけど素晴らしいなあと思っちゃう。環境を自分に都合よく整えていく人なんですよ。
――そこの部分は、娘ももらっているでしょう。
私はそんな母を持ったお陰でかなり疑心暗鬼に育った部分はありますけどね。様々な経験を経て今では一見良い人でも簡単には信じられません。その詩人と暮らすのは大変だったけど、刺激し合えるし、触発し合えて、もらえるものもありました。ただ私が若くて、「騙されてていいや」と思ううちはよかったんですけど、10年目にして子どもという現実が目の前に突きつけられたときに、「もう『はみだしっ子』ごっこ終わりです!」となって、ガシャンとシャッター降りました。
――息子さんを出産したときに選択の瞬間が訪れた。
あのときは、私一人の力では、詩人と子どもを養っていくのは無理だと思ったんですね。彼は大人なんだから、いざとなればどうにかして生きていくだろうから、私は首もすわっていないこの子をなんとかしなきゃいけない、と。「わあ、赤ちゃんだわ♪」なんて思えるゆとりはなかった。
――妊娠がわかったとき、経済的にもどん底でした。
妊娠がわかったときは「え~っ」となりましたよ。ただ、「でも産むべき」という説得力のある直観はあったんですよね。この人と私の子どもだから産もうと思ったんです。親は問題あるけど、感性的にはきっとなにはともあれ、人生を面白いと思ってくれる子どもがうまれるんじゃないだろうかって思ったんです。
――産んだ瞬間に「別れます」と告げられた詩人は、さぞや驚いたでしょ。
2年間ぐらい別れる別れないでゴタゴタが続きましたね。でも、最終的に私たちのボヘミアンごっこは終わらなければならなかった。人は誰でも、大人になったら苦労は避けて通れない。だから子どもが生まれてきたときに、最低限、親の私がやらなきゃいけないのは、「ようこそ」と待ち構えていること。「私はあなたが一番最初に見る人間です。人生いろいろありますが、楽しいですよ」ということは見せなきゃいけないんです。だけど、彼が生まれたのはちょうど私と詩人とでサブビジネスとしてやっていた会社(アクセサリーや皮製品の露店)が倒産したときで、家財道具まで持っていかれた状態。そんなところにいきなり生まれてきて、素敵な社会も何もあったもんじゃないじゃないですか。それを全て抱えた状態で「素敵な世界へようこそ!」と子供を向かい入れられる心境では全くなかった。だから子どもをひとりで育てることを選んだのです。母に育てられてますから、シングルマザーになることに対しても、まったく躊躇はありませんでした。息子には小さい時から、お父さんの事もしっかり話してましたよ。会いたい時にはいつでもどうぞって。私とはうまくいかなかったけど、子どもとは仲良くなるかもしれないわけですから。
――息子さんの名前はデルス。黒澤明監督の『デルス・ウザーラ』からとられたとか。
あの話を読んでいると、私も主人公であるデルスのように地球から守られて生きる人間になりたいという気持ちになるんです。私は黒澤監督の映画を観る前に原作を読んでいて、シベリアのタイガという過酷な自然条件の中でも他の動物たちと調和を保ち、しかも人間最大の困難である「孤独」をきちんと味方につけている老人デルスに心底感動しました。だから子供が生まれて来た時には迷い無く、この名前をつけました。彼が自分の名前のルーツを知った時も、きっと励まされるだろうなと思って。







KV修正-350x350.jpg)