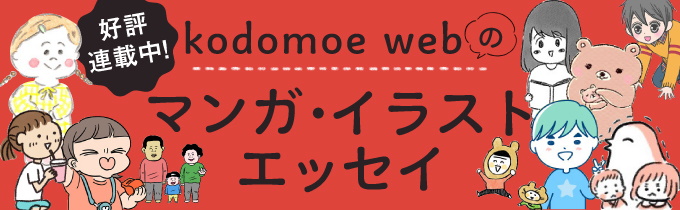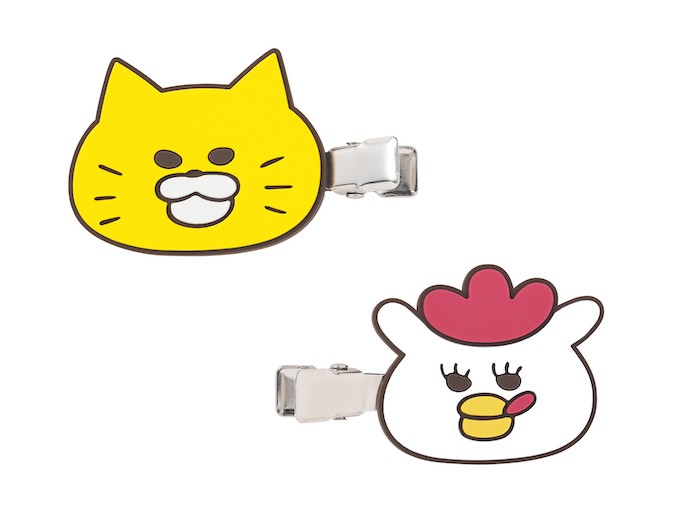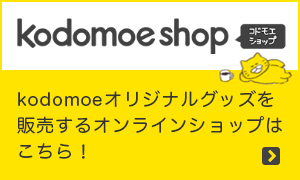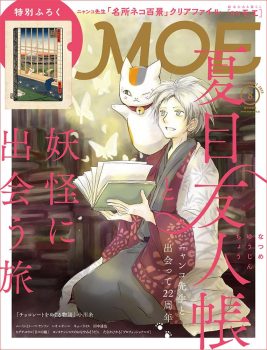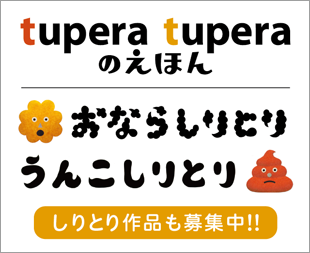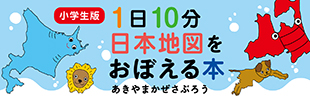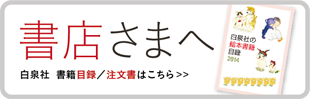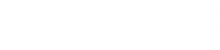絵本作家・大森裕子さんロングインタビュー。『ねこのずかん』や『いぬのずかん』は、子どもの頃の私がほしかった図鑑です【前編】
『へんなかお』、「コドモエのずかん」シリーズなどkodomoeでも多くの人気作を生み出してきた大森裕子さん。少年と猫の関係を描いた『わすれていいから』(KADOKAWA)は、MOE絵本屋さん大賞で第2位を受賞。猫をこよなく愛する大森さんに、絵本作家になるまで、子育てを振り返って、そして猫との生活をお聞きしました。kodomoe webでは、本誌の貴重なインタビューを全編公開。前編では、大森さんの子ども時代や、頼りになるプロデューサーだというご主人のお話などをご紹介します。
おおもりひろこ/1974年神奈川県生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科絵画専攻修了。MOE絵本屋さん大賞に『へんなかお』で2011年第4位、『パンのずかん』で2018年第7位&パパママ賞第3位、『ねこのずかん』で2019年第9位(すべて白泉社)、『わすれていいから』で2024年第2位など受賞多数。大学生と高校生の男子2人の母。

小さい頃から観察して
描くことが大好きだった
――大森さんは子ども時代、どんなお子さんでしたか?
うちは父も母も教師で、共働きでした。幼稚園入園前のちょっとしたテストの日、母が仕事で来られなくて、他の子はみんなお母さんと一緒なのに、私だけはお祖父ちゃんだったんですね。それがすごく嫌で大泣きして、入園をお断りされたという(笑)。まあ、昔だったので、なんだかんだそのあと入園できたんですけど。
絵を描くことはその頃から好きでした。園に絵の時間だけ、外部の先生が来てくれていたんですよ。本物のニジマスを持ってきて、「ピカピカしてる姿を描いてみよう」とか、冬に「桜の木を描きに行くぞ」って、大きい紙と真っ黒のコンテを一本くれて、「下から描くんだよ。どんなふうに枝が分かれてる? よく見てね」って。もう楽しくってしょうがなくて! 目の前のものを観察して、描くのが大好きでした。
――幼少期に、そんないい出会いがあったんですね。
あとはまあ、空想好きで。家の裏庭に行って、木の枝と石を手に、何時間でも空想して遊んでいられるような子どもでした。飼っていた動物のお墓もあったから、眠っている動物たちとおしゃべりしたり。大好きな時間でしたね。
対人関係でうまくいかないつらい気持ちを、動物とコミュニケーションをとることで埋めようとしていたのかもしれない。動物は本当に純粋だから、真剣に犬とかとしゃべりたくて。まだ漢字も読めないのに、大人向けの『犬と話す本』みたいなのを「どうしてもほしい」って買ってもらってました。
小学校の下校時は、犬がいる家を回って帰るっていうルートを作って。「今日はどんな気分かな」「もっと喜ばすにはどうしたらいいかな」とか考えてました。
――動物たちと、本気で仲良くなりたかった。
はい、今「ずかん」シリーズを描いているのも、同じ気持ちです。犬や猫と仲良くなる方法とか、自分が知りたかったことを今描いてます。まだ幼い当時も、どうやっていいかわからないけど、自分なりに図鑑みたいなものを描こうとしていた記憶があります。だから、夢が叶ったんですね。担当さん、描かせてくれてありがとうという気持ちです。
4歳の頃の野菜の絵とかも、かぼちゃの種が薄く透けているところとか、ラディッシュの色が変化していく様子とか、当時からすごく喜びをもって描いていました。今も、あんぱんのゴマがどういう向きについてるかとか、皮がむけてるゴマと黒いゴマの割合とか。いつもそういう細部に喜びを見出してしまう。ミクロな嗜好があるんだと思います。
安定志向の母と
夢をあきらめない娘
――その頃から絵本作家への憧れがあったんですか。
小学1年生の頃かな、なにかの拍子に「絵本作家になろっかな~」って言ったんですよ。そうしたら母が、「のたれ死ぬからやめておけ」って言ったんです。すごいよね(笑)。「絶対にお金稼げないから。そしてだんだん描いているうちに心を病む」って言ったの。
――すごいですね。でも、安定したご職業のご両親からすれば、心配だったのでしょうか。
まあ、昭和という時代を加味して聞いてあげてください(笑)。自分もその時は「あ、そういうもんかなあ」と思いました。結局、全然聞いてなかったんですけどね。
――それでも、ずっと絵本作家になりたかった?
小学校ぐらいになると、さらに動物大好きになっていて、当時はテレビでムツゴロウさん(※)の愛称。動物との共棲を目指し北海道に「ムツゴロウ動物王国」を設立。)が流行っていて、自分も野生動物を保護する活動がしたかった。でも、母の洗脳が入っているから、「――それだけだとお金が稼げないから、本を執筆してそれを売って、その売上で生活する」というプランまで含めた将来の夢を、小学4年生の頃に作文に書きました。でも、その作文への母親のコメントがね、「そう簡単にいくわけがない」って(笑)。
もちろん、「裕子らしいね、頑張ってね」みたいな感じはあるんですよ。だけど、「大人の目線から言うと、そううまくはいかないのが現実なのです」みたいなことを、チラッと入れてくるんですよね。そういうのは、すごく嫌だったなあ。
(※)ムツゴロウさん…小説家、動物研究家の畑正憲(1935〜2023)の愛称。動物との共棲を目指し北海道に「ムツゴロウ動物王国」を設立。
――それでも、大学は美大志望で、東京藝大に。
はい、絵はずっと好きだったから、「美術だけの大学がある」と知り、即「そこに行こう!」と思いました。母もそれは止めませんでしたが、「美大に行くのはOKだけど、将来絵だけ描いて生活するなんてあり得ないから、教職はちゃんと取っておくといい」って。
それで、そういうもんかと教職を取って、中学に教育実習に行くんですけど。もう本当にそのときの私の、死んだような目を見せてあげたいです(笑)。私は、教師になりたかったわけじゃないんです。
実習はちゃんとこなしましたが、自分の心がいないんです。だからどこかむなしいし、苦しい。「こうするのがいいからする」っていうのと「こうしたい」はぜんぜん違うんですね。「いいからする」っていう価値観に基づいた言動には、その人自身のエネルギーがない。親の「よかれと思って」は、子どもにとっては逆に迷惑で、足を引っ張ることにもなりかねないんじゃないかなぁと、私は思います。
――その後、大学院にも進まれて。
大学院で、院生としての制作活動とイラストレーターの仕事の二足のわらじでやっていました。仕事がひとつできると、また次の仕事につながっていったので、「フリーランスで絵の仕事をしよう」って決めました。でもまあ、母はがっかりしていました。心配だったんでしょうね。何度も何度も「こっちの方がいいよ」「こっちの道がいいよ」って言ってるのに、私はまったく違う方に行くっていう。大学院の頃に結婚したときも、「仕事が軌道に乗ってからの方が……」とか、言われましたしね。

同級生の夫は
頼りになるプロデューサー
――ちなみにご主人とは、大学でご一緒だったんですか。
はい、学生時代の同期です。私は油絵科、彼は芸術学科で。夫が当時「留学するから結婚しよう」って言って結婚したんですが、結局留学しなかった(笑)。
――なるほど、同じジャンルの人なんですね。
そうです。ただ描く人ではなくて、大学で西洋美術史を教えています。プロデュース能力が高いというか、私も結構絵の相談をしたり、いっぱい助けられてます。
ある日、やきそばを描いていた私は、加熱した豚肉がどうしてもおいしそうに描けなくて。色鉛筆でベージュを3種類ぐらい重ねて描いても、うまくいかなくて。「私、加熱した豚肉がおいしそうに描けないんだよね」って言ったら、夫が瞬時に「豚肉には紫が入ってると思うよ」って言ったのね。「それだ!」と思って。早速淡いパステルトーンの紫の色鉛筆を取って、下地に乗せて、その上からベージュを乗せたら、もうそれはそれはおいしそうな豚肉になって。「ああ、これだったんだなあ」って。
――言語化できるわけですね。
そうなの、『わすれていいから』のときも、私は枠の意識が強すぎるのか、広がりのない絵になっちゃってたんですね。そのときに、「枠は忘れて、とりあえず猫や人物やソファーや全部のモチーフをそれぞれハサミで切って、紙の上に乗せて配置してみてから、それを本描きしたらどう?」って、ナイスアイディアをくれたのも彼です。随所随所で、名プロデューサーです。
やらせたくなかったはずの
ゲームに母も大ハマり
――お子さんたちご兄弟は、何歳違いですか。
4歳違いです。ふたりとも男の子で、大学生と高校生です。
そういえば私、子どもたちが小さい頃、ゲームはさせたくないと思っていたんですね、最初は。でも長男が小学3年生くらいになると、まわりはみんなDSとか持っていて、「ほしいなあ」って言われて。どうしたもんかなあって。ずうっとゲームばかりやっちゃうんじゃないかって、心配だったんです。
でも、どこかで聞いた話で、19世紀かな、ヨーロッパのどこかで「砂場」っていうのを初めて作ったら、子どもたちがすごい夢中になっちゃって。で、当時の大人たちは「こんなにずうっと砂遊びばっかりやってたら、バカになるんじゃないか」って心配したんだって(笑)。笑っちゃうでしょ。それを知ったらなんか、バカバカしくなっちゃって。それでゲームを買いました。
そうしたら、面白いんだな、これが。当時『どうぶつの森』を長男が大喜びでやってて、母さんのアカウントも作ってくれたんですよ。で、やってみたら、めっちゃハマりまして。
――親子で『どうぶつの森』にハマッた(笑)。
そうそう。「うわ、これ面白!」って。どうぶつの森の中では夜にキャンプとかしてて、誰かがギターを弾いたり、お酒とかお茶とか飲んだり。ふと見上げた星空が美しすぎて、私感動しちゃって。「なんてステキな世界なんだ!」って。今まであんな頑なに拒絶してたけど、「なんかいいよねえ」みたいになっちゃって(笑)。
――お母さんも夢中になるとは。
ねえ(笑)。でね、長男も次男もゲームがすごい好き。長男は高校ぐらいのときから自分でプログラミングをするのが好きで、もう、目をキラキラさせて。今は大学卒業後に、プログラマーの道に進もうとしています。
次男もすごくゲームがうまくって、格好いいんですよ。長男と次男とで組んでプレイすると、次男はスナイパーで、自らガーッて行くタイプで、長男はその絶妙なサポートをする役回りらしく。バレーボールで例えると、次男アタッカー、長男セッターみたいな。そういうのを聞くと、あ、みんなこうやってeスポーツを楽しんでるんだなあって、熱くなる感じがわかる気がする。世界中が熱狂する理由が。
『テトリス』とかも、次男が超うまくって。「難易度的にこれくらいなら母さんでもできるかな」みたいなゲームを勧めてくるんですよ。「ちょっとやってみな」とか言われてやってみると、私、本当にああいう図形のパズルがまったくダメで。手詰まりになって画面がどんどん埋まって、「もう終わった」って思った瞬間に、私の手から次男がパッてSwitchを取って、ダダダダダッてやると、ワーッて消えるの。「え、なに? すごい!」って。尊敬する。そうしたら、「どんな状況でも、いつだって次の手を考えろ、あきらめんな」みたいなことを言ってて。
――かっこいい!
ねえ。なかなかできないけど、でもそのスピリットは学びたいと思います。ゲーム、面白いですよね。いっぱい教えてもらうことがあって、深いです。次男がちょいちょい持ってくる簡単なゲームを一生懸命やってます(笑)。
――それはうれしいですね。親子のいいコミュニケーションになりますね。
長男や次男がやっているゲームの世界は、もっと複雑で繊細でクリエイティブだと思います。でもちょっとだけ触れられるというか。触れているつもりだけかもしれないけど。面白いです。

2歳から20歳までの大森さんの作品が丁寧にまとめられたアルバム。
後編はこちら「絵本作家・大森裕子さんロングインタビュー。自分で勝手に義務にして、自分で勝手に怒ってた」
INFORMATION
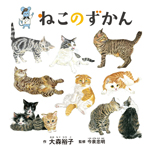
『ねこのずかん』
大森裕子/作 今泉忠明/監修
白泉社 1100円
猫の種類、生態から「猫語」「猫と仲良くなるには?」まで、無類の猫好きの作者が贈る、猫のすべて。大人気の「コドモエずかん」シリーズ第3作。
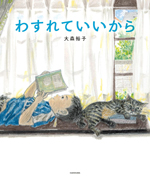
『わすれていいから』
大森裕子/作
KADOKAWA 1650円
人間の「おまえ」と猫の「おれ」。作者の息子たちと猫の「トム」をモデルに、男の子の成長と巣立ちを、いつも傍で優しく見守る猫の目線で描く。
インタビュー/原陽子 撮影/黒澤義教(kodomoe2025年4月号掲載)







KV修正-350x350.jpg)