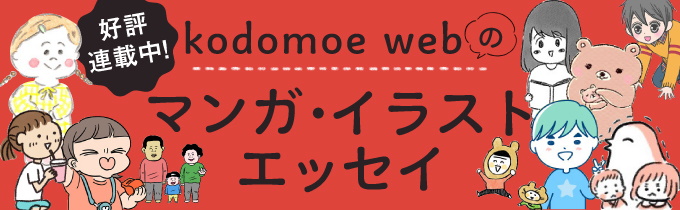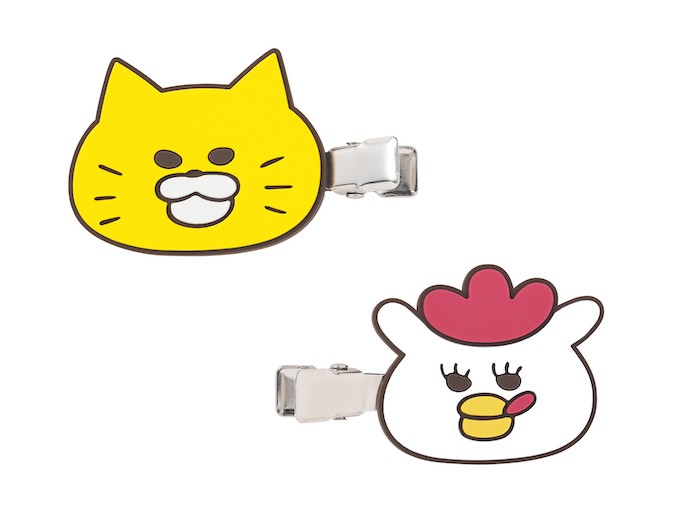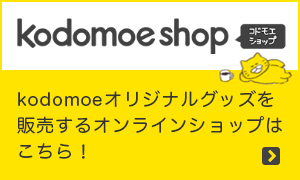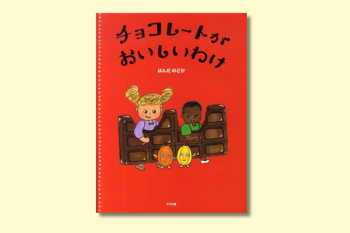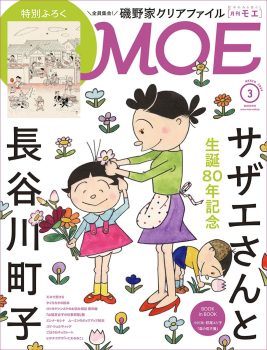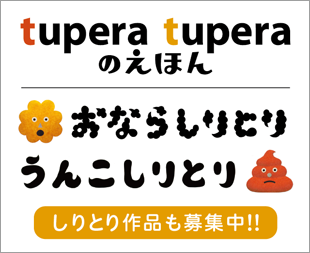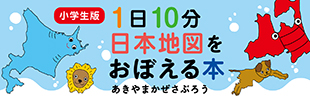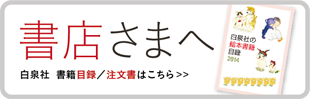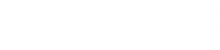作家・金原ひとみさんロングインタビュー。娘とは言葉で話し合える関係性を保っていきたい【後編】
2004年にデビュー作『蛇にピアス』で芥川賞を受賞した金原ひとみさん。人間が抱える根源的な孤独感や、やり場のない心情を繊細かつ生々しく描いて話題をさらいました。それから20年、今でも文壇の顔のひとりとして精力的に作品を発表し続けています。一方、プライベートでは2人の娘の母親としての一面も。育児と執筆の両立は「壮絶だった」と語ります。その真意とは。kodomoe2月号のロングインタビューを全編公開。後編をお届けします。
ロングインタビュー前編「小説を書くことが一番自分を救う行為。現実とフィクション、両方あるから生きていける」はこちら
かねはらひとみ/1983年、東京生まれ。2003年に『蛇にピアス』ですばる文学賞を受賞し、デビュー。翌年同作で芥川賞を受賞。2010年『TRIP TRAP』で織田作之助賞、2012年『マザーズ』でBunkamuraドゥマゴ文学賞、2020年『アタラクシア』で渡辺淳一文学賞、2021年『アンソーシャル ディスタンス』で谷崎潤一郎賞、2022年『ミーツ・ザ・ワールド』で柴田錬三郎賞を受賞。
保育サービスが充実しているフランスでの子育て
――金原さんは2012年から6年間、パリで過ごされていました。育児や母親に対する認識で日本とのギャップはありましたか?
パリは日本よりも、女性が社会的な存在として認識されているように感じました。だからか、「お母さん扱い」みたいなものは日本ほどされませんでした。制度が整っていることの差でもあったと思います。フランスでも保育園不足という問題はありますが、認定保育ママの自宅で子どもを預かってくれる制度があったり、保育ママやベビーシッターを雇用した親に対して「保育方法自由選択補足手当」が支給されるなど、保育サービスを安く利用できるシステムがあるんです。それに働いているか否かに関係なく、無条件で短時間から子どもを預かってもらえる「ギャルドリー」という託児施設もあります。保育サービスが多様で、選択肢が豊富。そしてその制度が使いやすいことにも感心しました。
――安いのはもちろん、預けるのに理由を聞かれないのはいいですね。母子密着が強い日本は子どもを預けるにも理由が必要で、「予定がないのに子どもを預けるなんてかわいそう」という思考が根強いように感じます。
日本は働いている女親への軽蔑がいまだにありますよね。預けたいのはあなたの都合でしょ、みたいな。でもフランスでは、子どもを預けることに対し、みんな罪悪感を持っていないんじゃないかな。制度が充実しているおかげか、お母さんたちもすごくのんびりしていました。私が仕事をしなきゃとキリキリしていることが恥ずかしくなるぐらい、フランスの人たちは悠々と子どもと向き合ってる気がします。一度、子どもを小学校に送りに行った際に、ガルディエンヌ(門番)に「今日はストライキで先生がいないから学校はお休み」と言われて追い返されたことがあったんです。私は〆切も迫っていたのですごくイライラしてしまい、子どもに対しても「仕事をしなきゃいけないから、本当悪いんだけど静かにしていてね」とピリッとした感じの態度を取ってしまったんです。でもそのあとに友達のお母さんに会ったら、彼女は「やったね、今日はママと過ごせるんだね。ラッキーじゃない」ということを子どもに言ってくれて。しょぼんとしていた子どもが、ちょっとキラキラし始めたんです。そうか、この日を楽しいものにしてあげなくてはと思い、その後子どもとカフェに行きました。その時、なんで自分はこんなにいつもピリピリしているのだろうと情けなくて泣けてきました。
――ストライキへの寛容さ含め、フランスはシティズンシップ教育がしっかりされている。そこにも日本との差を感じます。
労働者の権利ですもんね。市民としての権利を認め、みんな市民として社会に積極的に参加する姿勢はすごく重要なことだと思います。それを学んでいるからか、何かが起こった時に柔軟に対応できる心の余裕がある人が多いことにもびっくりしました。
――子どもに対する街の人々の寛容度はいかがでしょう。
日本にいると子どもに関わる人は親、実家、保育園ぐらいですが、パリは街全体がわりと子どもを許容しているような感じがしました。それこそベビーカーを使っていると当たり前に手伝ってくれたり、気を遣ってくれたりする人が多い。先へどうぞと譲ってもらったりとか。頼っていいんだなと気持ちが楽になった経験が何度もあります。もちろん意地悪な人は一定数いましたが。
言葉で話し合える関係性を
娘と保っていきたい

――近年、「母娘小説」に注目が集まっているように感じます。著書『腹を空かせた勇者ども』はご自身とご息女との普段の関係性が影響した作品だと想像しているのですが、「娘」であり「母」でもある金原さんは母娘の関係をどう捉えていますか?
私は自分の母親とは良好な関係を築けないままでいて、話をすることを諦めて久しいです。母は子どもを抑圧する人で、私が20歳ぐらいの時に、決定的に断絶をしました。なので、そこからはもう気持ちが楽になりました。わかり合う、共感し合うことを一切求めずに、別の生き物だと思うことで今は割り切っています。反面教師的に、私は何かあった時に言葉で話し合える関係性を娘と保っていきたいと思っています。例えば頭ごなしに何かを押し付けるのではなく、どうしたいのか意見を聞く。ちょっとラフな感じで友達のように接しながら、必要な時には助ける。今のところは何かがあった時にはすぐに相談をしてくれるので、関係はうまくいってるのかなと思っています。やはり自分がされて嫌だったことをしないように心がけてますね。
――そこにある決定的な差は、対話でしょうか。
そうですね。あと相手が嫌だと思ったことを強要しないこと。相手がしたいって思ってることを咎めないこと。相手の意思を尊重するということは、育児に限らず人間関係において大事なことだと思います。
――子育てに関する本は読まれたりしましたか?
ちょっと偏っているんですけど、妊娠中に内田春菊さんの『私たちは繁殖している』をずっと読んでいて、それで育児の全部を勉強したところがあります。家族という既成概念から外れたところにある家庭の物語なので、風通しよく感じられたこともよかったです。あと子どもが中耳炎になる描写を読んでいたので、子どもの中耳炎にはすぐに気づけました(笑)。
――金原さんはどのような家族観をお持ちですか?
みんなが幸せに暮らせればいいんじゃないかな。家族といっても、それぞれ個人の関係だと思っています。一つのコミュニティとしてとらえるのではなくて、ひとりひとりを個人として尊重したい。だから家訓のようなルールで縛りたくないし、話し合いでちゃんとお互いの気持ちを伝えられる関係であれば、どんな形でもいいんじゃないかなと思います。
――家族という単位を意識することはありますか?
ないですね。ただ、私と娘の関係でいうと、育ててきた自負みたいなものが個別に出てきてしまうことも。そういうのをできるだけ出さないようにしないといけないですね。
――家族像は今や多様なのに、現実社会はいまだに伝統的家族観を押し付けてきます。それでも金原さんの小説の主人公はそんな世界をうまくサバイブしている感じがあります。
私もそうなんですけど、自分の特性や傾向を掴めてきたことが大きいです。昔はいちいち社会と自己との差に傷ついたり疲れたりしていましたが、世の中のことや自分自身のことがわかってくると、対処のしようがある。ただそれだと自衛に走りすぎて刺激もなくなってくるので、最近はちょっと人付き合いを広げていこうとか、新しいことに挑戦してみようという方向にシフトしてます。
――すごい変化ですね!
昔は自分を守ることで精一杯でしたが、この十年くらいは人に目を向けられるようになってきました。自分の精神衛生的にも人と話す、共有することがいい具合に作用してきた気がします。
――以前、子育てについて「圧倒的な他者との暮らし」と語っていたと思うのですが、人に目を向けられるようになったのはご息女との暮らしを通しての変化でもあるのでしょうか。
そうですね。やはりそもそも子育てって完全に閉じた状態ではできないじゃないですか。だから当時の私にはそれ自体がすごく苦しかった部分ではあるんですけど、今ここまで子どもが育ってみると、新しい世界に通じて見えてくることもあって、すごく刺激的ですね。あと、外に対して自分自身が開けてきたのはフランスに行ったことも影響していると思います。自分と全然違う考え方の人や、これまでは敬遠してたような人たちとも付き合わなくてはいけない環境に強制的に身を置いたことで、割り切ってしまえば意外と平気だな、と気づきを得られました。いろんな人から影響を受けて、自分も変化してきたんでしょうね。

生きづらさを書くことで
人生を回していく
――金原さんにとって「書く」という行為は生業以外にどんな意味を持ちますか?
出産後、第一子の時は特に自分の時間が取れなくて執筆できなかったことがストレスになっていました。その時、私は書かないと生きていけないんだって実感したんですよね。特に育児中は憤りやつらさなどをビリビリと感じていたのに、それを表現する場所と時間がないということがすごく苦しかった。今まで何かあった時に、書くことでしか自分の中で理解できなかったことはたくさんあるし、日常の中で過ぎ去ってしまうようなことでも、自分がここに引っかかっていたんだ、傷ついていたんだ、ではなぜそれが生じたんだろう、と書くことで考えていたんです。それができなくなると、どんどん現実の方が狂っていってしまう感覚がありました。私は小説世界と現実社会の両方に足をかけて、その両輪で生きているんですよ。もはや私の人生とフィクションは切っても切り離せないものになっています。「書く」ことはもはや人生の一部というか、半分ですね。だからこそバランス感覚は大事になってきます。面白いことに、フィクションがうまくいっていない時は現実もうまくいかないし、現実がうまくいかない時はフィクションで調整しないと余計にボロボロになってしまう。どちらかだけではバランスが悪すぎるので、両方を必死に回しながら生きていかないといけないなと感じています。
――つらい物語を書いている時は現実が物語のつらさに引っ張られたりしませんか?
いや、逆に良くなるんですよ。たぶん現実のつらさを小説で昇華させているから、現実の苦しみがもう全然平気に感じてくるのかもしれません。
――もはやライフハックですね!
ある意味、書くことを利用しているんです。両方があることで、暮らしが成立している気がします。
INFORMATION

『ナチュラルボーンチキン』
金原ひとみ/著
河出書房新社 1760円
ルーティン生活を愛する45歳事務職の浜野文乃は、同じ会社で働く「パリピ」編集者の平木直理の見舞いに行ったことがきっかけで、忘れかけていた「本当の私」に出会い直す。
インタビュー/綿貫大介 撮影/馬場わかな(kodomoe2025年2月号掲載)







KV修正-350x350.jpg)