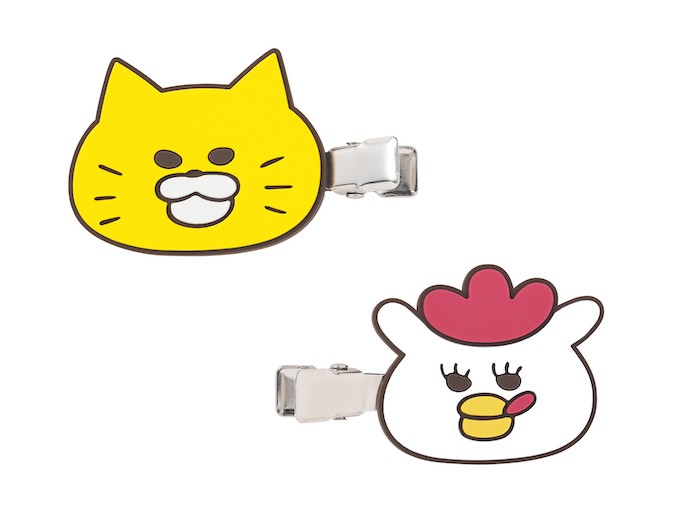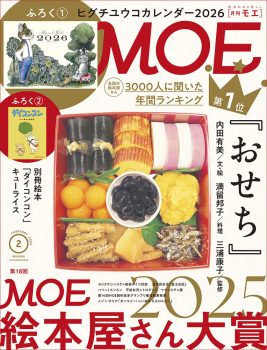社会学者・上野千鶴子さんロングインタビュー。世間知らずの「深窓のガキ」が進学校に進むまで【前編】

地域を応援しよう! 家族で楽しむふるさと納税
日本における女性学のパイオニア的存在である、上野千鶴子さん。『あなたたちのがんばりを、どうぞ自分が勝ち抜くためだけに使わないでください』と述べた、東京大学入学式(2019年)の祝辞が話題に。kodomoe2020年6月号で、ご自身のご両親との関係についてなどたっぷり語ってもらったロングインタビューを、kodomoe webで全編公開いたします。
前編では、「地域社会にお友達もいない世間知らずの『深窓のガキ』だった」と語る幼少期から、本ばかり読んでいたという中学時代、そして金沢の進学校に進む高校時代のお話をご紹介します。
うえのちづこ/1948年、富山県生まれ。社会学者。認定NPO法人ウィメンズアクションネットワーク理事長。東京大学名誉教授。日本における女性学、ジェンダー研究の第一人者。デビュー作は『セクシィ・ギャルの大研究』(岩波書店)。近刊に漫画家・田房永子さんとの共著『上野先生、フェミニズムについてゼロから教えてください!』(大和書房)、『介護保険が危ない!』(岩波書店)がある。
北陸の大家族
溺愛された「深窓のガキ」
日本のフェミニズムを牽引して40年。今も先頭で風を切る上野さんは、1948年7月、富山に生まれた団塊世代。開業医の父に専業主婦の母、5つ上の兄に2つ下の弟、そして父方の祖母の6人家族の中で愛されて育った。

――よく、「フェミニストになるのにはもってこいの環境だった」とおっしゃっています。
当時の普通の娘たちは、早い時期から我慢することを教えられたんです。兄弟に対して控え目になるとか。でも、私は好き放題、天井知らずに育ちました。といっても、子どもだから囲い込まれています。生まれたのは、父が疎開していた上市町(富山県)、その後に戻った富山市の家はお庭がすごく広くて、塀の中でも十分遊べた。次の家も150坪、それから金沢の90坪。段々ちいちゃくなったけれど、塀の中だけで遊んでました。地域社会にお友達もいない世間知らずの「深窓のガキ」だった。
父は妹ふたりの3人きょうだいの長男で、家の重しがずっしりのしかかっていて。その母親は、気が強くて早い時期に夫を失くして後家楽の一家のゴッドマザー。両親は大正元年生まれの同い年で、祖母にとっては息子が勝手に恋愛して連れてきた嫁だから、意に添わない。母は不満をためながらも「北陸の嫁」をやっていました。
妻と姑がうまくいかないのはザラにあることで、対立があると夫は母につくという普通のマザコン夫。小さなときから、三世代同居の中で人間関係をずっと見てきました。
――先日、NHKの「グレーテルのかまど」で母の味として焼きりんごを紹介されていました。当時、オーブンがあった家は珍しい。
そのままガスの火の上にのせる旧式のオーブンがありました。その前には天火鍋といって、ドーナツのような穴が空いてそこにケーキ種を流し込んで焼く厚い鉄鍋もあって、母はそれで毎年クリスマスケーキを焼いていました。
――そういう家だったんですね。
両親がクリスチャンでしたから。母は器用で何でもできる人で、編み物もできたし、洋服も作ってくれた。料理も上手でした。食卓にはサラダとか当時としてはハイカラなものが出てましたね。母はそうした暮らしを教会で覚えたんだと思う。私を送り込んだのも、富山のミッション系の名門幼稚園でしたから。
――日本舞踊も習っていたそうですが、どなたの趣味ですか。
父の趣味です。私たちの世代は、娘に稽古事をさせるのに「ピアノとバレエ」という組み合わせか、「お茶と日本舞踊」という組み合わせのどちらか。
私の父は「女の子は人前で足を上げるもんではない」と言う男だったから(笑)。自転車も「危ない」と言われ、乗せてもらえなかった。
――お父さんは人前で足を上げることのない妻を選んだわけですか。
そのつもりだったらしいわね(笑)。結婚するにあたって父は母の名前を変えさせたの。久子から静子に。「静さん」と呼んで、彼の女に対するファンタジーを妻にも押し付けていた。
でも、35年仕えた姑が死んでから、母はハジけたのよ。ものすごく活発で、発展家で、「あ、こんな人だったの?」と思ったもの。
父も急に母に気を使うようになりました。母は「私はこのままでは死ねない」と父に反抗し、写経して仏教徒として死にました。
――うーん。千鶴子という名前もお父さんの思い入れが強そうです。
本当は私は真理子になるはずだったの。兄と弟の名前はふたりとも聖書から取られてるから、私も「真理の子」に。
ところが、両親が仲良くしている教会友達のカップルが同じ時期に妊娠し、私より1週間早く出産してその娘に真理子とつけてしまった。で、急遽、千鶴子になりました。
クラシックなのが好きなんでしょう。父が「シズさん」と呼ぶと「チヅさん」て聞こえるからドキッとしてた。紛らわしい名前つけんなよって。
「子どもさえいなければ」
母の愚痴を聞いて育つ

――どんな子どもでした?
すごく繊細な子どもでした。お魚が泳いでいるのを見ると魚が食べられなくなり、お肉屋さんで枝肉がぶら下がっているのを見たらお肉が食べられなくなって、極端な偏食児童だった。母が偏食を直そうとカレーの肉をミンチにしても、そのミンチを全部取り除いてたもの。食べてたのは卵と蒲鉾と海苔。
兄に「海苔ばかり食べてたから色が黒くなったんだよ」とからかわれてました。お弁当の定番が煮カツだったのね。知ってる? トンカツを揚げてそれをお出汁で煮て卵でとじる。兄は「煮カツだ!」と大喜びしていたけど、私は「お肉抜いて」。出汁の染みた衣がおいしかったぁ。
一番苦労したのは給食でした。油っぽいお肉なんて食べられない。当時は過酷な教育で、残すと先生が目の前に子どもを置いて食べ終わるまで監視するの。私が食べ終わった途端吐いたら、それから何も言われなくなったけど。
――身体で反抗してたんだ(笑)、神経質だったんですね。
父親がそうだったし、またそうしたことが通る家庭だったからね。とんでもない子どもよ。育てにくかったと思う。
――お祖母さんとの関係は?
どんなに嫁との関係がよくなくても、孫はかわいがってくれる。家が家だからいただきものが山のようにあって、その裁量権は祖母が握っていた。一番いいのを確保して、実の娘たちに分け与えてたのが、私の母にすれば気に入らない。当時は出産するときに小姑たちは実家に帰ってきて、その世話を引き受けるのが長男の嫁の役割でした。
でも、かわいがってもらった私に祖母への恨みはない。気は強かったけれど、快活で社交的な人だったからね。早めに夫を亡くして、息子をマザコンに仕立てておいてコントロールするのが女の上がり。家父長制はちゃんと上がりを用意することで、女に報酬を払っているんだとわかりました。
――その上がりに憧れることはなかった。
その下に嫁の忍従があるのを見てますから。三世代家族で小姑が出入りし、住み込みのお手伝いさんも看護師さんもいたという複雑な人間関係を見てる。そこは核家族で育ってきた人とは違います。
――お祖母さんもクリスチャン?
北陸は真宗がものすごく強いところで、祖母は敬虔なる真宗門徒。別院にお参りに行ったり、仏教婦人会に行くのが楽しみで、孫を連れて行ってくれる。だから私は教会の日曜学校にも、お寺詣りにも両方行きました。大正モダニストの父は土着のコミュニティが嫌でしょうがないから、クリスチャンになったのよ。あの北陸の泥沼から抜け出したいと思ったんでしょう。
父は人づきあいが悪く狷介孤独(けんかいこどく)な男で、しかも酒煙草はやらない。若いときは賀川豊彦に憧れる理想家肌で、臨床医ではなく研究医になりたかったという人でした。ルソーの『エミール』(近代教育学の古典)を「抱いて寝た」と言ってたので、私、読んだの。そうしたら最後に、「以上述べてきたことは男にしか当てはまらない。女の役割は男を支えることだ」と書いてあって、おいおいと(笑)。仰天しました。
――ルソーもまさか上野さんに読まれるとは(笑)。しかし、お父さん、教養人です。
ふるまいは完全に家父長的だけれど、モダニストのふりをしたかったのね。だから食卓のキーワードは「団欒」だった。「さあ、みんなで団欒しよう。チコちゃん、今日学校で何があったか言ってごらん」。だから私は、「団欒っちゅうのは抑圧的なもんやなぁ」と思って大きくなりました。あとで明治の文献を読んでいたら、「団欒」は明治の新思潮だったことがわかった。
――その団欒にお母さんも加わってたのでしょうか。
あの時代、食事の差配は嫁の役目だったの。6人の食卓だし、母はこまねずみのように立ち働いていました。子どもたちもおかわりのときには当然のようにお茶碗を差し出してた。酷い世の中でしたね。それが母親の役割でしたからね。
――子どもの上野さんの目にはお母さんが不幸に見えました?
当たり前ですよ。だって母は葛藤してたもん。気の強い姑とわがままで癇癪持ちの夫に仕えて、夫婦喧嘩は日常茶飯事。そして、子どもに「あんたたちさえいなければ離婚できるのに」と愚痴る。日本の多くの母親と同じ。だから日本の普通の、最低の母でした。
ただ私の母は、毒母のように子どもへの過干渉や支配はしなかった。信田さよ子さんによれば、毒母は圧倒的に団塊世代なんです。一旦男女共学の中で平等の夢を見せられたのに、建前と現実のギャップが大きすぎて、エネルギーの捌け口が子どもに向かって毒母になる。その前の私の母の世代にどうして毒母があまりいないんだろう、と考えてみたら、家父長制の重圧があまりにも強く、子どもへ過干渉する余裕がなかったんでしょう。

2019年、東京大学の入学式で祝辞を述べた上野さん。東大生による性暴力や、東京医科大学の性差別入試事件、そして社会における不平等を明らかにし、話題に。その際の写真をパネルにして事務所に飾っている
ミソジニーを抱えた
不機嫌な女の子
学校と家の中だけが生活圏だった少女の頃の上野さんは、犬と本が友達だった。小さなときからきょうだいの中でもずば抜けて成績がよく、「体育と音楽以外オール5」。中学も高校も、一人娘を溺愛する父の選択だった。
――どんな本がお好きでしたか。
教会の日曜学校に行くと、本が山のようにありました。「岩波の子どもの本」という絵本シリーズを与えられた。バージニア・リー・バートンの『ちいさいおうち』は今でも大好きな絵本。あと、父が偉人伝を買ってきて、その中に『キュリー夫人』があった。いかにも、でしょう。
――私も父に買ってもらいました(笑)。「勉強しろ」とは?
逆なの。中学のときに本ばかり、しかも布団の中で読んでたから目が悪くなったの。女の子は眼鏡をかけちゃダメって時代で、父親は私が勉強していると、30センチの竹の物差しを私と本の間に置いて、「これだけ離して読みなさい」(笑)。
それから「30分読んだらやめなさい」「そんなに一所懸命勉強しなくてもいい」って。父は「女のくせに」と言ったことはないけど、兄と弟には医者へのレールを厳しく敷いていたから、「ああ、違うんだ。私はペットなんだ」と思ってました。子どもを侮っちゃいけません、そんなことぐらいわかりますよ。
――お父さん似とか。
そうね。顔もそっくりだったから。私は「活発なお嬢さんね」と言われて、トムボーイでチビでこましゃくれていて、色の黒い子だったけれども、母に似た弟は色白で、大人しくていい子。ずっと「逆だったらいいのに」と言われてた。
――高校は、金沢の進学校。そこには「飛び抜けて頭がよく、新聞部で活動していて弁が立った」という上野伝説が残っていますが。
「お嫁にもらうならここ」と言われていた旧制の第一高女が前身で、男女半々。男女が半々だと圧倒的に女が強くて、楽しかったよぉ〜。でも、将来の夢なんてものはありませんでしたね。ひねくれてたから、中学のときは考古学者になりたいと思ってた。父の職業を見てて「医者はつまらん商売やな」、「食いっぱぐれのない人生はつまらんもんや」と思って、世間の役に立たない人になりたかった。
――醒めてましたねえ。
第三者には「あんないいご家庭に育って、何のご不満が」と言われても、AC(アダルトチルドレン)といえばACだったし、一種の被虐待児だったと思う。家庭内の葛藤に傷ついていました。
兄も弟も母の不遇を見てたからマザコンに育ったけれど、やっぱり、娘のほうが息子より傷つくよね。母が不満を漏らすと、「それなら、そこから脱すればいいじゃない」と思うのに、母は脱しようとはせずに「お前たちのせいで」と言う。
息子と違って娘は、そういう母の非力さを見るのもつらいし、自分を待ち受けている将来が母のような人生だと感じて絶望する。母は完全に「こうはなりたくない」というカウンターモデルだったから、女であることを受け入れるのがものすごく辛いミソジニー(女性嫌悪)を抱えてました。
――親子喧嘩も激しかった?
喧嘩にはならない、私が言うことを聞かないの。父の言うことも母の言うことも聞かない、気難しい娘になった。私がそれまで「パパ」と呼んでいた父を13歳のときに「オヤジ」と呼んだら、顔色が変わった。それ以来、父は不機嫌な娘を腫れ物に触るように扱うようになり、私はそこにつけこんだ。そして母はそれを疎ましい思いで見てた。
インタビューは後編へと続きます。
インタビュー/島﨑 今日子 撮影/馬場わかな(kodomoe2020年6月号掲載)