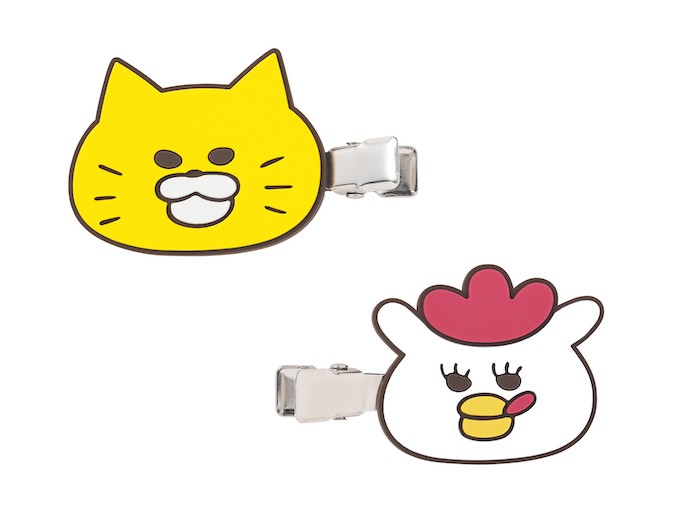お笑い芸人・Aマッソ加納愛子さんロングインタビュー。おもろくて機嫌がいいやつはいろいろダメなところがあっても最強【後編】
お笑いコンビ、Aマッソの「頭脳」としてお笑いファンの支持を集める一方、新進気鋭の文筆家として文芸界でも話題をかっさらっている、加納愛子さん。kodomoe6月号のロングインタビューでは、特異な言語センスで紡ぎ出される、過激でチャーミング、不思議な人間味にあふれた加納ワールドの原点を探るべく、「家族」と「笑い」について語ってもらいました。
kodomoe webでは、本誌の貴重なインタビューを全編公開。後編では、高校時代のお話や昨年作家デビューした小説についてなどをおうかがいします。
Aマッソ加納愛子さんロングインタビューの、前編はこちら
かのうあいこ/1989年生まれ。2010年に幼馴染の村上愛とお笑いコンビ「Aマッソ」を結成。主にツッコミとネタ作りを担当。特異な視点と言語センスによる笑いで「女性芸人」の枠を超えて広く支持を集める。近年は作家・エッセイストとしても活躍。エッセイ集『イルカも泳ぐわい。』(筑摩書房)、小説集『これはちゃうか』(河出書房新社)などの作品で、文芸界に新風を吹き込んでいる。

異性の視線がない分
「女子校はボケ放題」
――子ども時代のお話を伺っていると、大らかで風通しのいい、笑いに満ちた環境に好奇心の種がいっぱい蒔かれていて、のびのびと興味の枝葉を広げていかれた様子が目に見えるようです。ご両親の教育方針としては、やはり放任主義的な感じ?
そうですね。ガッツリ門限があった記憶もないし、勉強しろと言われた記憶もない。勉強しろと言うよりは、親父の友達と一緒で「そんなんも知らんの?」と煽ってくる感じ(笑)。まあ、言ってること自体は、同じ「勉強しろ」なんですけど、焚きつけ方が違う感じで。強制はしない分、自分でちゃんと考えろみたいなことやったんでしょうね。「そんなんも知らんの?」だけやとムカついて終わってたかもしれないですけど、同時に「おお、よう知ってるやんけ!」みたいなのもあったんで、私自身、勉強したり、何かしら知識を入れたりすることに対しては常に前向きでしたね。
――子どもの自主性を育む方法として、大いに見習いたいです。じゃあ、いわゆる反抗期も特にはなかったんですか?
いやぁ、ほとんどなかったんじゃないですかねぇ。私の興味の対象が、繁華街で夜中まで遊んでるとか、煙草を吸ってみる、みたいな方には行かなかったからかもしれませんが、バトることもほとんどなかったし。親がウザいみたいなのも、そもそもベタベタしてないし、あんまり寄りかかられてなかったので記憶にない。本当にのびのびと好きにさせてもらってましたね。
――ものを作る人は思春期の鬱屈が糧になっている人も多いですが、加納さんの場合はそういうものとも無縁そうですね。
そうですね。自分が変わってるとか思ったこともなかったし、歪んだ記憶もないです。
――Aマッソは結成当初から、性別関係なくネタのおもしろさで勝負するスタンスを貫いていて、近年はフェミニズムやシスターフッドへの共鳴もさまざまな形で発信されています。子どもの頃は、女性であることに息苦しさを感じることはありませんでしたか?
ありませんでしたね。親父はもちろん、おかんもそういうタイプじゃなかったし、抑圧みたいなのはマジでなかった。高校も女子校やったんで、ボケ放題でした。
――女子校はボケ放題は名言です。
異性の視線に晒されることもなかったから、変な競争も抑圧もなく、のびのび過ごせたんでしょうね。だから共学行ってたら、もしかしたら違ってたかなというのは、すごく思います。もしかしたら無意識に女子高を選んでたのかもしれない。村上も別の高校でしたけど、ほぼほぼ女子高みたいな学校やったし。芸人になってからも、先輩の世代は女芸人に対して当たりも強かったと思うんですけど、私らはとにかく自分らのネタを作ることに必死やったこともあって、悔しい思いをしたこともほとんどない。そういう意味では、意外と温室育ちです(笑)。
――高校ではどんな感じで過ごしていたんでしょう。
世話焼きとかではないけど、わりと先生にクラス内のパワーバランスについて相談されたりしてましたね。ひとりでいるような子がいたら、この子はどうやったら笑うんやろ?みたいなことが気になるタチで。よく三者面談とかで「ちょっと最近あそこらへん不穏やんな」「あの子もなあ、なんかしゃべった方がいいと思うけど」「いや、あの子はほんまひとりがええから放っといてって」「ほんまか!?」みたいなことを先生とずっとしゃべってて。三者面談はいっつも最後で、めっちゃ長かったです。
――進路はすんなり決まったんですか?
高校で映画が好きになって、詳しくはないんですけど、おもろそうやし映画に携わる仕事したいなあと思って。映画サークルとか学祭とか楽しそうやから、同志社大学か立命館大学に行きたいと思ってました。でも、親からは学費が安いから市大(大阪市立大学)行けと言われて。進路を決める三者面談では、なぜか親父が「俺が行くから」って来て、先生の前で「授業料高いやんけ、市大行けや」「嫌や」みたいな感じで、3時間ぐらい延々と揉めました。
――これまたコントのようです。
「高いやんけ」とか言うのがおもろいと思って言ってるのが、タチが悪いなーって(笑)。
――結局、高校卒業後は同志社大学の商学部に進まれました。大学生活はどうでしたか?
映画サークルに入って、楽しかったですね。自分で脚本を書いて映画を作ってたんで、将来は映画の脚本とかやりたいなと思ってたんですけど、たまたまコント映像みたいなのを撮ったときに、すごいしっくりきて。大学2年のときに村上を誘って、インディーズライブに出始めました。
その映画サークルは、映像監督になった人もいるし、役者になった人もいるし、お笑いやってる喜劇サークルとも仲が良くて、芸人を目指してる人もいたんで、自分の中で映画とお笑いがそこまでかけ離れたものではなかったんです。だから大学時代は映画とお笑い、両方をやってて、学費のためにバイトもしてたんで、授業はほとんど出てませんでしたね。1年で2単位とかしか取れてなかったんで、もう絶対に卒業できへん感じになって。推薦で大学に入ったので、高校には申し訳なかったけど、結局大学は辞めちゃいましたね。
――じゃあ、もうお笑いの道で行こうと?
いや、この瞬間に腹を括ったみたいな感じはなかったですね。ただ、自分が普通に就職して会社員になるとかいうイメージもまったくなかったし、脚本家か映画監督か芸人になれたらええなぁみたいなうっすらした感じで。将来の不安みたいなのも特にはなく、目の前のやりたいことしか考えてませんでした。
――ライブを始めてほどなく事務所の目に留まり、松竹芸能タレントスクールに特待生として入り、2010年にはAマッソとしてデビューします。本格的に芸人の道に進むことが決まったとき、ご両親はどういう反応でしたか?
親父は「好きなことやったら?」みたいな感じでしたね。おかんは後から聞いたら本当は物書きになって欲しかったみたいで、お笑いはピンと来てなかったっぽいですけど「まあ、がんばり」みたいな感じで。反対は一切されませんでしたね。
小説に挑戦できた
岸本佐知子さんとの出会い

――加納さんは2018年からエッセイの執筆を始めて、昨年に短編小説集『これはちゃうか』で作家デビューされました。お母さんの思惑もまんざら外れてませんね。
小説は声をかけてもらって、最初は無理やり書いてた感じでしたね。ずっとネタを書いてきたから、どうしても台詞ばっかりで情景描写が書けない。だから「なんかすごいしゃべってる小説だね」って言われるんですけど(笑)、私自身がこれまで小説を読んでて「話はおもろいねんけど、台詞がいまいち嘘っぽいな」と思うこともあったんで、自分が文芸というジャンルの中で勝負できるとしたら、上っ面でないしゃべりのおもろさかなって。
――翻訳家・エッセイストの岸本佐知子さんは、加納さんの文章を「言葉のサーカス」と評されていましたが、あのテーマもストーリーもぶっちぎったアクロバティックなしゃべり言葉の奔流は、お笑いをやってる人ならでは、という気がします。
小説に挑戦できたのは、5、6年前に岸本佐知子さんのエッセイや岸本さんが翻訳した海外小説と出合ったのが大きいんです。岸本さんのエッセイもそうなんですけど、岸本さんが翻訳してる海外文学って、これまで自分が読んできた海外文学とはまったく違う。たとえばスティーヴン・キングみたいな、物語としておもしろいとかじゃなく、ただただ言葉がおもしろい。テーマがどうとかも関係ない、「ただおもろいだけ」みたいな。手法としてはほとんどお笑いみたいな、私がめっちゃ好きな世界が小説にもあるんやということを知って、これなら自分も戦えるなって。難しいですけど楽しんでやってますね。
――こうしてお伺いしていると、加納さんの場合は表現でも日々のちょっとしたことでも、常に「おもしろがる」ことが第一にある気がします。
謙遜でもなんでもなく、私自身はおもろいやつでもなんでもないんですけど、何かをおもろがることに関しては、お笑いという仕事を抜きにしても得意な方かもしれません。たとえば、変なやつを変としか思わなければ、否定的な方向に向かいがちやけど、その変さをおもろがれば、フワッとでも肯定できる。自分のことも一緒ですよね。コンプレックスみたいなことも、おもろがってしまえば、あってないようなもんになるし。
――何かをおもろがることは、肯定することでもある。
なんでもどう見るかですよね。毎週ラジオをやってて思うんですけど、ネタになるようなことって、しょっちゅう起こらんし、ほんならもう感情を掘るしかない。嘘を付くわけではないけど、感情を掘って、無理矢理にでも膨らませておもろがる。大阪とか私の育った環境は、そういう筋肉が自然に鍛えられる環境やったんかもしれません。
――芸人さんの中には「おもろさ」をストイックに突き詰めるあまり「孤高の存在」みたいになっちゃう人もいますが、加納さんは仲間に囲まれて、楽しそうに活動されています。
やっぱり「機嫌よく」というのは、人生の優先順位のかなり上位にありますね。長年生きてて自分で自分の機嫌とられへんやつって、アホやなと思うんですよ。もちろん、うちらも若手のときは、いろんなことに対してずっとムカついてたし、ある程度結果が出た今やから言えることなんですけど。すごい売れてる大御所やのに、いまだにずっと怒ってる人とか見ると、なんのために稼いでんのやろなと思います(笑)。不機嫌も芸のうちみたいな職人的なことかもしれませんけど、私の場合、とにかく自分のことを嫌いになることが無理なんで。自分がどう見られるかよりは、自分が機嫌よくいられることを優先しちゃいますね。だから、決して努力家ではないけど、締切を守るとか「これやらへんかったら自分で自分のこと嫌いになる」と思うことは、全力でやるようにしてます(笑)。
――自己嫌悪に陥る前に、その状況を回避する。シンプルですが最良のライフハックですね。他に、日々機嫌よくいられるための秘訣はありますか?
自分の周りを好きなもので固めることですね。たとえば、職場でめちゃくちゃ嫌な人がいて、行くの嫌やなーみたいなことって、社会的には我慢してスルーしなあかんと思われがちですけど、実はめっちゃでかいことやと思うんです。嫌な感情が毎日、定時でやってくるというのは、人生においては絶対によくないと思うので、私の場合はできる限り排除します。人にしてもモノにしても、私は今、自分の周りに好きなものしかない環境をわがままに作らせてもらっているので、毎日機嫌よくいられてます。やっぱり、おもろくて機嫌がいいやつは、いろいろダメなところがあっても、最強やなって思いますね。

Aマッソ加納愛子さんのロングインタビュー前編はこちら
INFORMATION

『これはちゃうか』
加納愛子/著 河出書房新社 1540円
終わりのないおしゃべり、奇想天外な町。日常から一歩はみ出したホラーなど「加納節」を堪能できる短編小説集。文芸誌「文藝」に掲載した4篇に、書き下ろしを2篇加えた、全6篇。
インタビュー/井口啓子 撮影/大森忠明 スタイリング/渡邊アズ(kodomoe2023年6月号掲載)