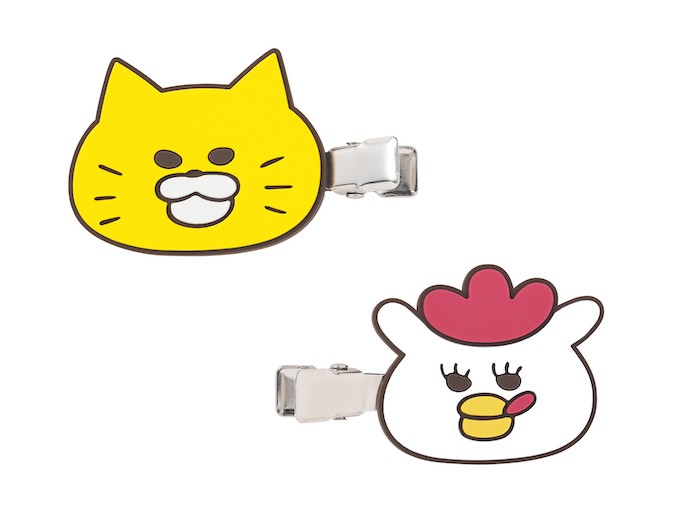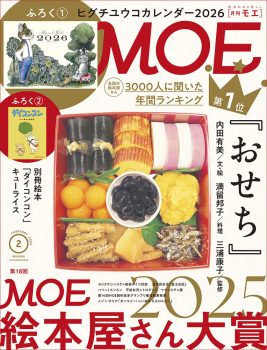社会学者・上野千鶴子さんロングインタビュー。学生運動、女性学との出合い、そして両親のこと【後編】
日本における女性学のパイオニア的存在である、上野千鶴子さん。『あなたたちのがんばりを、どうぞ自分が勝ち抜くためだけに使わないでください』と述べた、東京大学入学式(2019年)の祝辞が話題に。kodomoe2020年6月号でたっぷりと語ってもらったロングインタビューを、kodomoe webで全編公開いたします。
後編では、親元を離れて入学した大学生時代やご両親との関係についてのインタビューをご紹介します。
前編はこちら
うえのちづこ/1948年、富山県生まれ。社会学者。認定NPO法人ウィメンズアクションネットワーク理事長。東京大学名誉教授。日本における女性学、ジェンダー研究の第一人者。デビュー作は『セクシィ・ギャルの大研究』(岩波書店)。近刊に漫画家・田房永子さんとの共著『上野先生、フェミニズムについてゼロから教えてください!』(大和書房)、『介護保険が危ない!』(岩波書店)がある。
18歳で親元を離れる 全共闘運動の渦中へ
――1967年、京都大学文学部へ入学。これはご自身の選択です。
父は「娘は温室に入れて育てるもんです」と公言していたから、私の目の前にある選択肢は地元の金沢大学しかない。でも、「ここに行くと私は家から出られない」と思って必死だったから、すでに関西に出ていた兄と同居するという条件で第二の選択を見つけたの。
教育パパとママだから、両親と一緒に関西へ大学見学ツアーに行きましたよ。神戸女学院と関西学院と同志社と京大。父は神戸女学院を望んだけれど、私には女子大の選択はなし。で、関学に行くとシンメトリーの建物で……。あの美しさを見ただけで、やめておこうって。同志社では、男女のカップルが手をつないでた。京大に行ったら、みんなひとりずつ俯いて歩いてたの。その姿を見て「あ、ここは私の来るとこだ」と思った。18歳のとき。
――俯いて歩く姿が18歳の上野さんの心情そのものだった。
高校生のときから花田清輝や鶴見俊輔、林達夫を読んでいて頭の中は老成しているのに、常識も生活力もなーんにもないただの世間知らずでした。だから入学試験には母がついてきた。兄のところに一緒に泊まって、入試1日目、苦手意識があった数学の試験を終えて帰ったところで「お母さん、私受かるわ。ウンチして、ババつけてきた」と報告するような気楽な子どもだったのさ(笑)。
――さすが。お父さんはさぞ合格を喜ばれたでしょう。
「よかったね」とは言ったけれど、あとでオヤジは「ボクにとって入試は一番で合格するかだけが問題だった」と言ったので、唖然とした。さらに「お前が息子だったら京大ではなく東大に行かせた」。そのとき、初めて「お前が息子だったら」と言われたから、へえ〜って。
――東大の先生になったんですけどね(笑)。入学式にはご両親も。
もちろん、喜んでついてきた。子煩悩で親バカだから。そういう意味では、今の若い子たちのことは笑えません。私、すごく過保護でした。家ではちゃんとお料理したこともなくてね。今でも兄にからかわれるんだけれど、ふたりで暮らし始めた頃にお味噌汁を作ろうと、市場で「お味噌ふたり分ください」と買って。笹舟に載せてもらった味噌を、全部鍋に入れたの。薄めても薄めても飲めなくて(笑)。
――世間知らずなのに、早々にお兄さんの部屋から脱走します。
兄の友達が「上野の妹が来た」と、入れ代わり立ち代わりのぞきにくるんですよ。「お兄ちゃんのところにいると勉強できないー!」っ て、夏休みに必殺技を使いました。学生部で探した、大学のそばでお年寄りご夫婦の古いおうちの二階の学生下宿に移ったの。おじいちゃんおばあちゃんのいる茶の間を通らないと玄関には行けないようなところ。大家さんに「本当にもの静かで躾けのいいお嬢さん」と言われた。基本そうなの。
――そのお嬢さんが弾けたのが学生運動です。ちょうど全共闘運動が始まろうかという時期でした。
私のデモ初体験は1年の秋。全学連の学生と警官が羽田で衝突し、文学部の同期生だった山崎博昭君が死んだ。その追悼デモでした。彼とは面識はなかったけれど、普通に正義感の強い子どもだったらショックを受けるよね。それからは疾風怒濤。
そりゃあ、両親はものすごく心配しましたし、反対もしました。大家さんに「娘を監視してください」と頼みに来たりとか。入学後にワンゲル部に入ったときも、「危ないからやめろ」と反対された。兄が「学生運動やるより山登っているほうがマシだろ」とかばってくれましたが、結局、両方ともやっちゃいました。
敗北のあとの出会い
女は信じるに足りる
全共闘運動のピークは69年。1月に東大安田講堂が、半年後に京大のバリケードが機動隊によって解除される。72年、連合赤軍事件で政治の季節にピリオドが打たれた頃には、日本にもウーマンリブが芽吹いていた。だが、この時代の上野さんは「死んでいた」。

――70年初頭、田中美津さんがリブ新宿センターを立ち上げています。リブに参加するつもりは。
バリケードが解除されたあと、ものすごい敗北感にうちのめされ、1年間キャンパスに足が向かず休学しました。私があの運動の中で学んだことは、「ひとりになること」だった。
集団になったときの恐ろしさや、運動が退潮期にあらわれる人間の卑劣さを、とことん味わいました。白けていたし、特に女だけの集まりは気持ち悪く、リブの運動が始まってもこんなときにコレクティブなんてよく作れるね、と思ってた。就活なんて死んでもしたくない。だから向上心、向学心ゼロでしたが、大学院にモラトリアム入院しました。
――その時期には恋人と暮らされてますが、ご両親はさぞ気を揉まれたでしょう。
「困ったもんだ。ちゃんとできないのか」と言われましたが、こそこそやってたわけじゃない。あんまり思い出したくないけど、結婚を前提に相手の両親と親を引き合わせたりしましたよ。契約を結ぶつもりはさらさらなかったけど、一応親には報告しました。で、けじめはつけようと、同居と同時に親からの仕送りは断りました。
――えらい!
家庭教師に塾の講師、売り子さんもウェイトレスのバイトもいっぱいしましたが、貧乏しました。当時は自動振り込みなんてないから、ガス代の集金が来るときは部屋の中で息を潜めてた。
大学院にいることに何の意義も見つけることができなかったので、在学中に三度退学しようと思いました。そのつど思いとどまったのは奨学金があったから。25歳のある日、京都新聞の求人欄を開いたのね。見開き両面のうち8割が「男子のみ」。そこに「男女共」があると、求められているのはパチンコ店の住み込み夫婦。残りの「女子のみ」は、ホステスさんか経理事務で珠算簿記3級以上。ホステスやるには薹が立ってたし、珠算簿記なんてできない。新聞を見ながら、私には何の能力もない、無芸無能なんだと思い知りました。奨学金とバイトで食いつなぎ、男が働いていたから、生活力のない私は一時期養ってもらっていました。
大学に5年、大学院に5年、オーバードクター2年、計12年京大にいた。大学教員なら教員免許はいらないと気づいて就活を始め、平安女子短期大学の専任講師の職を得たときには30歳になっていた。
――12年の大学生活は長いです。
なんの展望もありませんでした。女には可能性がなかった。周囲の男たちの就職がどんどん決まっていくのを、「私と同じ程度に無能なのに就職先あるんだ。なんで私にはないのか」と見てた。あの当時、就職は指導教官からのお声がかりなんです。助手のポストが空いたとき、順当にいくと研究室で最年長の私に回ってくるはずなのに、後輩の男が就きました。
教授に呼び出されて「助手は雑用が多くて研究の妨げになり、キミには向かない」とこんこんと説かれました。言い訳がましかったので、「差別するなら堂々としろよ」と思いましたね。
ようやく公募が出始めて、それも形だけの公募と言われたけど、やっと重い腰を上げて応募し始めたんです。今でも覚えてる、受かったのは23通目だった。
――頼まれた推薦状や推薦文を断らないのは、そういう体験からですよね。女性学との出合いは。
20代後半の大学院時代に出合ってましたね。日本女性学研究会に誘われたとき、「気持ちわる〜」と思いながら「一回ぐらい付き合おうか」と出かけたら、女たちがとてもチャーミングだった。OL、主婦、教師、いろんな職業の人がいて、みな自立していて、知的で寛大で。それでハマって、「女遊び」したのよ。
それまで男と付き合うのは簡単だけど、女とはどう付き合っていいのかわからなかった。でも、おネエさんたちが本当に優しくしてくれて、ケーキ食べに行ったり、ショッピングしたり。どんなに楽しかったか。女が信じるに足りる生き物だと学んで、ひとりでいることから抜け出せた。あの頃の女たちには感謝してもしきれません。

共著『上野先生、フェミニズムについてゼロから教えてください!』についてくる、しおり。学生がアプリでかわいく加工した上野先生の写真が使われている
母と父を見送る
愛された記憶は贈り物
82年、消費社会を分析した『セクシィ・ギャルの大研究』でメディアデビュー。以来、教壇に立ちながら数多くの著作を出版、フェミニズムとジェンダー研究の扉を開け続けてきた。
――刺激的なタイトルのデビュー作は、社会学者としての研究成果でもあります。
あくなき人間への好奇心ゆえに社会学を選んだんですが、タイトルを見た両親は仰天して「うちみたいな堅い家からなぜあんな子が。お前の育て方が悪かったからだ」と父は母を責め、「あなたが甘やかしたから」と母は父を責め。
あとで、母が本屋さんから本をたくさん買って親戚縁者に「こういうふうに見えるけど真面目な本で」と配ったと聞き、親とはありがたいものだと思いました。
――やっぱり自慢の娘だったんだ。
まあ、結果的にね。70歳を過ぎた父がポツリと「女が働くのもいいもんだ」と言いました。だから父も変わったんだと思います。
――お母さんとの関係は。早くに亡くなられていますが。
乳ガンで病院を出たり入ったりで、私が43歳のときに亡くなりました。私は娘プレイができるのは2泊3日までで、3日目からキレるから、ずっと距離を置いて、できるだけ親のところに行かないように逃げてたの。
でも、母の最期の頃、かなり長く傍にいられたときがありました。あるとき、わぁ〜と気持ちが抑えられなくなって、「お母さん、私は家を出てから必死で自分を育て直したのよ」という言葉が口から出たの。そうしたら母は「なら、私の育て方がよかったんじゃないの」と言った。もうガーンよ。母という名には勝てやせぬ。
――お母さんは娘が自分をどう見てるか、おわかりでした?
それはわかってたでしょう。結婚もしない、出産もしない、仕事を続けている。「母のようになるまい」と娘が思っていることははっきりわかる。普通の親だから、私が30代の頃は「老後はどうするの?」と愚痴こぼしてたもの。同世代の母親たちの母娘関係を見ていると、十代の娘を持つことは内懐に棘を抱えて生きるようなものだと思えて耐えられない。私のような娘がいて、私に痛烈な批判を向けると考えるとそれだけで身がすくむ。「お母さん、イヤな娘でごめんなさい」と思っています。
――母を亡くした喪失感は。
ずっと離れていたからあんまりなかった。それより子どもたちにとって大問題だったのが、「残された父をどうしよう!」。父は、母が逝ってから孤独と失意のうちに10年生きました。
――激務の中、お父さんの看病に毎週末金沢に通っておられました。
父に愛された記憶があるから「この人が衰えて死んでいく姿をちゃんと見届けよう」と思いました。私が男と別れてから、父は嬉しそうな顔をして東京にも来て、「子どもはいつまでたっても子どもだ」と娘の家の中をあちこちいじくりまわしてましたよ。やっぱり、「愛された」というのは贈り物です。愛されずに、いやそれどころか疎まれて育った子どもたちのその後の傷の大きさ、トラウマを引きずる長さを見ていたら「ああ、自分は幸運だった」と思うしかないもの。運ですね。
さる方に「未熟な父の未熟な愛に振り回されて迷惑を被りました」と言うと、「未熟でない親がいますか」って。素晴らしい台詞。
――父を亡くした喪失感は。
ありません。それどころか肩の荷が下りました。いろんな人にいろんな言葉をかけてもらったけど、一番嬉しかったのは「親より先に死なないのが子の務め。立派に務めを果されましたね」でした。そういう言葉を言ってあげられる人になりたいと思いました。
――上野さんにとって親とはどんな存在なんでしょう。
はた迷惑(笑)。子どもは親を選べませんから、親の役割はできるだけはた迷惑を減らすこと。具体的には「介入と干渉をできるだけしない」。子どもを産んだ人に「『この子を置いて死ねない』って、いつ思わなくなる?」と聞いてまわったことがあるの。「結婚させてから」とか「小学校に上がったとき」とか「3歳のとき」とかいろいろ答えはあったけど、「身二つになったとき」と答えた人もいた。
そういう答えは超レア、見事な覚悟だと思った。子どもは自分とは「別の人」で、たまたま縁あって今暮らしを共にしているだけだから、できるだけ相手の迷惑にならないようにと考えることができればいいと思う。
津島佑子さんの『山を走る女』には、シングルマザーになってからまた恋愛して、そのすったもんだを子どもの前で見せる母親が出てきます。「こうやって母親の人生に巻き込まれるのがこの子の運命」とあって、それは母の気構えとしてはいいけれど、自分が「迷惑な存在」という自覚は持ってほしい。子どもは絶対的な弱者だから。そうして、できるだけ迷惑の分量を減らすことです。
――最後の質問は「男の子と女の子の育て方に違いはあるのか」です。
基本のキは変わらないと思うけど、女の子には特に「翼を折らない」育て方をしなきゃね。だって、これっぽっちも教えたことがないのに、保育園の5歳児が取っ組み合いをしたシングルマザーの母親に組み敷かれて「女のくせにぃー」て言ったというからね。
世の中いくらか変わってきてはいても、こういう価値観は再生産される。女の子にも男の子にも一歩外に出たら、そういう環境が待っているということ。だから、女の子は世間に押しつぶされないような育て方をしてほしい。
――フェミニストの上野さんが学生に教えてきたことと同じです。
そうですね。私が教えてきた基本は「自分を大事にしなさい」ということです。自分を大事にできない人は、他人も大事にできませんから。
インタビュー/島﨑 今日子 撮影/馬場わかな(kodomoe2020年6月号掲載)







KV修正-350x350.jpg)