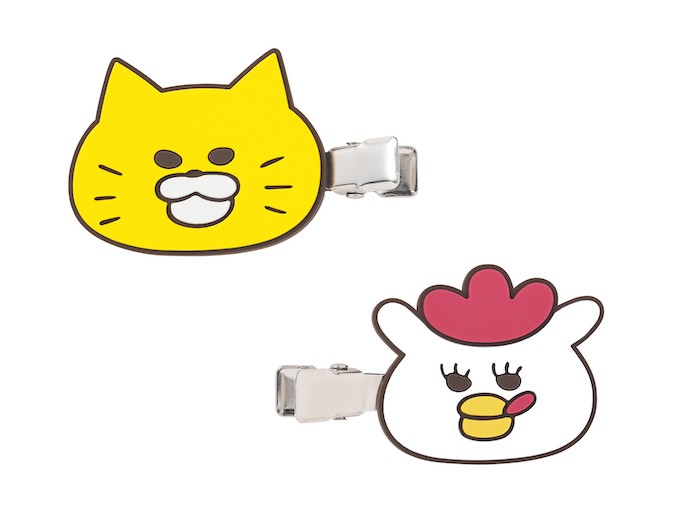小泉今日子さんロングインタビュー。原点はやっぱり家族。 両親や姉がここまで 引っ張り上げてくれた【前編】
1982年にデビューして以来、約40年にもわたり第一線で活躍する小泉今日子さん。「キョンキョン」の愛称で愛され続ける小泉さんに、生まれ育った街・神奈川県厚木市のこと、ご両親のこと、そしてデビューのきっかけとなった伝説のオーディションについて伺いました。たっぷりとお話をおうかがいしたkodomoe12月号から、kodomoe webでは全編公開。今回は前編をお届けします。
後編はこちらから
こいずみきょうこ/俳優、アーティスト。神奈川県出身。オーディション番組『スター誕生』に出場、グランプリを獲得してデビュー。トップアイドルとして人気を集める。俳優としてテレビドラマ、映画などに多く出演。2015年に舞台や音楽などのエンターテインメント作品をプロデュースする会社「明後日」を立ち上げ、代表取締役を務める。

『SPY×FAMILY』みたい
干渉し合わない家族でした
歌手であり、俳優であり、近年は自身の制作会社を立ち上げ、舞台や映画のプロデューサーとしても活躍する小泉今日子さん。デビューから40年以上にわたって芸能界のトップランナーであり、その一挙手一投足が常にニュースになる存在でもある。そんな彼女に、自身の原動力は? と問うと、ちょっと考えてからこう答えた。「結局、厚木なんだと思う」。厚木は神奈川県の中央に位置する市であり、彼女が生まれ育った街である。彼女が書いた歌詞に倣うなら、心帰る場所、『マイスイートホーム』。そこで、キョンキョンという希代のポップアイコンのベースである、彼女の子ども時代の話を中心に聞いてみることにした。
――1966年2月生まれですよね。
はい。丙午の水瓶座です。両親と姉が2人いて、三人姉妹の末っ子として生まれました。
――厚木のどの辺で育ちましたか。
生まれたときは街中の、本厚木駅近くにある「はとぽっぽ公園」、正式名称は「厚木公園」なんですが、その近くに住んでました。当時は何軒か平屋建ての借家があって、我が家はそのうちの一軒。2歳まではそこで、その後、厚木市郊外へ。父が親族から土地を譲り受け、マイホームを建てたんです。
――お父さんも厚木のご出身?
そうです。父は次男で、本家は長男が継いでいて。だから私は15歳で仕事を始めるまで、基本、郊外のマイホームに住んでました
――仲良し三姉妹でしたか?
どうだろう。特別に仲良かったわけでもなければ、仲が悪かったわけでもなく。極めて普通(笑)。ただ、2番目の姉とは2歳違いですが、1番上の長姉とは8歳違うので、「この人がお母さんだ」と錯覚していた時期があって(笑)。
私、幼い頃に周期性嘔吐症を患っていたんです。小っちゃい子がよくなる病気ですが、簡単にいうと吐きやすい子ども。何かというとすぐに吐いちゃう。夜寝ててもゲロゲロって(笑)。眠りながらも、ああ、どうしよう、吐いちゃった、という自覚はあるけど、寝てるからどうすることもできずにいると、誰かが拭いてくれたり、背中をさすってくれたりする。ああ、こういうことをしてくれるのは「お母さん」なんだろうとずっと思ってたんですが、ある日目を開けてみたら長姉だった。「ああ、そうか、お姉ちゃんが『お母さん』だったんだ」っていう錯覚(笑)。
――お母さんはあんまり面倒を見てくれなかった?
というわけではないんです。母は母なりに面倒を見てくれましたし、ごはんも作ってくれました。でも、ちょっと浮いているところがあって。基本、お洒落な人なんです。コーヒーもサイフォンで淹れるし、細いタバコを吸ってるし、毎日喫茶店へ行ってインベーダーゲームをやってるし(笑)。娘の私から見ても「洒落てんなー」って。だから、世間一般でいう「お母さん」のイメージとはちょっと違っているから、長姉が「お母さん」の方が納得できるなって。長姉はすでに他界しましたが、彼女が亡くなるまでずっとその感覚は持っていたんです。私が一人暮らしを始めるときには裁縫セットを持たせてくれたし、私が二十歳になったときに真珠のネックレスとピアスのセットをくれた。私が結婚したときには色無地の着物に合わせるバッグと草履のセットをくれたのも長姉だったんです。
――大人の女性が持ってて然るべきものを全部持たせてくれた。
普通なら、母親がやることを全部やってくれたんです。母は、なんかピントがズレているというか。誕生日のプレゼントに東南アジアの工芸品のような象の彫り物をくれる人(笑)。自分がカッコいいと思うものをくれるんですけど。
――お母さんは専業主婦だったんですか? それとも何かお仕事を?
ずっと専業主婦でした。私が中学2年生のときに一家離散するんですが、それまでは専業主婦。父が小さな会社を経営していて、その手伝いをしたりしてました。

小泉さんの父はカセットテープを作る会社を経営していたという。本社は東京・世田谷区にあり、その工場が厚木の自宅そばにあった。「小さな工場ですが、プレハブの建物が2棟あって。近所の主婦たちがパートでやってくるので、母がそのケアをしていたり」。ただ、母にとっては不慣れな仕事、それなりにストレスを抱えていたのでは、と小泉さんは振り返る。
もともと芸者だったんです、母は。厚木の飯山温泉で。私の大叔母がそこで置屋をやっていたので。だから、父の会社が経営難に陥ったとき、昔から知ってる芸者仲間が経営するスナックでバイトを始めて。その後、そのまま自分も店を持つようになるんです。
実は、母も一家離散を経験していて。母が10代の頃、母の父、つまり、私のお祖父ちゃんが出奔しちゃったんです。それで長女の母が、大叔母の養女となり芸者を始めて。だから水商売は何となく肌に合ってたんじゃないかな。結婚してからは主婦になり、子どもたちのお母さんたちと交流して、学校のPTA活動だったり地域の子ども会のことだったり、父の会社の手伝いも含め一生懸命やっていたんです。でも本当に仲が良かったのは、芸者時代のお友達。美容院の先生とか、スナックのママさんとか。そういう人たちと一緒にいる方が居心地がよかったんだと思う。だから、父の会社がうまくいかなくなったとき、借金取りが家に来ると厄介だから、父とは別の場所に暮らす方がいいと、母と私たち三姉妹は狭いアパートへ引っ越すことになったんです。そのとき、母はパッとそっち側へ行き、仲間たちがパッと助けてくれた、そんな感じだったと思います。
――じゃあ、お父さんの仕事がうまくいかなくなるまでは仲良く?
ごく普通の5人家族、だと思ってました(笑)。でもやっぱり、なんかちょっと友達の家とは様子が違うな、みたいな感じはあって。例えば、「サンタクロースにもらったもので覚えているものはありますか?」みたいな質問をされることがあるんですけど、「いやうち、サンタクロースなんて来たことないですけど」って(笑)。父が扮装して「サンタだぞ」なんてやって来たりしたら、家族全員で「はあ?」って言っちゃう、そんな家庭だった。大人が子どもを子どもとして扱って育てる、そういう環境ではなかったんです。全員対等、みたいな。とってもドライに感じるかもしれないけれど、でも、それが逆に私は心地よかった。
だから、夜、「眠れない」と言うと母が絵本を読もうとするから、「いや、ちょっと、それだけはやめて」と言ってました。読まれちゃったら2番目の姉と2人でゲラゲラ笑い出しちゃうんです。母が急に母親を演じるような感じになるので。「あなた、そういう人じゃないでしょ」って(笑)。
――お父さんはどんな存在だったんですか、家の中では。
男一人だったので、大事にされてました。晩ごはんになると、母はまず父に出すんです。晩酌用のおつまみとお酒を。その後に私たちのごはんを作る。テレビのチャンネル権も父が持っていて。ちぇっ、また野球のシーズンか、『3年B組金八先生』観たいのに! って(笑)。そして、やっぱり家族の中ではいちばん物知り。いつも新聞を隅々まで読んでいたし、何か質問をしたらちゃんと答えてくれる。ただ無口ではありました。そして、ちょっとだけ、プチ酒乱。それを唯一私が受け継いでいるんです(笑)。でも、それは家での父で、仕事場ではどんな人かは知らなかった。父が亡くなって、お葬式で仕事関係の人たちに会ったとき、「お酒ですごく迷惑をかけましたよね?」って恐る恐る聞いたら、「いやいや、酒癖は全然悪くなかったよ」って。お父さん、家に帰るまで頑張ってたんだね、っていう結論(笑)。
――内弁慶だったんですね。
ホントに。あと、私が小学生のとき、父親が見に来る授業参観があって、クラスの多数決で体育をやることになったんです。私はものすごく体育が苦手なのに、跳び箱を跳んで台上で前転をする、みたいな授業になっちゃって。出来た人から座っていくから、案の定、私ともう1人の女の子だけが取り残されてしまったんです。あの人、どんな気持ちで見てるんだろうと思って父の方を振り返ったら、あれ? いない? すると、父が学校を出ていく姿が見えたんです。ああ、帰るんだ。でしょうね。いたたまれないでしょうね。いいと思う、帰って。っていう関係(笑)。だから、家族全員内弁慶というか、他人行儀というか。
――あまり干渉し合わない?
街で姉とすれ違っても絶対に声をかけ合ったりしないんです。でも、あるとき一度だけ、声をかけられたことがあるんです。中学生の頃だったかな。2番目の姉は高校生。ものすごくびっくりして、「えっ!?」て言ったら、姉が「傘」って。「傘貸して」「いやいや、雨降ってるし、私も使うし」「お前の友達、持ってんじゃん」「ああ……。じゃあ、まあ」って渋々傘を渡した、っていう(笑)。
あと、これも中学生の頃ですが、学校をサボって友達と一緒にファミレスに行ったんです。すると父が誰かと商談をしていて。そのときも声をかけ合わず、他人のふり。それで家に帰ってから、父が「お前、お金持ってたの?」「うん」。それだけ。学校サボっただろ、とかそういうことは全然言わないんです。なんかこう、『SPY×FAMILY』みたいな感じ(笑)。
――本物の家族として世間に振る舞う偽装の家族の(笑)。
そう。面白いのは、2番目の姉がちょっとヤンチャだった時期があって、親が学校からよく呼び出しをくらってたんですが、そうすると父が嬉々として行くんです。スパイだから顔はポーカーフェイス。でも内心はワックワク。こりゃ面白いことになった! 潜入してくる!っていう感じ(笑)。
たぶん、普通の感覚や常識みたいなものにとらわれない親だったんです、2人とも。「勉強しろ」なんて言われたことがないし、他の子と比べられたりすることもなく。だから、学校でアニメキャラの飛び出す筆箱が流行ったときに、私も欲しいと思って父と母に言ったんです。「この筆箱買って」って。すると「なんで?」って。「みんな持ってるから」って言うと、「意味わかんない。あんた、ホントにそれでいいの?」。でも私はゴリ押しで買ってもらって。すると、すぐに飽きちゃったんです。そして私は、やっぱ親の言うことは正しかったんだな、と静かに自省しながら我慢してその筆箱を使い続ける、という(笑)。
――結果、素晴らしい教育方針だった、と言えますけれど(笑)。
意図していたわけではなかったと思います。とにかく私は「決められない」子だったので。姉たちは趣味嗜好がはっきりしてるから、洋服も「私はこれ」ってすぐに決めるんです。私はなんかもうずっと迷ってる。こっちもかわいいけどあっちもかわいい、どうしよう。ただ、気を遣うタイプでもあるので、最終的には値段を見て、じゃあ安い方、ってなるんです。すると母が「今何した? 値段見たでしょ」って。「どっちもいいから、安い方がいいと思って」と言うと、「私、そういうの大っ嫌い。じゃあ両方買ってやる」(笑)。
――江戸っ子的な気っ風で。
「ひ」が言えなくて「し」って言ってましたから(笑)。とにかく、私はそういう人間なので、自分の人生を誰かに導かれてここまでやって来たんだ、とよく思うんです。オーディションに応募したのは友達に「キョンキョンも出しなよ」と言われたことがきっかけだったし、お仕事を始めてからは、レコード会社のディレクターだったり、クリエイターの方々だったり、演出家だったり映画監督だったり。時代時代で出会った人々がみんな私を先導して連れて来てくれた。だから、そのスタートは、原点はどうだったかと振り返れば、それはやっぱり、家族。他人行儀ではあったけど、「決められない子」に「何やってんの」って言いつつ、引っ張り上げてくれていたのは、姉たちや両親だったなって。
BOOK INFORMATION

『ホントのコイズミさん WANDERING』
小泉今日子/編著 303BOOKS 1650円
Podcast番組「ホントのコイズミさん」の書籍化第二弾。作家・吉本ばななや写真家・佐藤健寿らとのトークが活字と写真でよみがえる。第三弾は今冬に発売予定。番組はSpotifyで配信中。
インタビュー/辛島いづみ 撮影/馬場わかな スタイリング/藤谷のりこ ヘアメイク/石田あゆみ(kodomoe2023年12月号掲載)