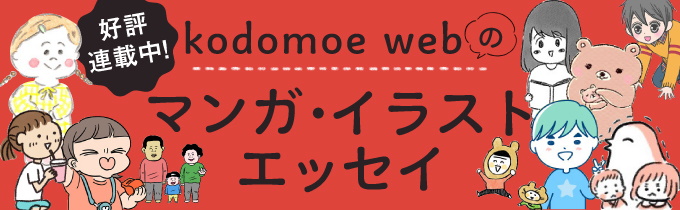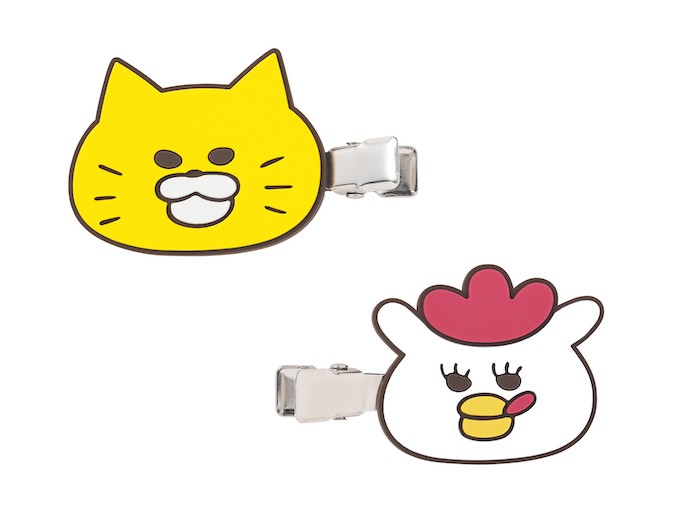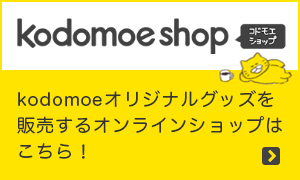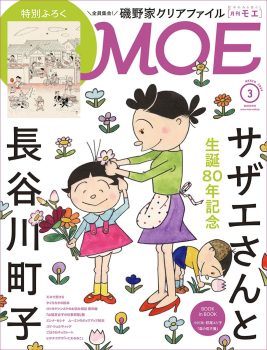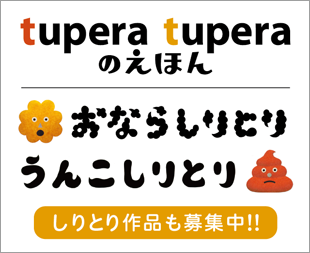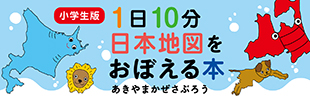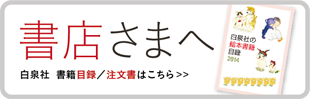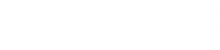昔は村にひとつのパン窯で村人全員分のパンを協働で焼いたとか。ドイツ伝統のパン作りで思うこと【タベコト in Berlin・112】
ベルリン在住で6人の子どものお母さん。モデルとして活躍する傍ら「台所から子育て、暮らしを豊かに」をコンセプトに、オンライン講座とウェブサイトを主宰している日登美さんによる、「食」からはじまるエッセイです。
ドイツ伝統のパン作りを習う
いよいよ寒くなってきて、クリスマスまでカウントダウンの始まったベルリン。こうなると、焼き菓子にパンにと多くの家庭でクリスマスの準備が始まります。

パン焼きの前にザワークラウトも作ったのです。どの国も独自の発酵文化があって面白い!
ドイツではクリスマスの準備は11月から始めるのが一般的。スーパーには10月頃から既にシュトレンの材料、クリスマス菓子に使われるスパイスやドライフルーツなどが店頭に並びます。日本でも人気のシュトレンですが、焼いてすぐには食べられない、というか食べないものだと、昔ドイツ人の夫に聞いて驚いたのを覚えていますが、この時期はそんな保存のきく楽しいお菓子があふれているのです。

焼き上がったライ麦100%の全粒粉サワードウパン。これぞドイツスタンダード!
そんな焼き菓子の勢いに押され、やりたいと思ってずっと先延ばしにしていたサワードウのパン作りを教えてもらいにいきました。ドイツではパンといえば黒パン。つまり全粒粉なんです。白いふわふわしたパンやトーストなどは、ほとんどの家庭で食べていない。これもドイツに来たとき衝撃でした。日本人の感覚でいうと、みんなが玄米を食べてるという感じかしら?

全粒スペルトパンも焼いたよ。もっちり美味しくて全粒粉っぽさもない。これが家で食べられるって最高!
そんなわけで友人に教えてもらい、分けてもらったサワー種ももちろん全粒。なんなら家で粉を挽いている! 基本的にパンはパン屋で買うことが主流のベルリンで、伝統的に家庭で焼き続けているパンを教えてもらえたのはとってもラッキー。毎日はできないけど、これはこれでやっぱり習っておきたい技術です。

昔のドイツの粉挽水車小屋の内部。小麦とパンは歴史の上でも重要なドイツ。
昔のドイツの村では、村に一軒パン焼き窯があって、そこで村人全員分のパンを焼いていたそうで、そんなふうに協働作業で、どこかでまとめて作るっていうのも、それぞれの負担が少なくていいので、すごくいいなぁと思っているのですが、同時にこうして自分でできるという良さもある。
食卓で楽をするのもいいけれど、それで伝統や文化を知らないまま終わるのは何だかもったいない。何より自分でできることが増えると、安心感が増えるんです!

昔は村ごとにあったというパン焼き小屋。大きな桶に粉を入れて発酵させてたらしい。
だから、どちらかにこだわらず時と場合に応じて、伝統を紡いだり、楽をしたりしながら、美味しく楽しい、いろんな台所のあり方を紡いでいきたいなぁとあらためて思った1日でした。

日登美/ひとみ
3男3女6児の母。10代よりファッションモデルとして雑誌、広告等で活躍。その後自身の子育てから学んだ、シュタイナー教育、マクロビオティック、ヨガなどを取り入れた自然な暮らしと子育てを提案した書籍、レシピ本など多数出版。現在はモデルとして活躍する傍ら、オーガニック、ナチュラル、ヘルシーをモットーに、食、暮らしと子育てのワークショップ、オンライン講座などを行う。
台所から子育て、暮らしを豊かに。「Mitte(ミッテ)」
instagram / @hitomihigashi_b
音声プラットホームvoicyで「日登美のイロイロ子育てラジオ」発信開始!







KV修正-350x350.jpg)